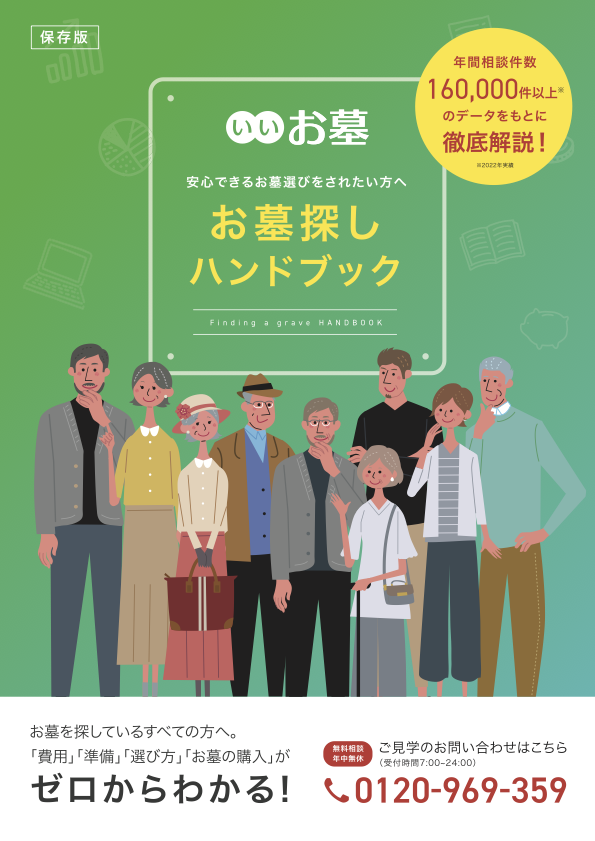「故人は死後すぐに成仏する」とされている浄土真宗には、永代供養という考え方がありません。ですが実際は、お墓の種類や納骨方法、霊園・寺院の選び方によって、浄土真宗でも永代供養墓を利用できます。
この記事では、浄土真宗における永代供養の考え方や永代経との違い、浄土真宗で永代供養する方法などを解説します。
浄土真宗で永代供養はできない?
浄土真宗では、故人は阿弥陀仏の導きによって死後すぐに成仏し、極楽浄土で生まれ変わるとされています。死者の成仏を願う必要がないため、浄土真宗にはそもそも「供養」という考え方がありません。
他の宗派では、故人は亡くなってから四十九日まで、御霊としてこの世とあの世のはざまに留まっているとされています。そのため、遺族は故人が成仏できるよう、お墓参りや読経などの「供養」を行うのです。
ただ、「供養」の概念がない浄土真宗でも、方法次第で永代供養を利用できます。たとえば、永代供養のついたお墓は「永代供養墓」と呼ばれ、霊園・寺院によって定義が違います。後継者のいない人のためのお墓を「永代供養墓」と定義し、利用者を募集している浄土真宗の寺院もあるので、探してみるとよいでしょう。
浄土真宗で永代供養をする方法

- 宗派の本山に納骨する
- 供養塔があるお寺に納骨する
- 宗教不問のお墓に納骨する
浄土真宗で永代供養をする方法は、大きく3つ。厳密には永代供養ではないですが、お墓の後継者が不要で管理を任せられるため、永代供養の代わりになる納骨方法です。浄土真宗で永代供養を希望している方は、ぜひ参考にしてください。
宗派の本山に納骨する
開祖の墓所がある仏教宗派の本山に、故人の遺骨の一部または全部を埋葬します。浄土真宗では、本願寺派と真宗大谷派で、総本山の場所や納め方が違うので注意してください。
浄土真宗の開祖・親鸞が眠る廟所として、浄土真宗本願寺派は西本願寺(龍谷山本願寺)、真宗大谷派は東本願寺(真宗本廟)に納骨します。また、浄土真宗本願寺派は分骨または全骨、真宗大谷派は、納められる遺骨の量が決まっているため、分骨で納めます。
供養塔があるお寺に納骨する
供養塔とは、引き取り手のない遺骨を納めるために建てられた石造りの塔で、五重塔や五輪塔などさまざまな形があります。
浄土真宗でお墓の継承者がいないなら、供養塔のあるお寺に納骨するのもひとつの方法。供養塔なら、永代供養と同じようにお寺が遺骨を管理し、手厚く供養してくれます。お墓の継承に悩んでいる人のために、供養塔を建立している浄土真宗の寺院もあるので、探してみてください。
宗教不問のお墓に納骨する
永代供養つきの合祀墓や樹木葬、納骨堂などは、宗旨宗派に関係なく利用できるお墓が多いです。浄土真宗でも、永代供養墓は宗派不問で利用を許しているお寺があります。
また、浄土真宗のお寺にこだわらないなら、宗教・宗派不問で永代供養を受け入れている寺院・霊園に納骨するのもひとつの手です。浄土真宗で永代供養を考えているなら、お墓の種類や霊園の形態にも視野に入れて検討してみましょう。
浄土真宗の永代供養にかかる費用
- 合祀墓(共同墓)
- 集合墓
- 単独墓(個人墓)
永代供養墓は、大きく合祀墓(共同墓)、集合墓、単独墓(個人墓)の3種類に分けられます。
永代供養料にかかる費用は、遺骨を収蔵する面積や墓石の有無によって変動するのが一般的です。3つの永代供養墓の違いや費用を確認しておきましょう。
合祀墓(共同墓)

合祀墓(共同墓)とは、1つの墓標の下に、不特定多数の遺骨をまとめて埋葬するお墓。
合祀墓にかかる費用の相場は5万円〜30万円で、永代供養墓ではもっとも費用が安いです。個別の墓石や納骨するスペースがなく、他の遺骨と一緒に埋葬されるため、管理の手間がかからないぶん費用が安くなっています。
ただし合祀墓は、血縁関係者ではない他人とまとめて埋葬されます。また、遺骨を骨壺から取り出して埋葬するため、一度合祀すると故人の遺骨を取り出せません。合祀墓を選ぶときは、デメリットも理解したうえで、家族・親族と相談してから判断するのが大切です。
また、単独墓と集合墓は契約期間が終わると、合祀墓として他の遺骨と一緒に埋葬されます。
合祀墓にかかる費用の例
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 永代供養料 | 10万円 |
| 納骨料 | 5万円 |
| 刻字料 | 3万円 |
集合墓

集合墓とは、1つの墓標(石碑や塔、樹木など)の下に、個別の収骨スペースが用意されたお墓。墓標は共有ですが、遺骨は個別に管理されます。単独墓と同じく、永代にわたって個別管理される場合と、契約期間が過ぎたら合祀される場合があります。
個々の墓石が必要ないため、単独墓より安く納骨できるのがメリット。集合墓の費用相場は20万円~60万円なので、費用をおさえて個別の納骨スペースを確保できます。
集合墓にかかる費用の例
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 永代供養料 | 20万円 |
| 納骨料 | 5万円 |
| 刻字料 | 3万円 |
単独墓(個人墓)

単独墓(個人墓)は、従来のお墓と同様に、個別の墓石を建てて納骨するお墓です。永代にわたって個別管理される場合と、契約期間が過ぎたら合祀される場合があります。
単独墓は、個々の墓石があるため、家族だけで納骨できるのがメリット。ただ墓石が必要なぶん費用が高額になりやすく、単独墓の費用相場は50万円〜150万円です。
また、他の永代供養墓に比べて埋蔵にかかる面積が大きくなるため、永代供養料も高くなります。その他、単独墓は年間管理料がかかる可能性もあるので、契約内容をよく確認しておきましょう。
単独墓にかかる費用の例
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 永代供養料 | 40万円 |
| 墓石料 | 50万円 |
| 納骨料 | 5万円 |
| 刻字料 | 3万円 |
浄土真宗で永代供養する流れ
- 家族・親族で話し合いをする
- 墓地管理者へ墓じまいの意思を伝える
- 新しい納骨先を決める
- 墓石撤去を依頼する石材店を決める
- 改葬許可申請の手続きを行う
- 遷仏法要を行う
- 墓石を撤去して土地を返還する
- 改葬先に遺骨を納める
浄土真宗の方が永代供養をする場合、先祖代々のお墓を墓じまいしたあと、永代供養墓に改葬するのが一般的です。墓じまいとは、先祖代々のお墓を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還すること。改葬とは、お墓から取り出した遺骨を別のお墓に移動させることです。
浄土真宗で墓じまいをして、永代供養墓に移動するまでの流れは大きく8つのステップに分かれます。
1.家族・親族で話し合いをする
まずは家族・親族で話し合い、墓じまいや改葬について同意を得ておきましょう。家族・親族の同意を得ておくことで、無用なトラブルを避けられます。
2.墓地管理者へ墓じまいの意思を伝える
先祖代々のお墓を管理している霊園・寺院に、墓じまいの意思を伝えます。また、霊園・寺院の管理者から「埋蔵証明書(埋葬証明書)」を交付してもらいましょう。
3.新しい納骨先を決める
既存のお墓から取り出した遺骨の納骨先を決定します。浄土真宗で永代供養を考えているなら、永代供養墓を扱っている霊園・寺院を探しましょう。永代供養墓や供養塔のある浄土真宗のお寺もあります。
4.墓石撤去を依頼する石材店を決める
墓石の撤去作業をお願いする石材店を決定します。霊園・寺院によっては、利用できる石材店が決められているため、事前に確認してください。石材店の指定がないなら、複数の石材店から見積もりを取り、比較検討するのがおすすめです。
5.改葬許可申請の手続きを行う
「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点を市区町村に提出し、「改葬許可証」を交付してもらいます。「埋蔵証明書」は現在のお墓の管理者、「受入証明書」は新しい納骨先の管理者、「改葬許可申請書」は役所で手に入るので確認してください。
6.遷仏法要を行う
他の仏教宗派では、お墓から遺骨を取り出すときに「閉眼供養」を行います。閉眼供養とはお墓に宿っている魂を抜くための供養。供養の概念のない浄土真宗では、閉眼供養の代わりに遷仏法要を行います。
7.墓石を撤去して土地を返還する
遺骨を取り出したら、墓石を撤去して墓所を更地にします。工事が完了したら、土地の使用権を霊園・お寺の管理者に返還しましょう。
8.改葬先に遺骨を納める
新しい改葬先の管理者に「改葬許可証」を提出し、お墓に遺骨を納めます。
浄土真宗の永代経とは?永代供養との違い
永代供養と似た言葉として、浄土真宗の「永代経」があります。永代経とは「永代読経」を略した言葉。仏の教えを代々伝えるため、永代にわたってお経を読むことを意味します。
浄土真宗の永代経は、死者を浄土へ導いてくれた阿弥陀如来に感謝を表すために読むお経です。死者の供養を目的に読経する他宗派と違い、浄土真宗では阿弥陀如来の繁栄を願って永代経を唱えます。
永代供養と永代経の違い
- 永代供養:霊園・寺院に遺骨を供養してもらうこと(供養方法)
- 永代経:永代にわたってお経が読まれること(お経)
永代供養とは、永代にわたって寺院・霊園に遺骨を供養してもらうこと。対して永代経とは、永代にわたって信徒からお経が読まれることです。
永代供養は供養方法、永代経はお経を指すので、そもそも意味がまったく異なります。また、永代供養は故人の冥福を祈るのが目的ですが、永代経は仏の教えを伝えるのが目的です。
永代経法要のお布施
浄土真宗では、永代経を読んで仏様の教えが代々受け継がれることを願う「永代経法要」が行われます。永代経法要では、永代経を読んでくださった僧侶にお布施として「永代経懇志(えいたいきょうこんし)」を渡すのがマナーです。
永代経懇志は、僧侶への感謝を示す金銭なので、本来決まった金額はありません。ただ相場金額は3万円〜10万円とされています。永代経をお願いする寺院の方針や関係性によって包む金額が違うため、お寺や門徒総代に確認しておくと安心です。
永代経のお布施のマナー
永代経法要のお布施である永代経懇志は、白い無地の封筒に入れてお渡しするのが一般的。地域によっては、紅白や黄白の水引をつけてお渡しするようです。
永代経懇志の表書きは、「永代経懇志」または「永代懇志」と書きます。故人がご逝去した法要でお渡しするなら、表書きの右横に小さく故人の戒名を記載してください。また、表書きの下には永代経懇志を納める方のフルネームを記入します。
そもそも永代供養・永代供養墓とは?

永代供養とは、霊園や寺院が永代にわたって遺骨を管理・供養すること。永代供養のついたお墓を「永代供養墓」と呼びます。お墓の維持が難しかったり、お墓参りできなかったりする遺族に代わって、霊園・寺院が遺骨を管理してくれます。
永代供養にするとお墓の継承が不要なので、子どもや身寄りのない方を中心に人気です。また墓石のお墓以外の選択肢が多く、比較的費用をおさえやすいのも特徴。永代供養のついたお墓は、「後継者がいらなくて費用も少なく済むお墓」として注目されています。
ただし、永代といっても未来永劫ではなく、33回忌までを期限とするのが一般的です。また、5年や10年といった短期間で契約できる霊園・寺院もあります。契約期間を過ぎた遺骨は、合祀墓に合祀(骨壺から遺骨を取り出し、他人の遺骨とまとめて埋葬する)されることが多いです。契約期間が過ぎた後の対応は寺院・霊園で異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
浄土真宗と浄土宗の違い
| 浄土真宗 | 浄土宗 | |
|---|---|---|
| 開祖 | 親鸞 | 法然 |
| 成仏 | 死後すぐに成仏 | 四十九日後に成仏 |
| 追善供養 | 不要 | 必要 |
法然を開祖とする浄土宗は、「南無阿弥陀仏を唱えれば誰でも極楽浄土に往生できる」という「専修念仏」の考えが基本となっています。対して浄土真宗の開祖親鸞は、法然の専修念仏をさらに発展させ、「阿弥陀仏を信じれば誰でも極楽浄土に往生できる」と説きました。
それぞれの教えの違いから、浄土宗と浄土真宗では成仏のタイミングや追善供養の有無が異なります。
浄土宗では、一般的な仏教宗派と同様、故人の魂は49日後に成仏するとされています。故人が極楽浄土に旅立てるよう、法要や読経などで追善供養して手助けするのです。浄土真宗では、故人は死後すぐに成仏するため、追善供養が必要ありません。浄土真宗における法要は、故人を極楽浄土へ導く阿弥陀仏に感謝を伝えるために執り行います。
浄土真宗の永代供養についてのよくある質問
浄土真宗で永代供養はできる?
浄土真宗に「供養」の概念はありませんが、「永代供養墓」を利用することは可能です。
永代供養墓とは永代供養のついたお墓で、霊園・寺院によって定義が違います。後継者がいない人のためのお墓を「永代供養墓」と呼ぶこともあり、永代供養墓を募集している浄土真宗のお寺も存在します。浄土真宗で永代供養を希望している方は、受け入れしている寺院・霊園を探してみましょう。
浄土真宗で永代供養以外で納骨するには?
- 宗派の本山に納骨する
- 供養塔があるお寺に納骨する
- 宗教不問のお墓に納骨する
浄土真宗では、永代供養の代わりとなる納骨方法として、3つの方法があります。1つ目は、浄土真宗の本山に納骨すること。2つ目は、供養塔のある浄土真宗のお寺に納骨すること。3つ目は、宗旨宗派不問で受け入れている霊園やお墓に納骨することです。
どの方法も、納骨することで遺骨の管理・供養を永続的に任せられます。
全国の永代供養墓ランキング
全国の永代供養墓のランキングをご紹介します。永代供養墓をご検討の場合は参考にしてみてください。
関東












関西







中部




北海道・東北


中国・四国


九州・沖縄





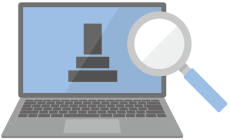
 かんたん
かんたん