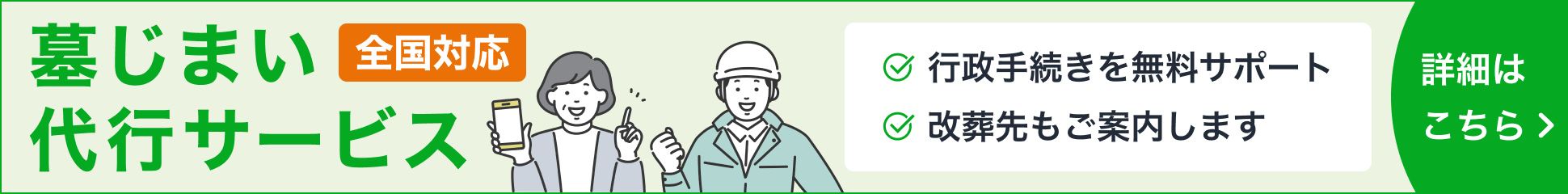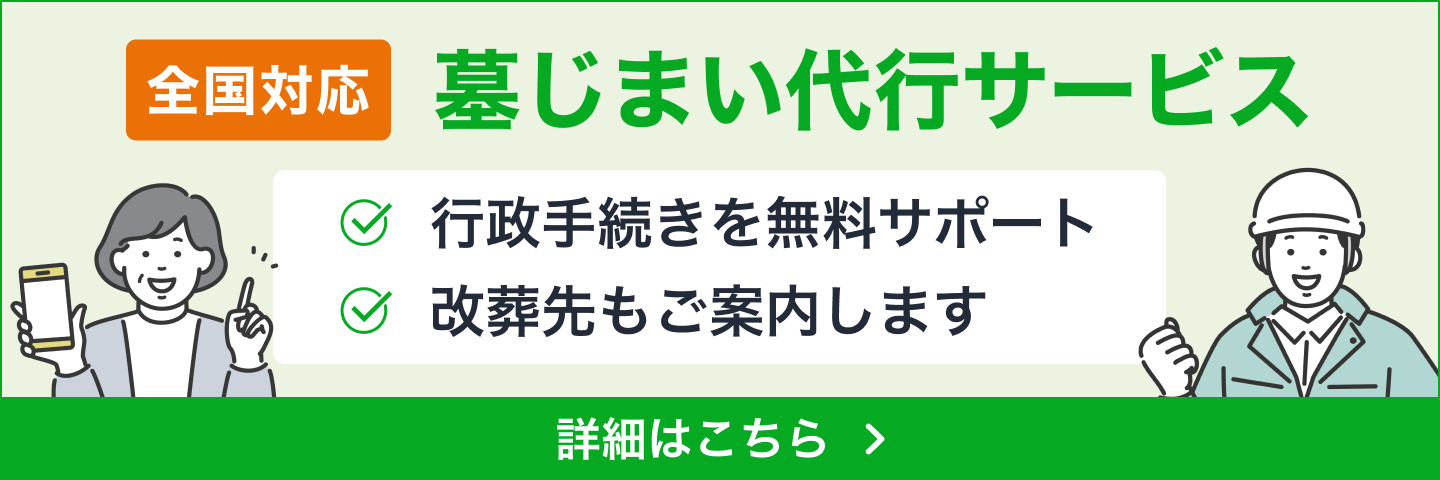墓じまいの費用相場は総額35万円〜150万円。内訳は、お墓の撤去・行政手続き・新しい納骨先にかかる費用の3つに分けられます。
この記事では、墓じまいにかかる費用の相場や内訳を紹介。あわせて、墓じまい費用の抑え方や払えない場合の対処法も解説します。
墓じまい費用の総額と内訳

| 墓じまいにかかる費用 | |
|---|---|
| 墓じまい費用の総額 | 35万円~150万円 |
| お墓の撤去に関する費用 | 30万円~50万円 |
| 行政手続きに関する費用 | 数百円~1,000円 |
| 新しい納骨先に関する費用 | 30万円~100万円 |
墓じまいにかかる費用の総額は、35万円〜150万円です。内訳は、「お墓の撤去に関する費用」「行政手続きに関する費用」「新しい納骨先に関する費用」の3つに分けられます。
墓じまいの費用相場の幅が広いのは、「お墓の撤去に関する費用」と「新しい納骨先に関する費用」によって金額が変動するから。
たとえば、「お墓の撤去に関する費用」では、区画の大きさや道幅の広さなどの環境条件によって費用が異なります。区画が広くて作業人数が増えたり、道幅が狭くてクレーン車が入れなかったりすると、かかる金額が上がります。
また、墓じまいは墓石を撤去して、区画を更地にすれば終わりではありません。取り出したご遺骨を新しい納骨先(=お墓)に納める必要があるため、墓石の撤去・原状回復の費用だけでなく、新しい納骨先を用意する費用もかかります。
墓じまいの費用は、現在建てられているお墓の状況や、選択した納骨先によって必要な費用が変わってきます。そのため、今あるお墓をこれからどうしたいのか、ご自身で整理しておくのが大切です。
お墓の撤去にかかる墓じまい費用

| 支払い先 | 費用の内訳 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 石材店・業者 | 墓石の撤去費用 | 10万円〜30万円 |
| ご遺骨の取り出し費用 | 1万円〜3万円 | |
| ご遺骨の運送費用 | ※距離・方法で異なる | |
| お寺・僧侶 | 閉眼供養のお布施 | 3万円〜10万円 |
| 離檀料 | 3万円〜20万円 |
墓じまいのお墓の撤去にかかる費用は、約30万円〜50万円が相場です。「石材店・業者に支払う費用」と、「寺院・僧侶に支払う費用」があります。
石材店・業者に支払う費用
墓石の撤去費用
お墓を撤去して、区画を更地に戻すための費用です。1㎡あたり10万円程度が相場で、10万円〜30万円が費用の目安です。
- お墓が急斜面に立っている
- お墓の参道や区画が狭い
- 複数の石碑が建立されている
など、お墓の立地や周辺状況によっては、重機が入れなかったり人手が必要だったりして、追加費用が発生するかもしれません。また、お墓の撤去費用に差がある地域もあります。
石材店・業者によって価格の設定が異なるため、複数の石材店・業者から見積もりを取って比較検討するのがおすすめです。
ご遺骨の取り出し費用
ご遺骨の取り出しは、墓石の解体工事とあわせて、石材店に依頼するのが一般的。遺骨の取り出しにかかる費用は、1柱あたり3万円〜5万円が相場です。
また、長い間お墓に納められていたご遺骨にカビが生えていたり、溶解していたりしたら、メンテナンスが必要です。ご遺骨を洗ったり骨壺内の水抜きをしたりすると、メンテナンス費用として追加で数万円かかる石材店もあるので、確認しておきましょう。
ご遺骨の運送費用
ご自身でご遺骨を移動するのが難しい場合、ご遺骨の運送費用が必要です。ご遺骨の運送費用は、方法や距離によって異なります。
たとえば送骨サービス業者は、サービス内容によって金額が変わりますが、数万円程度が相場です。また、日本郵便の「ゆうパック」では、遺骨の郵送が認められています。ゆうパックなら数千円程度で遺骨の移動が可能です。ただし、ヤマト運輸や佐川急便など、ゆうパック以外の方法では遺骨は郵送できないので注意してください。
お寺・僧侶に支払う費用
閉眼供養のお布施
お墓を撤去したあと、ご遺骨を取り出す前に「閉眼供養」を行います。閉眼供養とは、僧侶に読経していただき、お墓に宿る魂を抜く儀式です。
閉眼供養では、僧侶にお礼として「お布施」をお渡しします。閉眼供養のお布施の相場は、3万円〜10万円です。ただし、僧侶との関係性や寺院の方針、地域などによってお布施の金額は変わるため、事前に確認しておくと安心でしょう。
離檀料
檀家として寺院にお墓を管理してもらっていた場合、墓じまいと合わせて離檀(檀家を離れる)します。離檀するときは、今までお世話になった寺院に感謝を込めて「離檀料」を支払うのが一般的です。
離檀料は、寺院の方針や関係性、格式などによって変わりますが、通常の法要で包む金額の2〜3倍が目安。具体的には、離檀料の相場は3万円〜20万円といわれています。撤去するお墓が民営霊園にあったり、檀家に入っていなかったりするなら、離檀料は必要ありません。
行政手続きにかかる墓じまい費用

| 入手先 | 書類 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 既存のお墓の管理者 | 埋蔵証明書 | 300円~1,500円 |
| 新しい納骨先の管理者 | 受入証明書 | 無料 |
| 自治体の窓口 | 改葬許可申請書(改葬許可証) | 無料~1,000円 |
墓じまいの行政手続きにかかる費用は、数百円〜1,000円が相場です。
墓じまいをするときは、墓地の管理者や役所から書類を交付してもらう必要があります。自治体や管理者によって金額は異なりますが、発行時に数百円〜1,000円ほど手数料が発生するので、あらかじめ問い合わせて確認しておきましょう。
なお、埋蔵証明書は「お墓に埋葬されている人数分」の枚数が必要になる場合があります。先祖代々のご遺骨が納められているお墓だと、費用がそのぶん上乗せされるので注意が必要。また昔からあるお墓は、ご遺骨数を確認する作業の進捗によって、埋蔵証明書の取得に時間がかかるかもしれません。ご自身で手続きできないときは、行政書士などに代行を依頼できますが、追加で行政書士へ報酬を支払う必要があります。
新しい納骨先にかかる墓じまい費用

| 支払い先 | 納骨先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 新しい納骨先 | 永代供養墓 | 5万円~150万円 |
| 納骨堂 | 10万円~150万円 | |
| 樹木葬 | 5万円~150万円 | |
| 散骨 | 5万円~30万円 | |
| 手元供養 | 3万円~10万円 | |
| 一般墓 | 100万円~200万円 | |
| お寺・僧侶 | 開眼供養のお布施 | 3万円~5万円 |
墓じまいの新しい納骨先にかかる費用の相場は、30万円〜100万円です。「新しい納骨先に支払う費用」と、「寺院・僧侶に支払う費用」があります。
墓じまいでは、既存のお墓から取り出したご遺骨を納めるため、新しい納骨先(=お墓)を用意します。どのようなお墓を納骨先にするかによって費用が大きく異なるため、それぞれの特徴や違いを把握しておきましょう。
新しい納骨先に支払う費用
永代供養墓の費用

- 合祀型(合祀墓):5万円~30万円
- 集合型(集合墓):20万円~60万円
- 個別型(個人墓):50万円〜150万円
- 樹木葬型:5万円~150万円
- 納骨堂型:10万円~150万円
永代供養墓とは、霊園・寺院が永代にわたって管理・供養してくれるお墓。お墓の継承者が途絶えたとしても、霊園・寺院が管理・供養してくれるので無縁仏になる心配がありません。お墓の継承者がいなくなったり、管理が難しくなったりするのをきっかけに墓じまいをする場合、永代供養墓を選択するご家庭が多いです。
永代供養墓にかかる費用の相場は5万円〜150万円ですが、お墓の埋葬方法や種類によって金額が変わります。
永代供養墓の主な埋葬方法は、「合祀型」「集合型」「個別型」の3つです。他人と共通のお墓に遺骨をまとめて埋葬する「合祀型」は、もっとも費用が安く、5万円〜30万円が相場。一度合祀されるとご遺骨を取り出せませんが、ほかの永代供養墓と比べて格段に費用を抑えられます。
「個別埋葬型」は、専用のお墓に個人単位で遺骨を埋葬するお墓です。一定期間ないしは永代にわたって個別供養されるため、合祀墓より価格が上がり、50万円〜150万円が相場とされています。共通のお墓に個別で遺骨を埋葬する「集合型」は、20万円〜60万円と、合祀型と個別型の中間の価格帯です。
また、永代供養墓は「永代供養(=霊園・寺院が永代にわたって管理するサービス)」の付いたお墓全般を指すため、永代供養付きの樹木葬や納骨堂も永代供養墓に含まれます。樹木葬型は5万円〜150万円、納骨堂型は10万円〜150万円が相場です。
納骨堂の費用

- ロッカー式:約20万円~80万円
- 仏壇式:約50万円~150万円
- 位牌式:約10万円~30万円
- 墓石式:約50万円~150万円
- 自動搬送式:約70万円~150万円
納骨堂とは、ご遺骨を納めた骨壺を安置する建物のこと。屋内施設が主で首都圏に多く、立地の良さや管理のしやすさから、近年選ぶ人が増えています。納骨堂は永代供養がほとんどなので、お墓の管理・継承が必要ありません。また、永代供養付きの納骨堂でも、「最初から合祀にする」「一定年数が経過したら合祀する」「継承者がいる限り合祀しない」などの選択が可能です。
納骨堂の費用相場は10万円〜150万円で、墓標の有無や納骨スペース、機能などによって金額が変わります。
扉付きの小さな納骨スペースが並んだ「ロッカー式」の相場は、約20万円〜80万円。位牌を墓標として並べる「位牌式」は約10万円〜30万円と、納骨堂の中では安価です。一方、個々の仏壇に遺骨を納める「仏壇式」は約50万円〜150万円、個々の墓石を墓標とする「墓石式」は約50万円〜150万円と費用が上がります。その他、「自動搬送式」は参拝スペースまで遺骨が自動で運ばれてくる納骨堂で、最新技術・設備が必要なため約70万円〜150万円ともっとも高額です。
樹木葬の費用

- 合祀型:5万円~30万円
- 集合型:10万円~60万円
- 個別型:20万円~150万円
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とするお墓。墓石がないぶん費用をおさえやすく、安価な葬儀を上げたい方や、「死後は自然の中で眠りたい」という自然回帰志向をもつ方を中心に人気です。
樹木葬の費用相場は5万円〜150万円ですが、埋葬方法や種類によって金額が異なります。
1本の樹木に複数の遺骨をまとめて埋葬する「合祀型」は、5万円〜150万円。個々の墓標やスペースが不要なため、もっとも費用をおさえられます。1本の樹木に遺骨を個別に埋葬する「集合型」は10万円〜60万円、遺骨ごとに樹木と区画が設けられる「個別型」は20万円〜150万円です。
また樹木葬は、立地や環境によって「里山型」「公園型」「庭園型」の3つに分かれます。郊外に多い「里山型」は比較的低価格、都心に多い「庭園型」は比較的高価格、中間地に多い「公園型」は中間の価格帯です。
散骨の費用
散骨とは、故人のご遺骨を粉末にして山や海などに撒く供養方法。墓標や参拝場所を用意せず、永久にご遺骨を手放すため維持費がかかりません。最近は、一部のご遺骨を散骨し、残りのご遺骨をお墓に埋葬する「分骨」を選ぶ方もいらっしゃいます。
散骨の費用相場は5万円〜30万円です。散骨する場所や遺骨の処理方法などは、法律で定められています。何も知らずに勝手に散骨すると法に触れる可能性あがるため、散骨する場合は専門業者に相談しましょう。
手元供養の費用
手元供養とは、ご遺骨の全部または一部を自宅で安置する供養方法。小型の骨壺やミニ仏壇、飾り台などにご遺骨を安置します。また、ペンダントやブレスレット、ブローチなど、専用のアクセサリーに遺骨を納めて、身に着ける方法もあります。
手元供養は維持費がかからず、他の供養方法より費用も安価です。ただし、供養する人がいなくなったときの対応や、盗難・紛失の対策が必要なので注意してください。手元供養の費用相場は3万円〜10万円で、手元供養品によって金額が変わります。
一般墓の費用
一般墓とは、家族や一族など家単位で代々継承していく伝統的なお墓です。一般墓は、納骨室(カロート)に納めるご遺骨の数に上限がなく、管理費を支払うことで永続的に使用できます。
一般墓の費用相場は100万円〜200万円ですが、墓石がセットになっていたり、省スペースだったりする一般墓だと費用を抑えられます。
お墓の継承問題で墓じまいをするご家庭は、新しい納骨先に一般墓を選ぶのは難しいかもしれません。ですが、合祀されず、お墓を引き継いでいく一般墓は、先祖代々の供養を自分たちで手厚く行えます。お墓参りや法事で親族が集まりやすく、ご家族のより所にもなるでしょう。
お寺・僧侶に支払う費用
開眼供養・納骨式のお布施
納骨先の新しいお墓にご遺骨を納めるときは、「開眼供養」「納骨式」を行います。開眼供養とは新しいお墓に故人の魂を込める儀式、納骨式は故人の遺骨をお墓に納める儀式です。
開眼供養・納骨式をする場合、お礼として僧侶にお布施を支払います。開眼供養・納骨式のお布施の費用相場は3万円〜5万円です。お墓から魂を抜く閉眼供養とお墓に魂を入れる開眼供養(納骨式)を1日で行うときは、お布施を別々に包んでも、まとめて包んでも、どちらでも問題ありません。
墓じまいの費用は誰が支払う?
- お墓の継承者
- 継承者以外の血縁者
- 親(故人)
墓じまいの費用を誰が支払うか、明確な決まりはありません。
一般的にはお墓の継承者が支払いますが、墓じまいの費用は高額になりやすいため、ご家族や親族で協力して支払うご家庭も多いようです。また、親御さんが生前に墓じまいの費用を残しているご家庭もあります。
お墓の継承者
墓じまいの費用を支払うのは、一般的にお墓の継承者です。民法第897条で「お墓の所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定められているため、お墓を管理する継承者が墓じまいの費用を負担します。
お墓の継承者は、被相続人の指定がなければ慣習に従うのが通例で、長男・長女が多いです。
継承者以外の血縁者
墓じまいの費用は高額なため、お墓の継承者単独で支払うのは負担が大きいかもしれません。そのため、家族や親族など血縁者が協力して、墓じまい費用を支払うご家庭もあります。
費用の分担や割合に決まりはないですが、トラブルになりやすいので家族・親族同志でしっかり話し合いをするのが大切です。
親(故人)
終活の一環として、生前に墓じまいの費用を残している親御さんもいらっしゃいます。
お墓に入る本人が生前に費用を残していると、残された家族・親族間でトラブルになりにくいです。親御さんが亡くなったときは、念のため遺言や預貯金を確認しておきましょう。
墓じまいの費用を安く抑える方法は?
墓じまいにかかる費用の総額は35万円〜150万円と、決して安い金額ではありません。中には墓じまい費用の負担が大きく、支払えない方もいらっしゃるでしょう。
墓じまいの費用を安く抑えるには、「お墓の撤去に関する費用」と「新しい納骨先に関する費用」を見直すのが一番。とくに、「石材店・業者」または「改葬先のお墓」の選び方次第で、墓じまいの費用を安く抑えられます。
石材店・業者の選定
墓じまいの費用を抑えたいなら、墓石工事を依頼する石材店・業者を見直しましょう。墓石の撤去や区画の整地にかかる費用は、石材店・業者によって異なります。複数の石材店から見積もりを取ることで、費用感を把握しやすく、より適した石材店・業者を選択できます。ただし石材店を選ぶときは、相見積もりだけでなく、口コミや評判もあわせて調べ、総合的に判断するのが安心です。
また霊園・お寺によっては、墓石工事をする石材店の指定を受けるかもしれません。指定石材店がある霊園・お寺だと、自分で自由に業者を選べないので事前に確認してください。
いいお墓では墓石の撤去から各種手続き、改葬先のご案内まで墓じまいの全工程をサポートし、明朗な見積もりを提示しております
改葬先のお墓の選定
墓じまいで費用がかかるのは、お墓を撤去して墓所を更地にする費用より、新しく購入する改葬先のお墓のようです。お墓にはさまざまな種類があり、それぞれ費用が違います。
墓じまいの費用を抑えたいなら、伝統的な一般墓ではなく、新しいタイプのお墓を選びましょう。墓石が不要な永代供養墓や納骨堂、樹木葬などを選ぶと、石材費がかからないぶん費用を抑えやすいです。また、遺骨の個別安置期間があるお墓が多いため、合祀後は管理費を支払う必要もありません。また、お墓を用意しない散骨や手元供養も費用を抑えられます。
ただし、新しいタイプのお墓を選ぶときは、家族・親族の同意が不可欠です。墓標がなく、従来のお墓参りができないお墓が多いため、反対する家族・親族がいらっしゃるかもしれません。改葬先のお墓を選ぶ理由を丁寧に説明して、全員納得したうえで改葬先を決定することで、無用なトラブルを避けられます。
墓じまいの費用を払えない場合の対処法は?
- 家族・親族に協力してもらう
- 自治体の補助金制度を利用する
- メモリアルローンを利用する
- 寺院の住職に相談する
墓じまいの費用を払えない場合の主な対処法は、こちらの4つです。
家族・親族に協力してもらったり、自治体の補助金制度・メモリアルローンを利用したりすれば、墓じまい費用を補填できるでしょう。また、寺院の住職に相談することで、お布施や離檀料にかかる費用を考慮していただけるかもしれません。
家族・親族に協力してもらう
墓じまいの費用を、お墓の継承者一人で全額支払う必要はありません。全額支払えないなら、家族・親族に協力してもらって、墓じまいの費用を分担するのもひとつの方法です。
まずは家族・親族に相談して、墓じまい費用を分担できないか話し合ってみてください。
自治体の補助金制度を利用する
お住まいの地域によりますが、近年増加している無縁仏を避けるため、墓じまいの補助金を出してくれる自治体があります。墓じまいの補助金の主な対象は墓石の撤去費用で、工事費用の全額または一部を負担してくれます。
また、墓じまいのサポートをしてくれる自治体もあるので、一度役所に相談してみるのがおすすめです。
メモリアルローンを利用する
メモリアルローンとは、故人・家族の祭祀費用を賄うためのローンです。お葬式の施行費やお墓の購入費として利用されることが多く、審査に通れば墓じまいでも利用できます。
メモリアルローンは、霊園・寺院や石材店などを通して契約するのが一般的なので、墓じまい費用が足りない方は相談してみましょう。
寺院の住職に相談する
墓じまいするお墓が寺院にある場合は、お寺の住職に費用について相談してみるのもひとつの方法。住職に相談することで、閉眼供養のお布施や離檀料の費用を考慮してくださるかもしれません。
住職にこれまでの感謝を伝えたうえで、ご家庭の事情を素直にお話するのが大切です。
墓じまいせず放置するとどうなる?
墓じまいせず、放置されたお墓は、「無縁仏」として強制的に撤去されるのが一般的です。
そもそも墓石を建立している土地は、霊園・寺院から借りている状態。お墓を利用している間は、霊園・寺院に「管理料」を支払うのがルールです。お墓を放置して一定期間管理料が未払いになると、「無縁仏」として扱われて墓石が撤去されます。
墓石を撤去したあとのご遺骨は、不特定多数の遺骨をまとめて埋葬する合祀墓に移されます。一度合祀墓に移されると、個々の遺骨を取り出せなくなるので注意してください。また、放置された墓石の撤去費用は行政が負担します。
霊園・寺院や行政に迷惑をかけないためにも、お墓は放置せず、早めに墓じまいを検討しましょう。
墓じまいの費用をめぐるトラブル・注意点は?
墓じまいの費用は高額になることが多く、寺院や石材店とトラブルが起こる可能性があります。具体的な事例や注意点を知っておくことで、未然にトラブルを防ぎましょう。
寺院とのトラブル:離檀料
既存のお墓が寺院墓地の場合、墓じまいをすると離檀する(檀家を抜ける)ことになります。お寺は、檀家からのお布施を資金に運営しているため、檀家が減ると運営が厳しくなってしまいます。そのため、檀家を抜けるのを拒否されたり、高額な離檀料を請求されたりする寺院もあるようです。
寺院との費用トラブルを防ぐためには、まず住職をはじめ、お世話になった方々へ感謝を伝えるのが大切。そのうえで墓じまいをする理由を正しく伝え、理解してもらいます。
石材店とのトラブル:墓石撤去・工事費用
墓石の撤去を依頼した石材店から、高額な費用を請求されてトラブルになるケースがあります。また、お墓の区画が狭かったり山奥にあったりして作業車・クレーン車の使用が難しい場合は、相場より高い工事費を請求されるかもしれません。
石材店・業者によって費用やサービス内容は異なるので、できるだけ複数の業者から相見積りをとり、比較検討するのが大切です。
事前準備を徹底して後悔のない墓じまいを
墓じまいをすることで、残された子どもがお墓を管理する負担を軽減でき、無縁仏になる心配もなくなります。ただし、墓じまいにかかる費用は総額35万円〜150万円と、決して安い金額ではありません。
支払い方法や新しい納骨先について、家族・親族できちんと話し合って準備を進めるのが大切です。家族・親族や霊園・寺院の管理者の理解を得ることで、スムーズに墓じまいを進められます。
いいお墓の墓じまい
墓じまい(改葬)は完了するまでの手続きも多く、必要な費用も不透明なところが多いのが実態です。