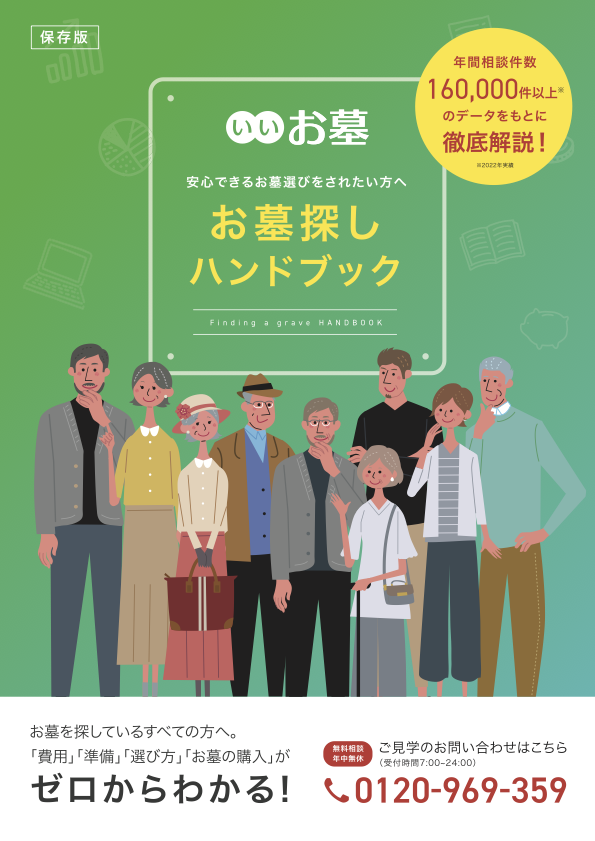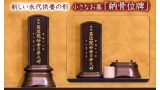納骨堂は、遺骨を収蔵するための屋内施設。建物内に収骨スペースがあるため、天候に左右されずお墓参りできます。また、墓石がないので掃除が不要で、費用も比較的安価なのが魅力です。
この記事では、納骨堂とはどんなお墓なのか、種類や費用相場、メリット・デメリットなどを紹介します。
納骨堂とは?特徴と一般墓との違い

納骨堂とは、遺骨を保管・管理するための屋内施設。建物の中に、個人や夫婦、家族などの単位で遺骨を納める収骨スペースが設けられています。
納める遺骨の数によって金額が変わりますが、墓石がないぶん従来のお墓より安価。また「屋内にお墓がある」「ひとつの建物に多数の収骨スペースがある」「遺骨を骨壺に納めて収蔵する」などが、従来のお墓との違いです。
納骨堂の定義
納骨堂は、厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律」第2条6項において定義されています。具体的にいうと、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」を納骨堂だと通達。つまり納骨堂とは、「遺骨を安置できる施設」だと言えます。
遺骨の保管を継続的・反復的に実施する納骨堂を経営するためには、法律に基づく許可が必要です。しかし、お墓に埋蔵する前に、故人の焼骨を一時的に預かる場合は、お寺が納骨堂としての許可を得ていなくても問題ありません。
納骨堂の費用相場と価格の目安

2024年にいいお墓が実施した「第15回お墓の消費者全国実態調査」によると、納骨堂の平均購入価格は80.3万円。149.5万円の一般墓と比べると、約70万円も費用をおさえられています。
一般的な納骨堂の費用相場は、個人用が50万円、家族用が100万円程度と考えればよいでしょう。費用の内訳は、永代供養料・使用料、納骨費用、開眼法要料が主で、施設によって戒名や位牌にかかる料金を含みます。また、管理費として別途年間1万円程度を求められる納骨堂もあります。
最新式の機械を使った自動搬送式の施設だと、個人用で80万円前後が相場。さらに有名な寺院などでは200〜300万円する納骨堂もあります。
納骨堂は通常のお墓に比べると安価ですが、種類や供養方法、規模などによって費用が異なるため、注意が必要です。収蔵可能な遺骨の数、個人用・夫婦用・家族用、施設の管理体制、設備の充実度、納骨時の戒名、法要の有無、立地などによって料金が変わってきます。
納骨堂のメリット・デメリット
納骨堂のメリット
- 一般的なお墓より費用・料金が安い
- 比較的アクセスの良好な立地が多い
- 天気や気温の影響がなくお墓参りが快適
- 墓石の掃除や草抜きなどの作業が不要
- 遺骨を移動しやすい
- 宗教・宗派不問で対応が柔軟
納骨堂のメリットは、何といっても従来のお墓と比べて費用が安いこと。墓石代と墓地の永代使用料を含めて100〜200万円かかる一般墓に対して、納骨堂は100万円以下におさえやすいです。
また、納骨堂は比較的アクセスのよい立地にある施設がほとんど。基本的に屋内施設なので、雨や風といった天気の影響を受けず、冷暖房完備で快適にお墓参りできます。もちろん、墓石の掃除や草抜きといった作業も必要ありません。
さらに納骨堂は遺骨の移動が簡単。お墓の引越し(改葬)手続きは必要ですが、遺骨を他の施設に移す負担が少ないです。その他、宗教・宗派不問で、顧客のニーズに柔軟に対応できる点も魅力です。
納骨堂のデメリット
- 最終的には他人の遺骨と一緒に埋葬される
- 従来のお墓参りやお供えができない
- 収骨スペースに限りがある
- 災害や老朽化で建物が使えなくなる
納骨堂は、遺骨の収蔵期間が決められています。そのため、最終的には他人の遺骨と一緒に埋葬(=合祀)される納骨堂が多いです。一度合祀されると、個別で遺骨を取り出せないので注意が必要。
また納骨堂によっては、お墓参りの方法やお供えする品物に制限があったり、収骨スペースが限られていたりします。その他、災害や老朽化で建物が使えなくなる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
納骨堂と永代供養の違い

- 納骨堂:遺骨を保管・管理するための屋内施設(お墓の一種)
- 永代供養:遺族の代わりに霊園・寺院がお墓を管理すること(供養方法の一種)
永代供養(えいたいくよう)とは、遺族の代わりに霊園・寺院がお墓の管理・供養をすること。供養方法の一種で、永代供養のついたお墓を「永代供養墓(えいたいくようぼ)」と呼びます。
対して納骨堂は、遺骨を保管・管理するための屋内施設を指し、お墓の一種です。永代供養のついた納骨堂も多くあり、永代供養墓の種類のひとつに納骨堂が含まれています。
ただし、実際は用語の統一が取れているとは言えず、定義が異なる霊園・寺院は珍しくありません。納骨堂や永代供養墓の購入を検討するときは、どのような施設なのかをよく確認しましょう。
納骨堂の種類と代表例

- ロッカー式
- 仏壇式
- 位牌式
- 墓石式
- 合祀式
- 自動搬送式
納骨堂の代表的な種類は、ロッカー式、仏壇式、位牌式、墓石式、合祀式、自動搬送式の6つ。それぞれの特徴を紹介します。
ロッカー式の納骨堂
ロッカー式は、コインロッカーのような扉付きの収骨スペースに骨壺を納める納骨堂。古くからある種類で、遺骨を一時保管するためにロッカー式納骨堂を利用する方もいます。
ロッカー式納骨堂は、個別のスペースを確保できて、費用が安価なので人気です。施設によっては思い出の写真や品物を一緒に納められます。納骨堂によりますが、見た目が簡素だと本物のコインロッカーのようだと敬遠する方もいるかもしれません。
ロッカー式納骨堂の代表例:伝燈院 麻布浄苑(東京都港区)
伝燈院 麻布浄苑(東京都港区)

伝燈院 麻布浄苑は、六本木ヒルズに近い元麻布にある納骨堂です。使用期間は50年間で、以降は合祀供養塔に合葬し永代供養されます。ロッカー式の納骨堂で、室内納骨堂と屋外納骨堂があります。花瓶やお線香も常備してあるため手ぶらで参拝でき、法要施設や、会食などで利用できる施設もあります。また、宗教に縛りはなく、どなたでも利用できます。遺骨を地上の礼拝堂に安置するため、地下の納骨堂に降りなくても参拝できます。
仏壇式の納骨堂
仏壇式は、仏壇が横並びになっている納骨堂で、「霊廟(れいびょう)型」とも呼ばれます。上段に仏壇、下部に骨壺を納めるスペースがあり、仏壇には位牌や遺影、お花などを飾れます。装飾が華美なため、ロッカー式と比べると比較的割高です。
仏壇式納骨堂の代表例:東福院 四谷納骨堂(東京都新宿区)

東福院 四谷納骨堂は、交通至便な四ツ谷にある仏壇式の納骨堂。5線利用できるアクセス抜群の立地に加え、歴史ある寺院が管理・運営する安心感が魅力です。
東福院 四谷納骨堂は、位牌の後ろに骨壺を納骨する場所を設置した直接参拝式の納骨堂で、永代供養もついています。納骨壇のプランには戒名料が含まれていて、粉骨や骨壺のサイズに応じて最大4霊まで納骨が可能です。いずれも生前契約でき、ご予算・ご希望にあわせて選びやすいです。
位牌式の納骨堂
位牌式は、参拝スペースに位牌を並べる納骨堂。位牌をメインにしていて、遺骨は別の場所に保管する施設が多いです。位牌と遺骨を別々に置く納骨堂は、個別にお墓参りするスペースがないぶん、費用をおさえられます。
位牌式納骨堂の代表例:小さなお墓 納骨位牌墓 妙経寺(東京都八王子市)

小さなお墓 納骨位牌墓 妙経寺は、少量の遺骨を位牌に格納し、本堂のご宝前横に安置する位牌式の納骨堂です。残りのご遺骨は永代供養塔に合祀されますが、要望に応じて個別で預かってもらうことも可能。また小さなお墓 納骨位牌墓 妙経寺は、JR八王子駅から徒歩8分の好アクセス。納骨位牌は本堂に安置されるため、季節や天候に関わらず快適にお墓参りできます。位牌の供養や掃除は寺院にまかせられますが、管理費が不要なのもポイントです。
墓石式の納骨堂
墓石式は、建物内に個々の墓石を並べる納骨堂。屋内にあるため、天候や気温、風化などの影響を受けにくいです。また、花や線香をお供えできる施設もあり、従来に近いお墓参りができます。ただし、墓石代が必要なぶん、納骨堂のなかで最も高額です。
墓石式納骨堂の代表例:屋内墓苑 松栄山 仙行寺 沙羅浄苑(東京都豊島区)

屋内墓苑 松栄山 仙行寺 沙羅浄苑は、池袋駅から徒歩5分圏内にある隠れ家的な屋内墓苑です。苑内には合計16の参拝ブースがあり、特別参拝室は国内の銘石「庵治石」を、一般参拝室には「黒御影石」の墓石が用意されています。遺骨の数に制限がないため、骨壺の大きさや骨袋の利用、永代供養墓への移動など、随時相談が可能です。また、沙羅浄苑内のご本堂、法要室さらに併設する「沙羅ホール」で葬儀・法要・会食などを行えます。
合祀式の納骨堂
合祀(ごうし)式は、永代供養塔の中に遺骨を収蔵する納骨堂です。そもそも合祀とは、不特定多数の遺骨をまとめて埋葬すること。遺骨をまとめて埋葬する合祀式の納骨堂なら、個々の区画や遺骨の管理が不要なため、費用を最もおさえやすいです。一方で、遺骨が混ざらないよう骨壺のまま納める納骨堂も存在します。
合祀式納骨堂の代表例:天妙国寺 永代供養納骨堂 鳳凰堂(東京都品川区)

天妙国寺 永代供養納骨堂 鳳凰堂は、青物横丁駅から徒歩4分、品川商店街沿いの好立地にある納骨堂です。永代供養納骨堂「鳳凰堂」は、継承者はもちろん、檀家になる必要もありません。お墓の後継者がいない、または維持管理が難しい方でも安心して利用できます。また、永代供養合祀墓「法界萬霊供養塔」を選べば、費用を大幅におさえられます。
自動搬送式の納骨堂
自動搬送式は、納骨箱が参拝スペースに自動で搬送される納骨堂。参拝者がICカードをかざしたりタッチパネルを操作したりすると、収蔵庫に収められている位牌や骨壺が参拝スペースに運ばれてきます。
他にも、スクリーンに遺影が投影されたり、故人が好きだった音楽が流れたりする自動搬送式の納骨堂も。最新テクノロジーを投入しているぶん、相場は少し高めに設定されています。
自動搬送式納骨堂の代表例:吾妻橋天空陵苑(東京都墨田区)
 吾妻橋天空陵苑は、浅草やスカイツリーに近い本所吾妻橋駅から徒歩2分の好立地にある民営の納骨堂です。建物内は完全バリアフリーで、1基48万円からの、リーズナブルな価格設定が特徴です。宗旨宗派を問わず申し込みでき、永代供養で後継者のいない人でも安心です。ICカード式の室内墓地で、お花やお香の用意もありますので、手ぶらでの参拝が可能です。
吾妻橋天空陵苑は、浅草やスカイツリーに近い本所吾妻橋駅から徒歩2分の好立地にある民営の納骨堂です。建物内は完全バリアフリーで、1基48万円からの、リーズナブルな価格設定が特徴です。宗旨宗派を問わず申し込みでき、永代供養で後継者のいない人でも安心です。ICカード式の室内墓地で、お花やお香の用意もありますので、手ぶらでの参拝が可能です。
納骨堂の運営主体
- 寺院
- 民間企業(民営)
- 自治体(公営)
納骨堂の運営主体は、大きく3つにわけられます。具体的には、お寺が運営する納骨堂、企業・社団法人が運営する民営の納骨堂、自治体・公的期間が運営する公営の納骨堂の3つです。
寺院が運営する納骨堂
一般的には、お寺が管理するお墓に入れるのは檀家になっている人だけ。ですが納骨堂では、宗旨宗派不問で、檀家になる必要のない寺院が多数あります。入檀しないためお布施や寄付金は不要ですし、誰でも納骨堂を利用できます。供養の方法は、運営しているお寺の作法に即すことが多いです。
民間企業が運営する納骨堂
運営を委託されて、企業や社団法人などの民間企業が運営している納骨堂もあります。民営の納骨堂は宗旨宗派不問なので、故人の信仰していた宗教・宗派にあわせて供養してもらうことも可能。ただし、施設によって条件やサービスが異なるため、契約前にしっかり確認しておきましょう。
自治体や公的機関が運営する納骨堂
都道府県や市区町村などの自治体が運営している、公営の納骨堂も存在します。公営の納骨堂は、公的機関が運営しているため倒産や解散のリスクがなく、リーズナブルなのが魅力です。ただし、居住年数や遺骨の有無など、自治体によって応募条件が違います。また、設備的には民間の納骨堂より劣っている納骨堂もあるため、注意してください。
納骨堂の注意点と選び方のポイント
- アクセス
- 納骨数
- 埋葬方法
- 宗教・宗派・檀家条件
- 施設・設備の充実度
納骨堂を選ぶときは、こちらの5つのポイントに注意してください。
まず大切なのは、お墓参りしやすい立地・アクセスかどうか。高齢になったり怪我をしたりしても足を運びやすいよう、交通手段や道のりも確認しておくと安心です。また、納骨数や埋葬方法、宗旨宗派は納骨堂によって違うため、ご自身の希望に合っているか必ず確かめておきましょう。
さらに施設・設備の充実度とあわせて、建物の状態もチェックしておくこと。災害や老朽化で建て替えになると、遺骨の一時引き取りが発生するかもしれません。
納骨堂の購入に向いている人
- お墓の管理者がいない人
- 既存のお墓が遠方にある人
- 子孫の負担を減らしたい人
- 個人または夫婦で眠りたい人
納骨堂を検討する際の判断材料の一つとして、納骨堂の購入に向いている人を紹介します。
お墓の管理者がいない人
お墓の跡継ぎがいないと、将来的に無縁墓・無縁仏になってしまいます。永代供養の納骨堂を選べば、後継者がいなくても永続的に供養してもらえるので安心。最初に費用を支払うため維持費は不要ですし、お墓参りする家族がいなくても、お墓をキレイに整備してもらえるので寂しくありません。
既存のお墓が遠方にある人
お墓と住まいの距離が離れていてお墓参りが難しいことから、納骨堂を選ぶ方も。元々あるお墓を墓じまいし、居住地に近い納骨堂に遺骨を改葬することで、お墓参りしやすくなります。
子孫の負担を減らしたい人
お墓を継いでくれる子孫がいるものの、お墓を管理する面倒をかけさせたくないと納骨堂を選ぶ方も多いです。納骨堂は、墓石の掃除や草むしりなどの管理が不要なので、家族の負担を減らせます。
個人または夫婦で眠りたい人
従来のお墓はご先祖様と一緒に埋葬されますが、納骨堂は個人や夫婦といった単位で契約可能です。自分一人でお墓に入りたい人や、夫婦だけで眠りにつきたい人が納骨堂を選ぶこともあります。
納骨堂が増えている理由
建物内に多数の遺骨を収蔵できる納骨堂は、墓地用地が不足している都心部を中心に広がっています。
また、核家族化や未婚率の上昇などによって、お墓を管理する人のいない家庭が増加。納骨堂は、お墓の維持・管理が不要で、後継者がいなくても無縁墓にならないと人気を集めています。さらに、価値観の多様化や生活スタイルの変化により、従来のお墓や宗旨宗派にこだわらない人が増えたのも、納骨堂が注目されている理由です。
納骨堂の歴史
納骨堂は「霊廟(れいびょう)」と呼ばれており、奈良時代前後の文献に記載がありました。また始まりは、天皇家や豪族などの上流階級の人々が、栄華存続のために建物内に遺体を安置する「納骨壇」だったそうです。
現在に近い納骨堂が現れたのは、昭和初期といわれています。もともと納骨堂は、お墓を建てるまでの間、利用料を支払って一時的に遺骨を預ける場所でした。しかし、次第に遺骨の預かり期間の延長や永代供養ができるお寺が増え、安価で場所も取らないことから全国的に普及。一般的な墓地と違い、跡継ぎがいなくても購入できると人気を集め、お墓の代用施設として拡大していきました。
納骨堂を探すなら「いいお墓」へ
新しいお墓の形として注目を集めている納骨堂。さまざまな種類がありますが、中身は千差万別なので、ご自分の思想やライフスタイル、予算などに応じてじっくり検討してください。
納骨堂を探すときは、交通アクセスや雰囲気、お墓参りの方法などを確認すること。資料やホームページだけでなく、現地見学をして実際に確かめてみるのが大切です。さらに複数の納骨堂や霊園を見学して比較検討すると、より後悔のない選択につながります。
日本最大級のお墓ポータルサイト「いいお墓」では、全国各地の納骨堂を多数掲載中。エリアや条件にあわせて検索できるのはもちろん、無料の資料請求や見学予約も受け付けているので、スムーズに納骨堂を探せます。あなたに最適なお墓を選ぶために、ぜひ「いいお墓」をご活用ください。
全国の納骨堂ランキング
全国の納骨堂のランキングをご紹介します。納骨堂をご検討の場合は参考にしてみてください。
関東










関西






中部


北海道・東北
中国・四国




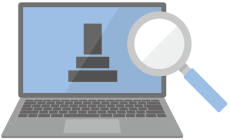
 かんたん
かんたん