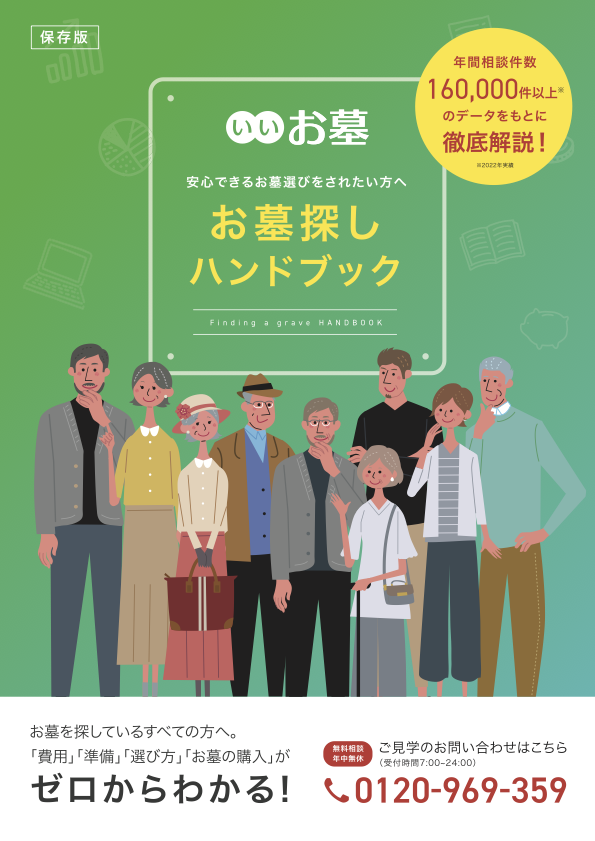合祀(ごうし)とは、骨壺から遺骨を取り出し、複数人の遺骨をまとめて埋葬すること。合祀墓(ごうしぼ)は、合葬墓(がっそうぼ)や永代供養(えいたいくよう)と混同されやすいですが、それぞれ意味が異なります。
この記事では、合祀・合祀墓の意味や費用相場、種類、メリット・デメリットなどを解説します。
合祀(ごうし)とは?遺骨をまとめて埋葬すること
合祀(ごうし)とは、複数人の遺骨をまとめて埋葬すること。「合(あ)わせて祀(まつ)る」という意味で、遺骨を骨壺から取り出して埋葬し、徐々に土へと返すのが一般的です。
合祀は本来、神道で使われる言葉で「複数の神や霊を合わせて一社に祀る」ことを指していましたが、近年では寺院・霊園でも使われています。
合祀墓(ごうしぼ)とは?複数人の遺骨を埋葬するお墓
合祀墓(ごうしぼ)とは、複数人の遺骨をまとめて埋葬するお墓で、「合同墓」「合葬墓」とも呼ばれます。家族・親族・先祖に限定せず、何の縁もない他人の遺骨と一緒に埋葬されます。遺骨を骨壺から取り出して埋葬するため、合祀後は個々の遺骨を取り出せません。
合祀墓の参拝方法
合祀墓は、墓標や参拝スペースが共用になっている霊園・寺院がほとんど。お墓参りするときは、参拝スペースに線香やお花をお供えするのが一般的です。
ただ施設によっては、線香・供花が禁止されていたり、定期的な合同供養が行われたりするため、事前に確認しておきましょう。
合祀墓の供養方法
合祀墓へ供養した後の供養方法は、墓地の運営管理者によって異なります。
寺院管理の合祀墓
寺院が管理する合祀墓は、住職や僧侶が定期的に供養してくれるのが基本。春秋の彼岸やお盆、祥月命日(故人の亡くなった月日)など、供養の頻度・時期は寺院によって変わります。境内にお墓があるため管理面は安心ですが、入檀が条件になっている寺院もあるため、注意してください。
公営霊園の合祀墓
合祀墓と合葬墓(がっそうぼ)の違い

- 合祀墓(ごうしぼ)骨壺から遺骨を取り出して、他人の遺骨と埋葬する
- 合葬墓(がっそうぼ)骨壺や骨袋に遺骨を入れて、他人の遺骨と埋葬する
合祀墓と合葬墓は、どちらも他人の遺骨とまとめて埋葬するお墓。ですが合葬墓は、遺骨を骨壺や骨袋に入れたまま埋葬するため、他人と遺骨が混ざりません。
また永代供養の合葬墓は、一定期間経過したら、遺骨を骨壺から取り出して合祀するのが一般的。弔い上げとなる33回忌を目処に合祀する霊園・寺院が多いようです。
公営霊園とは、自治体が管理・運営する霊園のこと。公営霊園の合祀墓は、運営管理者によって供養の方法や回数が違うため、事前の確認は必須です。また公営霊園は、宗旨宗派不問で低価格な合祀墓が多いため、墓所によっては競争率が高かったり申し込みに条件があったりします。
合祀墓と永代供養(えいたいくよう)の違い

- 合祀墓(ごうしぼ)遺骨の埋葬方法から見たお墓の一種
- 永代供養(えいたいくよう)遺骨を埋葬したあとの管理・供養方法の一種
永代供養(えいたいくよう)とは、遺族の代わりに霊園・寺院が遺骨を管理・供養すること。合祀墓は、他人とまとめて遺骨を埋葬するお墓を指しているため、「合祀墓=永代供養」ではありません。「永代供養というサービスのついた合祀墓」が正しい認識です。
永代供養がついているお墓は、合祀墓以外にもたくさんあります。遺骨を一定期間個別で保管する「合葬墓」や樹木を墓標とする「樹木葬」、納骨専用の施設「納骨堂」なども、永代供養でよく選ばれているお墓です。
合祀墓にかかる費用相場と内訳
- 永代供養料:お墓を維持・管理・供養するための費用
- 納骨料:合祀墓への納骨・納骨法要にかかる費用
- 刻字料:墓誌に故人の名前・戒名を彫刻してもらう費用
合祀墓にかかる費用の相場は、3万円〜30万円。費用の内訳は、大きく「永代供養料」「納骨料」「刻字料」の3つにわけられ、基本的に年間管理費はかかりません。
2024年にいいお墓が実施した「第15回お墓の消費者全国実態調査」によると、一般墓の平均購入価格は149.5万円。一般墓と比べると、合祀墓はかなり費用をおさえられることがわかります。
ただし経営母体やお寺の格式、墓地の立地などで金額は異なるので、あくまで目安として参考にしてください。一般的に、自治体が運営する公営施設は安価に、法人や民間企業が運営する民営施設は高額になる傾向があります。また、合祀墓によって供養の内容が違い、お寺に供養を依頼すると別途料金がかかる霊園・寺院も存在します。
合祀墓の種類

- 慰霊碑型合祀墓
- 樹木葬(自然葬)型合祀墓
- 納骨堂型合祀墓
- 立体型合祀墓
- 個別集合型合祀墓
- 区画型合祀墓
慰霊碑型合祀墓
慰霊碑型合祀墓とは、納骨スペースの上に石碑や供養塔、仏像などのモニュメントを建てた合祀墓。合祀墓のなかでもっともスタンダードで、モニュメントが目印となるため、従来のお墓と同じようにお墓参りできます。
樹木葬(自然葬)型合祀墓
樹木葬(自然葬)型合祀墓とは、墓石の代わりに樹木を墓標としている合祀墓。自然回帰をコンセプトにしたお墓で、1本の樹木(シンボルツリー)の下に、複数人の遺骨を直接埋葬するのが一般的です。樹木葬には、里山型や公園型、庭園型などの種類があります。
納骨堂型合祀墓
納骨堂型合祀墓とは、納骨専用の屋内施設にある合祀墓。ビルやマンションといった建物の一部に合祀スペースがあり、他人の遺骨とまとめて安置されます。納骨堂には、ロッカー式や仏壇式、機械式などの種類があります。
立体型合祀墓
立体型合祀墓とは、納骨スペースが地上と地下にわかれている合祀墓。最初は遺骨を骨壺に入れた状態で地上に保管し、一定期間経過したら、遺骨を骨壺から取り出して地下に埋葬します。
個別集合型合祀墓
個別集合型合祀墓とは、1つの大きなお墓の周囲に複数の区画が設けられている合祀墓。最初は区画ごとに個別埋葬され、期間が過ぎると合祀されるのが一般的です。
区画型合祀墓
区画型合祀墓とは、個々に専用の区画が設けられている合祀墓。それぞれの区画には納骨室があり、最初は個別で遺骨を安置しますが、最終的には合祀スペースに移動されます。
合祀墓・合祀のメリット
- お墓の管理・供養の負担を減らせる
- 無縁墓・無縁仏になる心配がない
- 通常のお墓より費用をおさえられる
- お墓の種類が豊富で選択肢が広い
- 宗旨宗派を問わないお墓が多い
お墓の管理・供養の負担を減らせる
合祀墓・合祀は、お墓の管理・供養を霊園や寺院にまかせられるのがメリット。お墓の清掃や法要の手配などが不要で、お墓参りのペースも調整しやすいため、家族の負担を大幅に減らせます。合祀墓・合祀は、単身者や子どものいないご夫婦、子どもに面倒をかけたくないご家庭など、現代のニーズに合致したお墓です。
無縁墓・無縁仏になる心配がない
合祀墓・合祀なら、霊園・寺院が存続している限り、無縁仏になる心配はありません。子孫がいないご家庭でも永続的に供養してもらえるので、安心して利用できます。
通常のお墓より費用をおさえられる
合祀墓・合祀は、すでに用意されているお墓に納骨するため、新たな墓石が不要。墓石代がかからないぶん、通常のお墓より費用をおさえやすいです。
また永代供養の合祀墓は、永代使用料(土地代)や管理料などが初期費用に含まれているお墓が多く、継続した支払いがないため金銭的負担が少ないです。
お墓の種類が豊富で選択肢が広い
合祀墓には、自然葬(樹木葬)型、納骨堂型、慰霊碑型など、さまざまな種類が存在します。選択肢が広く、ご自身が希望する埋葬方法や参拝のスタイルなどにあわせて、最適なお墓を選べるのも魅力です。
宗旨宗派を問わないお墓が多い
寺院墓地では、宗旨宗派が限定されたり、檀家に入るよう求められたりするのが一般的。ですが合祀墓・合祀は、宗旨宗派不問のお墓が多く、どなたでも利用できます。宗旨宗派に囚われない供養を希望している方に向いているお墓です。
合祀墓・合祀のデメリット
- 故人だけのお墓がない
- 合祀すると遺骨を取り出せない
- 墓じまいをしなければならない
- 家族や親族の理解を得る必要がある
故人だけのお墓がない
合祀墓・合祀は、1つの区画に複数の遺骨をまとめて埋葬するため、故人だけのお墓は存在しません。お墓が共用なので、従来のようなお墓参りや供養ができず、後悔されるご遺族もいらっしゃいます。
合祀したときのお墓参りや供養について、しっかりイメージしたうえで合祀墓を選ぶのが重要です。
合祀すると遺骨を取り出せない
一度合祀をすると、他人の遺骨と混ざってしまうため、個々の遺骨は取り出せません。後から「やっぱり個別のお墓を建てたい」「手元供養をしたい」と思っても、遺骨を返してもらえないので注意が必要。
すこしでも遺骨を取り出す可能性があるなら、一定期間個別で安置してもらえるお墓を選んだり、分骨して一部を手元に残したりしておくと安心でしょう。
墓じまいをしなければならない
墓じまいとは、お墓を解体・撤去して、更地にした土地を墓地管理者に返すこと。先祖代々のお墓から合祀墓に移動する場合は、墓じまいをしないと、管理料が発生し続けたり無縁仏になったりする可能性があります。
また、既存のお墓を返還(墓じまい)する費用と合祀墓へ引越し(改葬)する費用が、両方かかります。先祖代々のお墓を合祀墓に移動するときは、墓じまいと改葬、両方の費用をふまえて判断してください。
家族や親族の理解を得る必要がある
合祀墓は、通常のお墓と供養や参拝のスタイルが違います。伝統的なお墓に慣れ親しんでいる家族・親族は、抵抗感や喪失感を抱くかもしれません。また、先祖代々のお墓を墓じまいするのは、家族以外の親類縁者からの許可も必要です。
合祀墓の契約後に家族・親族から反対されて、キャンセルされる方もいるため、事前に周囲と話し合い、理解を得ておきましょう。
合祀墓・合祀が選ばれる理由
- お墓を継承したくない
- 先祖代々の遺骨を整理したい
- 無縁仏になる可能性がある
お墓を継承したくない
先祖代々のお墓を維持するのは、手間や時間、費用がかかります。また少子高齢化や核家族化、生涯未婚率の上昇などによって、お墓を引き継ぐ子孫がいないご家庭も増えています。
「残された家族に負担をかけたくない」「お墓の管理をするのが難しい」などの理由から、お墓を継承せず、永代供養の合祀墓を選択する方もいるようです。
先祖代々の遺骨を整理したい
先祖代々の遺骨を整理し、お墓を維持するために合祀墓・合祀を選ぶご家庭も存在します。
お墓の収骨スペースには限りがあるため、受け継ぐうちに新しい遺骨を埋葬できなくなるのが一般的です。古い遺骨を合祀することで、新しい骨壺を納めるスペースを確保できます。
無縁仏になる可能性がある
無縁仏とは、遺骨の管理・供養をする親類縁者がいなくなったお墓のこと。お墓の後継者が途絶えると、霊園・寺院に永代使用料(土地代)を支払う人がいなくなります。
霊園・寺院は、管理しているお墓が無縁仏になったら、行政手続きをして墓石を撤去し、遺骨を合祀墓に移動しなければなりません。霊園・寺院の負担が大きいため、無縁仏になる可能性があるなら、早い段階で墓じまいや合祀墓への移動を考えましょう。
合祀墓をお探しの方は「いいお墓」へ
合祀墓・合祀は、少子高齢化や核家族化、生涯未婚率の上昇などで家族のあり方が変わりつつある現代のニーズに合致するお墓。「お墓の跡継ぎがいらない」「費用をおさえられる」などメリットが多く、合祀墓を選択するご家庭も増えています。
一方、「遺骨を取り出せない」「従来のお墓参りができない」といったデメリットを把握せずに合祀墓を選択して、後悔する方もいらっしゃいます。家族や親族と話し合い、周囲の理解を得たうえで選択しましょう。
また合祀墓を選ぶときは、資料請求や現地見学を重ねて、複数の霊園・寺院を比較検討するのが大切。「いいお墓」では、エリアや条件にあわせて全国の合祀墓を一覧で確認できます。無料で資料請求や現地見学の予約もできるので、ぜひご活用ください。


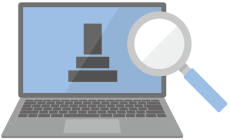
 かんたん
かんたん