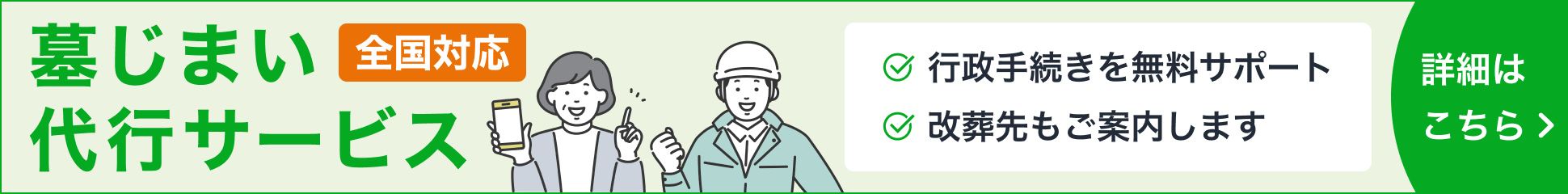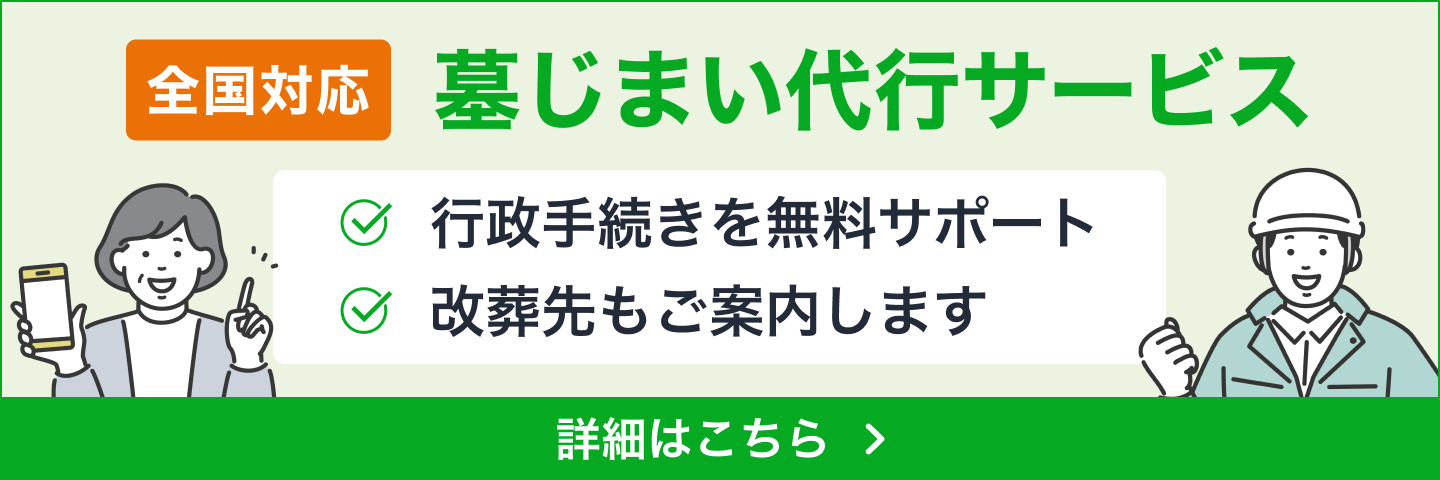墓じまいとは、今あるお墓を撤去・墓所を更地にして、管理者へ土地を返すこと。墓じまいして取り出された遺骨は、永代供養墓や樹木葬、納骨堂など、別のお墓にお引越し(=改葬)するのが一般的です。
この記事では、墓じまいが増えている理由や手続きの流れ、費用などを解説します。
墓じまいとは?お墓を撤去して土地を返還すること

墓じまいとは、墓石を撤去・墓所を更地にして、土地の使用権を管理者に返還すること。墓じまいをするには、行政の手続きと新しいお墓の準備が必要です。墓じまいをするお墓から新しいお墓に遺骨を埋葬・供養する、一連の流れを墓じまいとする考えもあります。
墓じまいと改葬の違い
「墓じまい」と似た言葉で「改葬」があります。墓じまいと改葬の違いを整理しておきましょう。
墓じまい
「墓じまい」とは、お墓を撤去して墓所を更地に戻し、墓地の管理者に返還することです。埋葬されていたご遺骨は、別のお墓に引越し(改葬)したり、合祀墓に埋葬したりします。
墓じまいには必ず改葬が伴います。お墓を片づけるからといって、お墓の中のご遺骨は処分できません。墓じまいでは、ご遺骨をどのような形で供養するか決める必要があります。
改葬
「改葬」は、今あるお墓から埋葬されているご遺骨を取り出し、所定の手続きを踏んで、一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬など、別のお墓に移動させること。いわゆる「お墓の引越し」を改葬と呼びます。
ご遺骨は法律上、勝手に処分・廃棄できないため、墓じまいや改葬をするには行政手続きが必要です。今あるお墓の管理者や住職、家族・親族などにも理解してもらわなければなりません。また、お墓の撤去費用は安くないため、慎重に検討してください。
墓じまいの手続きの流れ・手順・方法

墓じまいの流れは、新しく引越しするお墓の場所や埋葬方法などで異なります。墓じまいをする際の手続きは自治体によっても違うので、今あるお墓の所在地の役所で、改葬に必要な手続きや書類を確認してください。
ここでは、一般的な墓じまいの流れ・手順を紹介します。
1. 親族で話し合いをする
墓じまいをするときは、事前に親族と話し合っておくのが大切。お墓には、家族や一族を象徴する意味合いがあります。お墓を継ぐのは自分でも、親族から同意を得ていないと後々トラブルに発展してしまうかもしれません。
一人ひとりの墓じまいに対する意見に耳を傾け、親族間で話し合って合意形成しておくことで、無用なトラブルを回避できます。
2. 墓地管理者へ墓じまいの意思を伝える
親族の間で墓じまいをする合意が取れたら、今お墓のある霊園・寺院の管理者に墓じまいの意思を伝えます。
墓じまいをスムーズに進めるには、霊園・寺院に相談して事情を理解してもらうのが大切。とくに代々檀家としてお付き合いのある寺院に、墓じまいの意思を一方的に伝えるのはおすすめできません。墓じまいに至った家庭の事情や理由を丁寧に説明し、双方が納得したうえで、気持ちよく墓じまいしましょう。
墓じまいの意思を伝えたら、現在のお墓がある霊園・寺院の管理者に「埋蔵証明書(埋葬証明書)」を交付してもらいます。
3. 新しい納骨先を決める
墓じまいをするときは、ご遺骨をどのように供養するか考え、新しい納骨先を決めなければなりません。主な納骨先の選択肢には、「一般墓」「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬」などがあります。
納骨先が決まったら、改葬する霊園・寺院の管理者に「受入証明書」を交付してもらいます。
4. 墓石の撤去を依頼する石材店を決める
次に、お墓の解体や墓石の撤去作業をお願いする石材店を選びます。霊園・寺院が石材店を指定していないなら、複数の石材店から見積もりを取るとよいでしょう。同じ条件で見積もりを取得し、費用やサービスを比較・検討してください。
霊園・寺院によっては、利用できる石材店が決められているため、事前の確認は必須です。
5. 改葬許可申請の手続きを行う
遺骨をほかの場所に移すときは、改葬許可申請して「改葬許可証」を交付してもらいます。「改葬許可証」は、ご遺骨を取り出すために必要となる許可証です。
「改葬許可証」の交付に必要な書類は「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点。書類をそろえて市区町村に改葬許可申請をすると、「改葬許可証」が発行されます。「改葬許可証」は発行に時間がかかることがあるので、余裕をもって手続きしましょう。
「埋蔵証明書」は、現在のお墓の管理者から交付してもらいます。公営霊園は、各市区町村が窓口となっている場合もあるので確認してください。
「受入証明書」は、新たな納骨先の霊園・お寺の管理者から交付してもらいます。散骨や手元供養だと「改葬許可証」が不要な自治体もあるため、手続き方法を市区町村に問い合わせてみましょう。
「改葬許可申請書」は、役所の窓口で配布されていたり、郵送を受け付けていたりします。ホームページからダウンロードできる自治体もあるので、市区町村のサイトをチェックしてみましょう。記入事項は自治体によって異なるため、「改葬許可申請書」を取り寄せて様式を確認してください。
6. 遺骨の取り出し・閉眼供養を行う
墓じまいでは、ご遺骨を取り出す前に必ず閉眼供養を行います。閉眼供養とは、お墓に宿っている魂を抜くための供養で、「魂抜き」とも呼ばれています。
閉眼供養で読経をお願いした僧侶には、お布施をお渡しするのが通例です。浄土真宗では、「魂を入れる・抜く」という概念がないため、閉眼供養は行いません。
7. 墓石を撤去する
ご遺骨を取り出したら、墓石を解体・撤去して、お墓があった場所を更地に戻します。地上にあるお墓だけでなく、地下の基礎部分も撤去し、整地した土地の使用権を霊園・お寺の管理者に返却しましょう。
ご遺骨の取り出しは自分でもできますが、墓石の解体工事をする石材店に依頼するのが通例です。土葬の遺骨は、土を落として火葬をする必要があるので要注意。また、お墓に何度も足を運ぶのが大変な方は、閉眼供養と同日にすると負担を減らせます。
8. 改葬先に遺骨を納める
新しい改葬先のお墓にご遺骨を納めます。ご遺骨を埋葬するときは、僧侶に依頼してお墓に魂を入れる開眼供養を行います。閉眼供養をお願いした僧侶には、お布施をお渡しするのがマナー。
また埋葬時には、霊園・お寺の管理者に「改葬許可証」を提出します。
墓じまいの費用相場と内訳

- 墓じまいの費用相場:35万円〜150万円
- お墓の撤去に関する費用:30万円~50万円
- 行政手続きに関する費用:数百円~1,000円
- 新しい納骨先に関する費用:30万円~100万円
墓じまいにかかる費用は、総額で約35万円〜150万円程度。費用の内訳は「お墓の撤去」「行政手続き」「新しい納骨先」の3つです。
お墓の撤去に関する費用は、約30万円〜50万円。行政手続きに関する費用は数百円〜1,000円、新しい納骨先に関する費用は30万円〜100万円です。それぞれの費用の内訳と金額の目安を紹介します。
お墓の撤去に関する費用
| 作業内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 解体工事・整地作業 | 1㎡あたり10万円~ |
| ご遺骨のメンテナンス | 1万円~3万円 |
| 閉眼供養のお布施 | 3万円~10万円 |
| 離檀料 | 3万円~20万円 |
お墓の解体工事・整地作業:1㎡あたり10万円~
お墓を解体して更地にする費用の相場は、1㎡あたり10万円程度です。通路が狭くてクレーン車が入らなかったり、墓石・墓域が大きくて作業人数が多かったりすると、金額が上がります。
ご遺骨のメンテナンス:1万円~3万円
永年お墓に埋葬されていたご遺骨は、傷みや汚れがあるかもしれません。状態によっては、専門業者に依頼してご遺骨を洗ったりメンテナンスしたりしてもらいます。専門業者にご遺骨のメンテナンスを依頼したときの料金は、1万円〜3万円が目安です。
閉眼供養のお布施:3万円~10万円
お墓を撤去する前に閉眼供養をする場合、僧侶に読経をしていただいたお礼としてお布施を渡します。閉眼供養のお布施は3万円〜10万円が相場ですが、明確に金額が決められていません。寺院との関係性や地域の慣習によって違うので、確認しておきましょう。
離檀料:3万円~20万円
お寺が管理していたお墓を撤去・改葬するときは、檀家を離れるため、離檀料を支払う場合があります。離檀料の目安は3万円〜20万円で、法要で包むお布施の2〜3倍の金額が多いようです。
ただし、離檀料には法的根拠がなく、あくまでもお世話になった感謝を伝えるために渡すお金。お寺によって対応が違うため、確認してから用意するのが安心です。
行政手続きに関する費用
墓じまいをするときは、役所や墓地の管理者から書類を交付してもらう必要があります。
「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可証」の発行にかかる手数料は、数百円〜1,000円ほど。なかには、無料で発行されている書類もあります。自治体や管理者によって金額が異なるため、事前に確認してください。
改葬先の新しいお墓に関する費用
| 納骨先 | 費用相場 |
|---|---|
| 一般墓 | 100万円~200万円 |
| 永代供養墓 | 5万円~150万円 |
| 納骨堂 | 10万円~150万円 |
| 樹木葬 | 5万円~150万円 |
| 散骨 | 5万円~30万円 |
| 手元供養 | 3万円~10万円 |
既存のお墓から取り出したご遺骨は、新しい改葬先のお墓に納めます。改葬先にかかる費用は、選択するお墓の種類によって大きく異なります。
たとえば、一般的なお墓(一般墓)の費用相場は100万円〜200万円。お墓の場所や形態、大きさなどによって金額が変わります。また、永代供養墓は5万円〜150万円、納骨堂は10万円〜150万円、樹木葬は5万円〜150万円と、金額の幅は広いですが、一般墓より安価になりやすいです。
その他、墓石や墓所のいらない散骨は5万円〜30万円、手元供養は3万円〜10万円と、より費用をおさえられます。それぞれの埋葬先のお墓の相場をご確認ください。
墓じまいの補助金制度
墓じまいにかかる費用の総額は、35万円〜150万円と決して安い金額ではありません。自治体によっては、墓じまいの補助金制度を設けているため、活用してみるのがおすすめです。
墓じまいの補助金が支給される主な対象は、墓石の撤去費用。最大20万円で、工事にかかった料金の全額または一部を負担してくれる自治体が多いです。
ただし、墓じまいの補助金制度は、自治体によって支給の有無や金額、手続き方法が違います。お墓の所在地にある役所やホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
墓じまいした遺骨の納骨先・新しいお墓

- 一般墓
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 樹木葬
- 散骨
- 手元供養
墓じまいをするときは、ご遺骨をどのように供養するか考えなければいけません。墓じまいした遺骨の主な納骨先・新しいお墓には、「一般墓」「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬」「散骨」「手元供養」などがあります。
一般墓
一般墓とは、家族や一族といった家単位で継承していく伝統的なお墓です。「お墓」と聞いたとき、最初にイメージされるのは一般墓でしょう。
一般墓は、納骨室(カロート)に納めるご遺骨数に上限がなく、管理費を支払うことで永続的に使用できます。合祀されず、先祖代々のお墓を引き継いでいく一般墓は、ご先祖様の供養を自分たちで手厚く行えます。墓参りのために親族が集まるきっかけが生まれ、ご家族のより所にもなるでしょう。
「第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)」によると、一般墓の平均購入価格は149.5万円。費用の内訳は、墓石代が平均97.4万円、土地利用料が平均47.2万円です。
永代供養墓
永代供養とは、霊園・寺院が永代にわたってお墓を管理・供養することで、永代供養のあるお墓を「永代供養墓」と呼びます。そのため、永代供養つきの納骨堂や樹木葬も、永代供養墓に含まれます。永代供養墓は、お墓の継承者がいなくなっても、霊園・寺院が責任をもって管理し続けてくれるのが魅力です。
永代供養墓の費用相場は5万円〜150万円で、埋葬方法やお墓の形式によって金額が違います。たとえば、不特定多数の遺骨をまとめて埋葬する「合祀型」は、もっとも費用が安く、5万円〜30万円が相場です。一度合祀されるとご遺骨を取り出せませんが、ほかの永代供養墓より費用をおさえられます。また、個人単位で遺骨を埋葬する「個別型」は一定期間または永代にわたって個別供養されるため、合祀墓より高額です。相場は50万円〜150万円で、100万円以上かかる永代供養墓もあります。
納骨堂
納骨堂とは、ご遺骨を納めた骨壺を安置する建物のこと。永代供養される納骨堂がほとんどなので、お墓の管理を引き継ぐ必要がありません。また、屋内施設が多く、管理のしやすさや立地のよさから、近年はお墓より納骨堂を選ぶ人が増えています。
納骨堂には、扉付の収骨スペースに骨壺を安置する「ロッカー式」や参拝エリアまで遺骨が運ばれてくる「自動搬送式」、一定の年数を経てからご遺骨を合祀墓に移す「合祀式」などの種類があります。
「第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)」によると、納骨堂の納骨堂の平均購入価格は80.3万円。一般的な納骨堂の費用相場は、個人用が50万円、家族用が100万円です。
樹木葬
樹木葬は、墓石の代わりに樹木や草花を墓標(シンボルツリー)とするお墓で、ご遺骨を自然の中に埋葬・供養します。墓石がないぶん費用をおさえやすく、お墓の管理や継承者が不要なのがメリットです。
樹木葬は、環境によって「里山型」「公園型」「庭園型」の3種類に分けられます。また、「合祀型」「集合型」「個別型」など、複数の埋葬方法があるので、注意してください。
「第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)」によると、樹木葬の全国平均購入価格は63.7万円です。一般墓・納骨堂と比べて費用をおさられる傾向がわかります。
散骨
散骨とは、故人のご遺骨を粉末にして山や海などへ撒く供養方法。ご遺骨を手放し、納骨する墓石や墓所を用意しないため、維持費がかかりません。
散骨は、散布が許可されている土地や遺骨の粉砕する大きさが、法律で定められています。故人で散骨すると法に触れてしまう可能性があるので、専門業者に相談してください。
散骨にかかる費用は5万円〜30万円が目安です。最近は、ご遺骨の一部を散骨し、残りのご遺骨をお墓に埋葬する「分骨」を希望する方もいらっしゃいます。
手元供養
手元供養とは、ご遺骨の全部または一部を自宅に安置する供養方法。小型の骨壺や専用のアクセサリーなどにご遺骨を納め、手元で大切に保管できます。
手元供養は、納骨先が不要で維持費がかからないのがメリット。一方で、紛失・盗難のリスクがあったり、供養する人がいなくなると対応に困ったりするので注意が必要です。手元供養にかかる費用は供養方法によりさまざまですが、3万円〜10万円を目安とするとよいでしょう。
墓じまいのトラブル例と対策
墓じまいのトラブルは、親族・お寺・石材店との間で起きることが多いです。具体的なトラブル例と対策を把握しておくと、スムーズに墓じまいを進められます。
親族とのトラブル
墓じまいのトラブルでよく起こるのは、親族とのトラブルです。きちんと話し合いをせず、勝手に墓じまいを決めてしまうと、後々大きなトラブルに発展するかもしれません。
とくに年配のご親族は、先祖代々のお墓に思い入れがあり、墓じまいに抵抗がある方が多いです。また、お墓を継承する子どもに負担をかけたくないからと、勝手に樹木葬や納骨堂を選ぶのも避けましょう。家族・親族全員が納得できるまで話し合い、合意を得たうえで墓じまいを選択してください。
寺院とのトラブル
撤去したいお墓を管理しているのが寺院墓地の場合、お寺が墓じまいを認めていないかもしれません。「離檀する際に高額な離檀料を請求をされた」「改葬許可申請書に印鑑を押してくれない」「閉眼供養をしてくれない」など、何かとトラブルになるお寺もあるようです。
とくに地方では、過疎化が進んで檀家が減ると死活問題になるため、墓じまいに協力的でない寺院もあります。
墓じまいをするときは、住職をはじめ、お世話になった方々に対して感謝の気持ちを伝えるのが大切。そのうえで、墓じまいをする理由を丁寧に伝え、正しく理解してもらいましょう。簡単に解決しない場合は、弁護士をはじめとする第三者を交えて話し合いを進めるのが得策です。改葬先の方は、基本的には仲介に入ってもらえません。
石材店とのトラブル
墓石の撤去を依頼した石材店から、高額な費用を請求されてトラブルにつながるケースがあります。墓石の撤去費用は1㎡あたり10万円〜が相場で、場所の地形や立地、周辺環境によって金額が変わります。相場より金額が高いときは、理由や内訳を確認するようにしてください。
一方で、費用が安すぎる石材店も注意が必要です。撤去した墓石の処理や工事に、何か問題があるかもしれません。石材店とのトラブルを防ぐには、事前に複数の業者から相見積もりを取って比較するのが大切。墓じまいの評判や口コミ情報も収集して、依頼する石材店を決めるのがおすすめです。
いいお墓では墓石の撤去から各種手続き、改葬先のご案内まで墓じまいの全工程をサポートし、明朗な見積もりを提示しております
墓じまいが増加している理由

厚生労働省の「令和5年度衛生行政報告例」によると、2023年度(令和5年度)は全国で16万6,886件の墓じまいがありました。また、継承されないお墓・無縁墓を行政が撤去した件数は、全国で3,651件になっています。
2022年度の墓じまいの件数は全国で15万1,076件、無縁墓を撤去した件数は全国で3,414件でした。墓じまいは、毎年、増加傾向にあります。これまでは、2019年度の12万4,346件が最多でしたが、2022年を境に急増しています。また都道府県で墓じまいが多いのは、東京都(1万4,950件)、北海道(1万2,948件)、兵庫県(9,119件)でした。
墓じまいが増えている大きな理由は、「少子化や核家族化によりお墓の継承者がいない」こと。そのほか、「子どもたちにお墓を継ぐ負担をかけたくない」「高齢になりお墓の管理ができなくなった」「お墓を維持するためにお金をかけたくない」など、墓じまいを考えている方々にはさまざまな理由があります。なかには、地域一体が過疎化していて、墓じまいを考えなければならない切実な地方もあります。
また最近は、自分で埋葬の仕方を決めたいと、今あるお墓を墓じまいして、樹木葬、永代供養墓、納骨堂、散骨など、継承者を必要としない埋葬方法を選ぶ人もいらっしゃいます。ライフスタイルの多様性やお墓に対する価値観の変化などが、墓じまいが増える要因になっているようです。
お墓の持ち主が自ら墓じまいしている
お墓の管理をする子どもがいても、お墓を継げない理由があって墓じまいを選択する方もいます。とくに多い理由は、現在の住まいがお墓から遠く離れていて、お墓参りになかなか行けないから。住まいとお墓が遠い場合、現在あるお墓を解体・撤去して、継承者が住む場所の近くにお墓を移します。
お墓に埋葬されていたご遺骨は、取り出して改葬先のお墓に移しますが、一般墓のほか、樹木葬、永代供養墓、納骨堂、散骨などを選択する方も多いです。
お墓の継承者がいない無縁墓が増えている
昨今、無縁墓が増加しています。無縁墓とは、お墓の継承者がいなくなり、手入れや法要をされずに放置されているお墓です。お墓参りや掃除をする人がいないため、墓石が古びた状態になったり、雑草が伸び放題で霊園の景観を悪くしたりしています。
無縁墓になってしまう理由は、「お墓を継ぐ子どもがいない」「子どもはいるがお墓の存在を知らない」「お墓を知っているが放置している」などさまざまです。継承者が名乗りでないと、お墓は撤去されます。将来、無縁墓になるリスクをふまえて、墓じまいを選択するご家庭が増えています。
墓じまいをしないとどうなる?
お墓を建てている土地は、契約によって霊園・寺院から借りている状態。そのため、お墓を利用している間は霊園・お寺に管理料を支払うのがルールです。墓じまいをせず、放置されたお墓は管理料の支払いが滞ってしまいます。一定期間未払いになると、「無縁仏」「無縁墓」として扱われて、強制的にお墓を撤去されるのが一般的です。
お墓を強制撤去されたあとのご遺骨は、不特定多数の遺骨とまとめて合祀墓に埋葬されます。一度合祀されると、後から「もう一度埋葬し直したい」と思っても遺骨を取り出せません。お墓の継承者がいない、もしくはいなくなる可能性があるなら、墓じまいを検討してお墓の放置を避けるようにしましょう。
墓じまいはいつまで?してはいけない時期は?
墓じまいをする時期に決まりはありません。家族・親族のご都合に合わせて、お好きなタイミングで墓じまいをすればよいでしょう。
ただ、お墓の撤去・解体作業をするにあたって、寺院・石材店が忙しいお盆・お彼岸やお正月は避けた方が無難です。また、降雨量の多い梅雨や雪が積もる冬の時期は、墓石の解体工事が進みにくいため外してください。
後悔のない墓じまいにするには事前準備が大切
墓じまいは、残された家族や子どもの負担を軽減でき、お墓が無縁仏になる心配もなくなります。ただ、周囲と相談せず、墓じまいを勝手に進めると、トラブルが起きかねません。家族・親族や墓地管理者ときちんと話し合い、理解を得たうえで墓じまいをはじめてください。また、墓じまいの流れや費用、トラブル例を理解しておくとスムーズです。
とくに費用は、墓じまいでもっともトラブルや後悔が起きやすいので、注意が必要。墓じまいは完了までの手続きが多く、必要な費用もやや不透明なのが実態です。まずは、複数の業者から見積りを取り、墓じまいにかかる費用の全体感を把握しましょう。