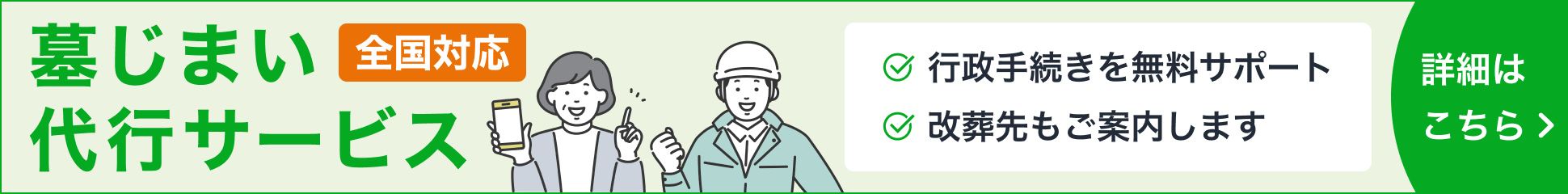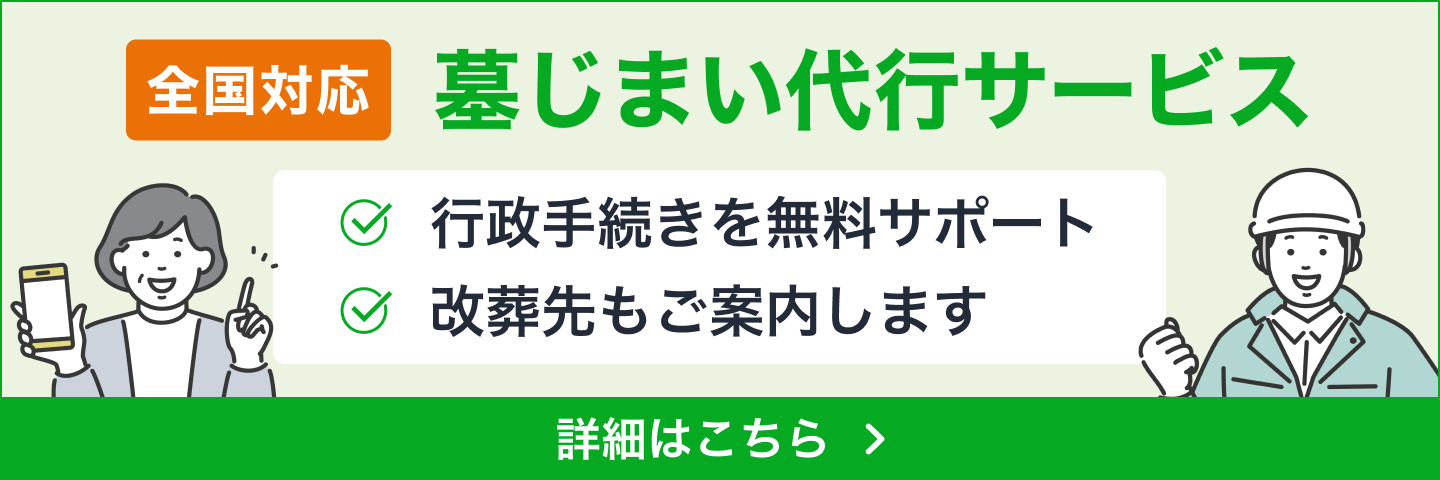浄土真宗の墓じまいの流れや費用は、一般的な墓じまいとほとんど変わりません。ただし、浄土真宗では「故人は死後すぐに成仏する」と考えられているため、閉眼供養や開眼供養は不要です。永代供養の概念もありませんが、永代供養墓のある寺院や宗教不問の霊園に納骨すれば、浄土真宗でも墓じまい・永代供養ができます。
この記事では、浄土真宗の墓じまいの特徴や費用相場、具体的な手順を解説します。
浄土真宗の墓じまいとは?他宗派との違い
浄土真宗には永代供養の概念がない
浄土真宗では、阿弥陀如来の救い(他力)によって、すべての人が成仏できる「他力本願」という教えを説いています。「故人は死後すぐに成仏して極楽浄土へ旅立ち、そこで生まれ変わる」と考えられているため、そもそも供養の概念がありません。
そのため浄土真宗には、故人を永代にわたって供養する「永代供養」の概念もないのです。
ちなみに浄土真宗におけるお墓は、故人の霊魂が宿る場所ではありません。「極楽浄土へ旅立った故人を想いながら、阿弥陀様への信仰心を新たにして仏縁を結ぶ場所」とされています。またお経は、故人を供養するためではなく、集まった人々に教えを伝えるために読まれます。
浄土真宗の墓じまいでは閉眼供養が不要
多宗派の墓じまいでは、墓石を解体する前にお墓から魂を抜く「閉眼供養」を行うのが一般的です。ただし浄土真宗では、故人は死後すぐに極楽浄土に旅立つとされているので、お墓には魂が入っていません。そのため、浄土真宗では閉眼供養を行いません。
浄土真宗の墓じまいでは、閉眼供養の代わりに「遷仏法要(せんぶつほうよう)」や「遷座法要(せんざほうよう)」を行います。遷仏法要・遷座法要はご本尊を移動するための儀式で、閉眼供養との違いは読経供養で読むお経だけです。法要の手順や施主の準備、お布施の費用などは閉眼供養と変わりません。
浄土真宗は開眼法要ではなく建碑法要を行う
多宗派の墓じまいでは、改葬先の新しいお墓に魂を込める「開眼法要」を行います。開眼法要は「お性根(おしょうね)入れ」「お魂(たましい)入れ」とも呼ばれ、法要をすることでお墓に仏様の魂が宿ると考えられています。
浄土真宗の墓じまいでは、閉眼供養と同じように開眼法要も行いません。浄土真宗では、開眼法要の代わりに、「建碑(けんぴ)法要」または「建碑式」を行います。建碑法要・建碑式は、お墓を新しく建てたことを記念して営む法要です。
浄土真宗のお墓の特徴
墓石の正面に家名を刻まない
他の宗派では、墓石の正面に「〇〇家先祖代々之墓」「〇〇家之墓」と家名を刻むのが通例です。対して、浄土真宗の墓石には「南無阿弥陀仏」または「倶会一処(くえいっしょ)」と刻みます。「南無阿弥陀仏」は、「阿弥陀様どうかお救いください」という意味の念仏。「倶会一処」は、「故人や先祖と極楽浄土で再会する」という意味の言葉です。
浄土真宗のお墓に家名を入れるときは、二段目の台石や花立てに刻みます。また、浄土真宗は阿弥陀様ご自身を信仰するため、お墓に阿弥陀様の分身となる梵字・仏種子を刻んではいけないとされています。
墓誌ではなく法名碑と呼ぶ
多宗派では、お墓の横に建てる、故人の名前や戒名を刻む石碑を「墓誌」「霊標」と呼びます。
一方の浄土真宗では、戒名ではなく法名を使うため、「法名碑」と呼びます。浄土真宗のお墓に故人の霊は宿っていないので、「霊位」をはじめとする「霊」の文字は使用しません。また、棹石に法名を記載するのであれば、法名碑は必須ではありません。
卒塔婆を使用しない
卒塔婆とは、故人の追善供養のためにお墓の後ろに立てる縦長の木片です。浄土真宗では、故人は死後すぐに成仏するとされるので、追善供養の考え方はありません。他の宗派のように卒塔婆を立てて卒塔婆供養をしないので、卒塔婆や卒塔婆立は不要です。
五輪塔や宝塔を建てない
五輪塔とは、先祖の霊をまとめて祀る塔で、お墓のそばに建てます。故人の魂が死後すぐに極楽浄土に旅立つ浄土真宗では、先祖の霊を塔で祀る必要がないため、五輪塔を建てません。また、阿弥陀様のみを信心すべきとされ、地蔵像や観音像、宝塔なども建てるべきではないとされています。
墓相や吉凶占いにこだわらない
墓相とは、墓石の色や形、お墓の向きなどが運気に影響を及ぼすという占いの一種です。浄土真宗では、阿弥陀様がすべてをお決めになると考えられているため、お墓の方位や形、色などが吉凶を左右する墓相は気にしないとされています。
浄土真宗の墓じまいにおける費用の相場

| 墓じまいにかかる費用 | |
|---|---|
| 墓じまい費用の総額 | 35万円~150万円 |
| お墓の撤去に関する費用 | 30万円~50万円 |
| 行政手続きに関する費用 | 数百円~1,000円 |
| 新しい納骨先に関する費用 | 30万円~100万円 |
浄土真宗の墓じまいにかかる費用は、他の宗旨宗派による墓じまいと基本的に変わりません。
一般的な墓じまい費用の相場は、総額35万円〜150万円。内訳は、「お墓の撤去に関する費用」「行政手続きに関する費用」「新しい納骨先に関する費用」の3つです。
墓じまいの費用は、撤去するお墓の墓地面積や周辺環境、撤去後の供養方法によって大きく変動します。内訳別に、浄土真宗における墓じまいの費用の詳細を確認しておきましょう。
浄土真宗の墓じまいにおける費用の内訳
1:お墓の撤去に関する費用(30万円~50万円)

| 支払い先 | 費用の内訳 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 石材店・業者 | 墓石の撤去費用 | 10万円〜30万円 |
| ご遺骨の取り出し費用 | 1万円〜3万円 | |
| ご遺骨の運送費用 | ※距離・方法で異なる | |
| お寺・僧侶 | 遷仏法要のお布施 | 3万円〜10万円 |
| 離檀料 | 3万円〜20万円 |
お墓の撤去にかかる費用の相場は、30万円〜50万円です。
墓石の撤去費用は、お墓の状態や周辺環境などによって変わりますが、目安は10万円〜30万円。ご遺骨の取り出しやメンテナンス、運搬を依頼するなら、追加で数万円の費用がかかります。
また、浄土真宗は閉眼供養の代わりに遷仏法要を行いますが、読経供養で読むお経が違うだけでお布施の金額は変わりません。遷仏法要のお布施の相場は3万円〜10万円で、墓じまいをして檀家を離れるなら別に離檀料も必要です。離檀料の費用相場は3万円〜20万円ですが、僧侶との関係性や寺院の方針、地域などによって変わるので確認しておくと安心です。
2:行政手続きに関する費用(数百円~1,000円)

| 入手先 | 書類 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 既存のお墓の管理者 | 埋蔵証明書 | 300円~1,500円 |
| 新しい納骨先の管理者 | 受入証明書 | 無料 |
| 自治体の窓口 | 改葬許可申請書(改葬許可証) | 無料~1,000円 |
行政手続きに関する費用の相場は、数百円〜1,000円です。
墓じまいするときは、役所や墓地の管理者から書類を交付してもらう必要があります。自治体や管理者によって金額が異なりますが、発行時に数百円から1,000円ほど手数料が発生します。あらかじめ問い合わせて確認しておきましょう。
3:新しい納骨先に関する費用(30万円~100万円)

| 支払い先 | 納骨先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 新しい納骨先 | 永代供養墓 | 5万円~150万円 |
| 納骨堂 | 10万円~150万円 | |
| 樹木葬 | 5万円~150万円 | |
| 散骨 | 5万円~30万円 | |
| 手元供養 | 3万円~10万円 | |
| 一般墓 | 100万円~200万円 | |
| お寺・僧侶 | 建碑法要のお布施 | 3万円~5万円 |
新しい納骨先に関する費用の相場は、30万円〜100万円です。
墓じまいでは、既存のお墓から取り出した遺骨を納めるために、新しい納骨先を用意しなければなりません。納骨先によって費用が大きく異なるので、相場金額の幅が広くなっています。また浄土真宗では、新しいお墓を建立した記念に「建碑法要」を行います。建碑法要で僧侶にお渡しするお布施は、3万円〜5万円ほど包むのが目安です。
浄土真宗で墓じまい・永代供養をする方法
- 宗旨宗派不問の民営霊園を利用する
- 菩提寺に相談してみる
- 永代供養墓のある浄土真宗のお寺を探す
- 浄土真宗の本山に納骨する
本来、浄土真宗に永代供養の概念はありません。ですが、方法によっては、浄土真宗でも新しい納骨先に永代供養を選択できます。浄土真宗で墓じまい・永代供養をする主な4つの方法を紹介します。
宗旨宗派不問の民営霊園を利用する
宗旨宗派の制限がない民営霊園を利用すれば、浄土真宗でも永代供養が可能です。
民営霊園とは、宗教法人や財団法人、社会法人などが運営母体となり、民間企業が委託を受けて運営する霊園。民営霊園には、宗旨宗派や居住場所、年数などの申し込み条件がほとんどありません。もちろん、浄土真宗の方も利用できるのでご希望の永代供養墓を選択できます。
菩提寺に相談してみる
菩提寺があるなら、一度ご住職に相談してみるのもひとつの方法です。
ただし、浄土真宗には永代供養の概念がないため、伝え方には注意が必要。「永代供養をお願いしたい」と伝えると、受け入れてもらえないかもしれません。「後継者がいないので、お墓や遺骨を永続的に管理してもらえないか」と、事情を説明して相談するのがよいでしょう。
浄土真宗では、引き取り手のない遺骨を納める供養塔のある寺院もあります。菩提寺で対応するのが難しくても、他の方法を教えてくれるかもしれません。
永代供養墓のある浄土真宗のお寺を探す
永代供養墓は、「遠方に住んでいてお墓の管理ができない」「お墓の後継者がいない」などの理由から近年選択する方が多いお墓です。需要が増え、認知が広がるにつれて、永代供養墓を設置する浄土真宗のお寺が出てきています。
浄土真宗の永代供養墓でも、一般的な永代供養墓と同じようにお墓の管理・供養をしてくれます。まだ数は少ないですが、浄土真宗にこだわって永代供養をしたい方は探してみてください。
浄土真宗の本山に納骨する
浄土真宗の本山に納骨するのも、永代供養する方法のひとつです。本山納骨とは、開祖のご廟所(墓所)に遺骨を埋葬する供養方法。浄土真宗の本山納骨は、本願寺派は大谷本廟、真宗大谷派は大谷祖廟で、浄土真宗の開祖・親鸞が眠る廟所へ納骨します。
ちなみに、浄土真宗では「喉仏の骨を分骨して本山に納骨する」という宗派特有の慣習があります。他の宗派では「分骨すると成仏できない」と考えられていますが、往生即身仏の教えのある浄土真宗では問題ありません。
浄土真宗の墓じまいの流れ
- 家族・親族で話し合いをする
- 墓地管理者へ墓じまいの意思を伝える
- 新しい納骨先を決める
- 墓石撤去を依頼する石材店を決める
- 改葬許可申請の手続きを行う
- 遷仏法要を行う
- 墓石を撤去して土地を返還する
- 改葬先に遺骨を納める
浄土真宗の墓じまいの流れは、大きく8つのステップに分かれます。浄土真宗の墓じまいが他の宗旨宗派と違うのは、閉眼供養に代わる「遷仏法要」を行うことです。
ここからは、浄土真宗の墓じまいの流れや、手続きの手順を確認していきましょう。
1. 家族・親族で話し合いをする
墓じまいするときは、事前に家族・親族と話し合いをしておくこと。お墓は、一族の象徴や家族の拠り所にもなる大切な場所です。自分がお墓を継承したからといって、勝手に墓じまいを進めるのはやめましょう。
まずは、家族・親族の合意を得られるよう、墓じまいを考えている理由を丁寧に説明してください。全員が納得して墓じまいをすることで、無用なトラブルを避けられます。
2. 墓地管理者へ墓じまいを伝える
家族・親族で墓じまいの合意がとれたら、お墓を管理しているお寺・霊園に墓じまいの意思を伝えます。これまでお世話になった感謝を伝えたうえで、墓じまいを検討している理由や家庭の事情を説明するとスムーズです。
お寺の住職から了承を得たら、「埋葬(納骨)証明書」を発行していただきます。
3. 新しい納骨先を決める
墓じまいをしたあと、遺骨を供養する納骨先を決定します。墓じまいは、お墓の管理・供養が難しくなって選択する方が多いので、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などの改葬先が人気です。それぞれの特徴や費用を理解したうえで、最適なお墓を選ぶようにしてください。また、納骨先を決めるときは、いくつか資料請求や現地見学をして比較検討するのが大切です。
改葬先が決まったら、納骨先のお寺・霊園の管理者に「受入申請書(永代供養許可証)」を交付してもらいます。
4. 墓石撤去を依頼する石材店を決める
墓じまいで、墓石の撤去や墓所の整地をお願いする石材店・業者を選びましょう。墓石工事の費用は、立地や周辺環境、石材店の価格設定などによって変わります。工事費用で後悔したくないなら、複数の石材店から見積もりを取得して、比較検討するのが大切です。
お寺・霊園によっては、工事を依頼する石材店が指定されています。指定石材店があるお寺・霊園では、他の石材店に依頼できないので、事前に確認しておいてください。
いいお墓では墓石の撤去から各種手続き、改葬先のご案内まで墓じまいの全工程をサポートし、明朗な見積もりを提示しております
5. 改葬許可申請の手続きを行う
墓じまいして遺骨を取り出し、他の場所に移すときは「改葬許可証」が必要です。「改葬許可証」は、お墓の移転元の自治体に「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点を提出することで交付されます。
埋葬証明書は現在のお墓の管理者、受入証明書は新しい納骨先の管理者、改葬許可申請書は移転元の自治体から取り寄せます。3つの書類が用意できたら、各市区町村の窓口で改葬許可申請をしてください。
なお、改葬許可証は発行までには時間がかかることがあるので、余裕をもって手続きしましょう。また、改葬許可証は遺骨の数だけ必要です。複数の遺骨を埋葬しているお墓もあるので、遺骨1体につき、改葬許可証を1枚用意します。
埋葬(納骨)証明書は、現在のお墓の管理者に交付をしてもらいます。なお、公営霊園は各市区町村が窓口となっている場合もあります。
受入申請書(永代供養許可証)は、新しい納骨先のお寺・霊園の管理者に交付してもらいます。散骨や手元供養をする場合は、各市区町村に手続き方法を問い合わせておきましょう。
改葬許可申請書は、基本的に各自治体によって異なります。改葬許可申請書は郵送で取り寄せるか、自治体のホームページから取得できるので、各市区町村のサイトを確認してください。
6. 遷仏法要を行う
浄土真宗の墓じまいでは、閉眼供養の代わりに「遷仏法要」や「遷座法要」を行います。
遷仏法要・遷座法要は、ご本尊を移動するための儀式で、僧侶を手配して読経してもらいます。法要のあとは、読経してくださったお礼として僧侶にお布施を渡しましょう。
7. 墓石を撤去して土地を返還する
遷仏法要・遷座法要が終わったら、遺骨を取り出して墓石の撤去を行い、墓所を更地にして土地をお寺・霊園に返却します。
遺骨の取り出しは自分で対応できますが、墓石の解体工事をする石材店に、あわせて依頼するのが通例です。ちなみに土葬の遺骨は、土を落としてから火葬する必要があるので注意してください。
8. 改葬先に遺骨を納める
最後に、新しい納骨先に取り出した遺骨を納めます。浄土真宗では、開眼供養の代わりに「建碑法要」または「建碑式」を行います。また、納骨時には墓地管理者に改葬許可証を提出してください。
浄土真宗の墓じまいをお考えなら「いいお墓」へ
浄土真宗の墓じまいにかかる費用や流れは、他の宗派と大きく変わりません。
ただし、浄土真宗では「故人の魂は、死後すぐに極楽浄土に旅立つ」と考えられています。そのため、浄土真宗の墓じまいでは、お墓から魂を抜く閉眼供養の代わりに「遷仏法要」を、お墓に魂を込める開眼法要の代わりに「建碑法要」を行います。
また、浄土真宗には永代供養の概念もありませんが、永代供養墓のある浄土真宗のお寺や宗旨宗派不問の霊園に納骨すれば、永代供養墓の利用は可能です。
浄土真宗の墓じまいも、一般的な墓じまいと同様に、家族・親族としっかり話し合うのが大切。さらに工事を依頼する石材店や新しい納骨先は、比較検討することで後悔のない墓じまいにつながります。
「いいお墓」では、墓じまいの基本がよくわかるガイドブックや、墓じまい業者の一括見積もりサービスをご提供しています。墓じまいをよりスムーズに進めるために、ぜひ「いいお墓」をご利用ください。
いいお墓の墓じまい
墓じまい(改葬)は完了するまでの手続きも多く、必要な費用も不透明なところが多いのが実態です。