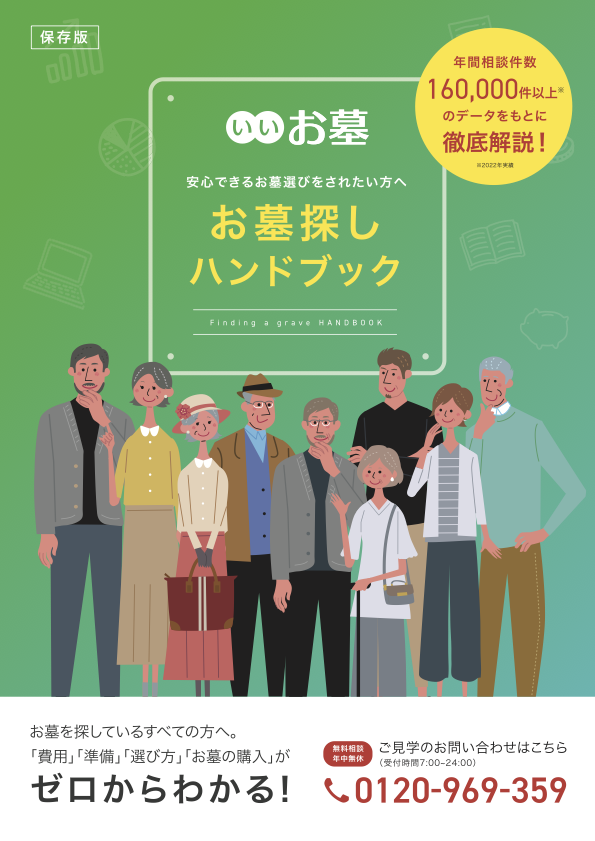樹木葬は、墓石の代わりに樹木を目印にするお墓の一種。墓石分の費用が安くおさえられる上、承継者を必要としないため、現代のニーズに合った埋葬方法といえます。
この記事では、樹木葬の特徴や他のお墓との違い、種類、費用相場などを詳しく解説します。
樹木葬とは?樹木を墓標とする永代供養墓
樹木葬の特徴
- 墓石ではなく樹木を墓標とするお墓
- 墓石がないぶん費用をおさえやすい
- 跡継ぎが不要な永代供養墓のひとつ
樹木葬は、樹木を墓標(シンボルツリー)として、遺骨を自然に還す埋葬方法。自然志向の新しいお墓の形で、樹林墓地とも呼ばれます。
石材費がかからないうえに、ユニット部品を使用することで作業や造形コストが減るため、費用をおさえられるのが魅力。また永代供養墓の一種で、埋葬後のメンテナンスは寺院・霊園に任せられます。
ちなみに日本で最初の樹木葬をはじめたのは、岩手県一関市の祥雲寺(2006年から管理運営は知勝院)。1999年7月、一関市から許可を受け、地元の山林を樹木葬としたのが最初です。日本初の樹木葬として注目を集め、その後日本全国に樹木葬が広がっていきました。
永代供養とは、遺族の代わりに寺院・霊園が遺骨を管理・供養してくれる供養方法です。樹木葬は永代供養墓の一種で、他にも納骨堂や合祀慕、集合墓などが含まれます。
樹木葬を選ぶ人の割合

「第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)」によると、お墓の種類のなかでもっとも選ばれているのは樹木葬。48.7%と約半数の方が樹木葬を選択しています。
過去のデータを見ると、2010年ごろは一般墓が主流でしたが、2020年に樹木葬が逆転。消費者の嗜好が変わり、お墓を継がせたくない・費用をおさえたい・自然回帰したいといった要望から、樹木葬を選択する方が増えているようです。
樹木葬に使われる樹木
| サクラ(桜) | ツツジ(映山紅) | サルスベリ(百日紅) |
| ハナミズキ(花水木) | アジサイ(紫陽花) | モミジ(紅葉) |
| カラマツ(落葉松) | ポプラ(箱柳) | クスノキ(樟) |
樹木葬の墓標に多いのは、人々に馴染みがあって花が咲く樹木。たとえば日本人に好まれるサクラや常緑樹のクスノキ、紅葉を見られるモミジなどが選ばれています。
樹木葬に使われる樹木は、霊園や墓地によって募集時に決められていたり、候補から好きな樹木や低木、花を選べたりします。
樹木葬を他のお墓と比較!墓標・後継者・埋葬場所の違い
| 墓標 | 後継者 | 埋葬場所 | |
|---|---|---|---|
| 樹木葬 | 樹木 | 不要 | 屋外 |
| 一般墓 | 墓石 | 必要 | 屋外 |
| 納骨堂 | なし | 不要 | 屋内 |
| 散骨 | なし | 不要 | 屋外 |
樹木葬と一般墓の違いは、墓標と後継者の必要性。樹木葬は樹木が墓標で後継者が不要なのに対して、一般墓は墓石が墓標で必ず後継者が管理しなければなりません。
また、樹木葬と納骨堂は同じ永代供養墓の一種ですが、樹木葬は屋外、納骨堂は屋内で遺骨を管理するという違いがあります。
海や山に粉骨した遺骨を撒く散骨は、樹木葬と違って墓標が不明確です。
樹木葬の種類は里山型・公園型・庭園型
樹木葬は、大きく分けて里山型、公園型、庭園型の3種類あります。
里山型

里山型は、山林や丘など自然と密接した環境に遺骨を埋葬する樹木葬。「人を弔う墓地で里山の草木を育てる」といった自然保全の目的があります。一区画に1本ずつ墓標となる樹木を植樹する樹木葬が多いようです。
里山型のメリット
- 自然環境に優しい
- 自然回帰志向を実現できる
里山型のデメリット
- 郊外に多く、交通アクセスが悪い
- 景観が自然や四季に左右されやすい
公園型

公園型は、霊園・寺院の一角を整備して遺骨を埋葬する樹木葬。花木を植えたり、墓域をマウント状にして芝生を植えたりと、公園のように環境が整備されています。
公園型の樹木葬は、1本~数本の樹木を墓域に植えるシンボルツリー型が主流です。一方で、区画ごとに1本ずつ樹木を植える寺院・霊園もあります。
公園型のメリット
- 敷地が広く、景観が美しい
- 庭園型より比較的費用が安い
公園型のデメリット
- 面積が必要なため、やや郊外に多い
庭園型

庭園型は、霊園・寺院のごく限られたスペースに遺骨を埋葬する樹木葬。墓標となるシンボルツリーや花木が庭園・ガーデニング風に植えられ、整理された美しさがあります。公園型より敷地が狭く、都市部に多いため“都市型”の樹木葬といえるでしょう。
庭園型のメリット
- 庭園風の整理された美しさを楽しめる
- 都市部に多く、アクセスしやすい
庭園型のデメリット
- 郊外の樹木葬と比べると価格が高め
樹木葬の埋葬方法は合祀型・集合型・個別型
樹木葬は、埋葬方法にも複数の種類があります。
ここでは、合祀型・集合型・個別型と、代表的な3つの埋葬方法を紹介します。
合祀型(合葬型)

合祀(ごうし)型は、1つの区画に複数の人の遺骨をまとめて埋葬する方法で、合葬型とも呼ばれます。骨壺を使わないため、他の人と遺骨が完全に混ざり、1本の樹木を墓標(シンボルツリー)として共用します。一度合祀すると、特定の故人の遺骨だけを取り出すことはできないので注意してください。
合祀型の相場は5万円〜30万円と、もっとも安い埋葬方法です。
集合型

集合型は、1本のシンボルツリーに複数の区画があり、区画ごとに遺骨を埋葬する方法。合祀型と違って、他の人と遺骨が混ざらないのが特徴です。区画が分かれてない場合、遺骨を袋や骨壺に入れて混ざらないようにしている樹木葬もあります。
集合型の樹木葬は、合祀型より値段が上がり、10万円〜60万円が相場です。
個別型

個別型は、個々の区画に遺骨を埋葬する方法で、1区画に1本シンボルツリーを植えるのが一般的です。個人はもちろん、夫婦や家族単位で埋葬してもらえます。また納骨後、一定年数が経過したら合祀墓に移動し、永代供養されることがほとんどです。
個別型は、個々に区画と樹木が割り当てられるため、20万円〜150万円と相場がもっとも高いです。
樹木葬の費用相場は63.7万円

樹木葬の費用相場は、立地や埋葬方法によって変わります。ただし一般的には、墓石がないぶん一般墓より石材費がかからず、費用をおさえやすいでしょう。
実際に「第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)」によると、樹木葬の平均購入価格は63.7万円。一般墓149.5万円、納骨堂80.3万円と比べると、樹木葬は約16万円〜85万円安いです。また樹木葬は、直近5年間は70万円前後で推移しており、相場は安定しています。
樹木葬のメリット・デメリット
樹木葬のメリット
- 継承者が不要な永代供養が基本
- 墓石がないぶん一般墓より費用をおさえやすい
- 「死後は自然に還りたい」という希望を満たせる
樹木葬のデメリット
- 契約期間が決まっている墓地が多い
- 埋葬方法によって後から遺骨を取り出せない
- 個別のお墓参りが難しくなる可能性がある
樹木葬を選ぶ3つのポイント
- 種類と埋葬方法
- 立地条件
- 設備管理
樹木葬は、霊園・寺院によって種類や埋葬方法が違うため、ご自身の希望にあわせて選んでください。また、現地を見学して立地条件や設備管理を確認しておくのが大切。お墓参りしやすい立地で設備環境が整っている樹木葬なら、家族から理解を得やすいでしょう。
樹木葬の申し込みと埋葬の流れ
樹木葬の申し込みの流れ
1.樹木葬がある霊園・寺院の情報を集める
インターネットやパンフレット、資料などで情報を集め、気になる霊園・寺院を探します。
2.霊園・寺院の現地見学をする
霊園・寺院を現地見学し、交通アクセスや管理状況、雰囲気などを確認します。
3.樹木葬の契約を申し込む
霊園・寺院に契約を申し込み、あわせて費用を納めます。
4.使用許可証を交付してもらう
霊園・寺院側の入金確認後、使用許可証が発行され、樹木葬が可能になります。
樹木葬の埋葬の流れ
1.死亡届を役所に提出する
死亡届の受理とあわせて、役所から火葬許可証が発行されます。
2.ご遺体を火葬する
火葬許可証を提出して火葬を行うと、火葬場から埋葬許可証が発行されます。
3.樹木葬を行う霊園・寺院に埋葬する
埋葬の当日になったら、霊園・寺院に遺骨と埋葬許可証、使用許可証を持参します。
樹木葬のよくある疑問
Q.樹木葬で遺骨はどのように埋葬しますか?骨壷を使いますか?
樹木葬を依頼する霊園・寺院の埋葬方法によって変わります。
個々に遺骨を埋葬する個別型の樹木葬は、骨壺に遺骨を納めることがほとんど。一方、遺骨を他の人と混ぜる合祀型は、骨壺を使わず遺骨を直接土に還すケースが多いです。
Q.樹木葬はお墓の場所を見失いませんか?目印はありますか?
樹木葬にはシンボルツリーがあり、墓地の区画も整理されているため、お墓を見失う心配はありません。ただ、自然環境によって樹木や見た目の印象が変わる可能性はあります。
Q.樹木葬はどんな場所でも行えますか?場所の条件はありますか?
樹木葬は決められた場所でしか行えません。埋葬方法は墓地・埋葬等に関する法律で定められており、埋葬には市町村長の許可が必要です。
許可がないと私有地でも法律違反になるため、樹木葬のある霊園・寺院を探しましょう。
Q.樹木葬墓地を購入する場合、先祖代々のお墓はどうしますか?
先祖代々のお墓は、購入にあわせて樹木葬や永代供養墓に移す方が多いです。菩提寺に永代供養墓があればそこに、菩提寺になければ他の墓地に改葬します。
Q.樹木葬墓地は生前購入がお得ですか?相続税対策になりますか?
お墓の購入費用は相続税控除の対象にならないため、生前に購入しておくことで節税できます。お墓の継承は相続税の課税対象外ですし、樹木葬墓地の生前購入は相続税対策になるといえるでしょう。
霊園・寺院によっては、名義変更に手数料がかかるため、事前に確認しておいてください。
樹木葬をお探しの方は「いいお墓」へ
樹木葬は、比較的新しいお墓の種類で、一般墓と埋葬形式が大きく違います。ご自身が納得した埋葬方法や場所を選ぶのはもちろん、周囲としっかり相談したうえで準備を進めるのが、トラブルのない樹木葬への近道です。
後悔のない樹木葬を選ぶためには、事前の情報収集が欠かせません。条件にあう樹木葬が見つかったら必ず現地見学し、複数の樹木葬を比較・検討しましょう。
「いいお墓」では、樹木葬を扱っている全国各地の霊園・寺院を無料でご案内しています。経験豊富なスタッフがお客様のニーズをヒアリングし、最適な樹木葬をご提案しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


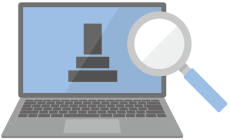
 かんたん
かんたん