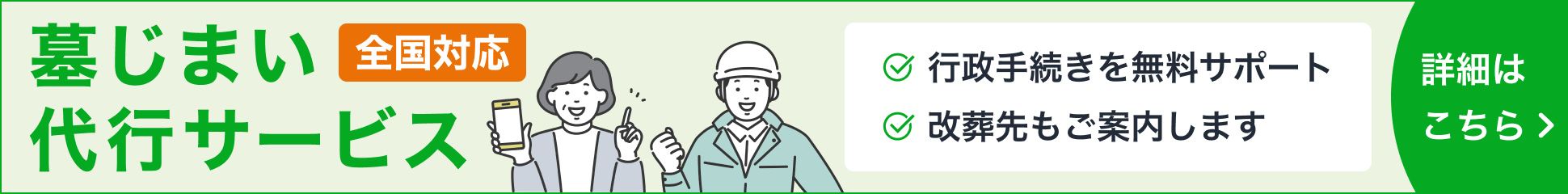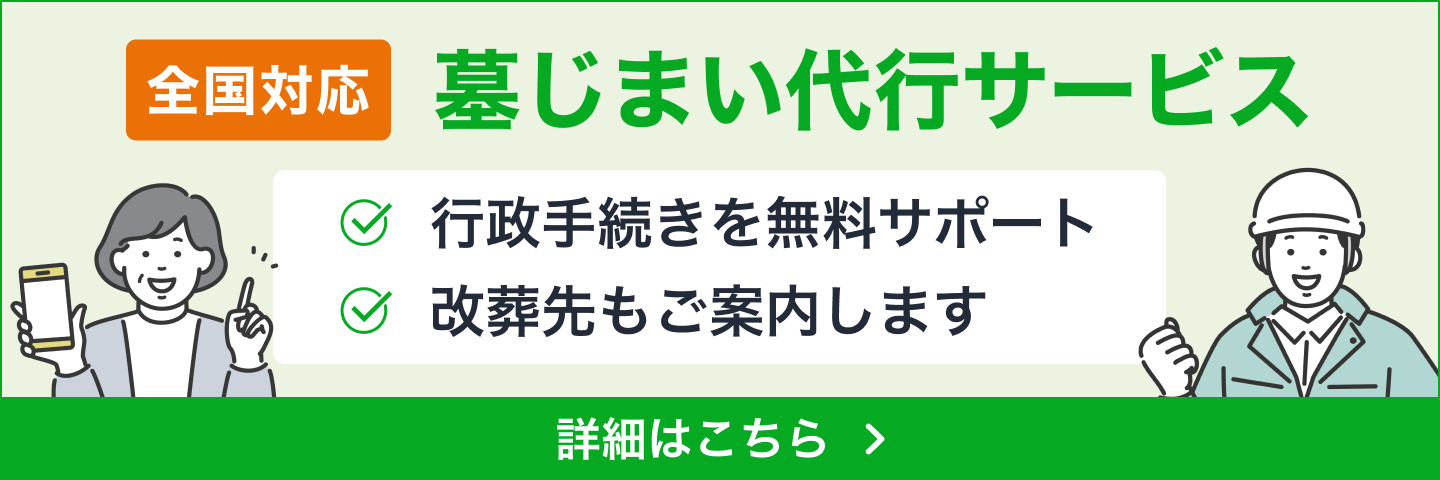改葬とは、今あるお墓から遺骨を取り出して、別のお墓に移動させること。いわゆる「お墓の引越し」です。 核家族化や少子高齢化が進む現代では、住まいからお墓が遠かったり、継承者がいなくなったりして改葬を選択する方が増えています。
この記事では、改葬が急増している理由や改葬の手順、改葬に必要な費用、改葬の方法、改葬によるトラブルと対応策などを紹介します。
改葬(かいそう)とは?いわゆるお墓の引越し
改葬(かいそう)とは、今あるお墓からすでに埋葬されているご遺骨を取り出し、所定の手続きを踏んで、一般墓・永代供養墓・納骨堂・樹木葬など別のお墓に移動させること。いわゆる「お墓の引越し」のことをいいます。お墓を継ぐ人がいない、故郷から離れて暮らしていてなかなかお墓参りできないなどの事情により、改葬を選ぶ人が多いようです。
お墓を継ぐ人がいなくなると最終的にお墓は撤去され、ご遺骨は合祀墓に納められます。合祀墓とは、不特定多数のご遺骨をまとめて埋葬するお墓。一度合祀されると特定のご遺骨を取り出せなくなるため、改葬について事前に考えておく必要があります。
改葬するには、今あるお墓の管理者(寺院・霊園など)の同意を得て、「埋蔵証明書」を発行してもらいます。また、改葬先のお墓を決めて「受入証明書」を受け取ります。そして、「改葬許可申請書」を「埋蔵証明書」「受入証明書」と共に管轄の役所に提出し、「改葬許可証」を交付してもらうのが一般的な流れです。また、既存のお墓で行う閉眼供養(魂抜き)や改葬先のお墓で行う納骨式、開眼供養(魂入れ)など、改葬には必要な手順があります。土葬されているご遺体を改葬するときは、火葬が必要です。
改葬が増えている理由

厚生労働省の「令和5年度衛生行政報告例」によると、改葬の件数は近年大きく伸びています。2023年度(令和5年度)は全国で16万6,886件の墓じまいがありました。また、継承されないお墓・無縁墓を行政が撤去した件数は、全国で3,651件です。核家族化や都市部への人口流入を背景に、改葬を行う人はこれからも増えていくと考えられます。
改葬が急増する理由は、大きく2つあります。
1つ目は、お墓とお住まいが遠く、お墓参りが難しいパターン。お墓の近くにあるご実家からお住まいを転居し、お墓へのアクセスが悪くなったため、お墓参りが困難となり、現在のお住まいの近くにあるお墓に引越しするケースです。若いころは多少遠方のお墓でもお墓参りできたものの、年齢とともに赴くのが億劫になったり、車の運転に不安を感じたりと、高齢化によりお墓参りしにくくなる方もいらっしゃいます。また、生前にお墓を建て、納骨しないままお墓を改葬するケースもあるようです。
2つ目は、少子高齢化によりお墓の継承者が途絶えてしまうパターンです。近年、少子高齢化によりお墓を管理する継承者がいない、または、子どもはいるがお墓を継ぐ負担をかけたくない方が増えています。この場合、代々継いでいく従来型の一般墓ではなく、継承者が不要な永代供養墓や納骨堂、樹木葬など新しい埋葬方法のお墓に引越しをする方が多いです。
改葬と墓じまいの違い

改葬とは、今あるお墓から遺骨を取り出し、新しいお墓に移動させること。墓じまいは、お墓を撤去・処分して墓所を更地にし、土地の使用権を墓地管理者に返還することです。
墓じまいと改葬は、基本的にセットで行われます。墓じまいで取り出した遺骨は、必ず新しい納骨先に改葬しなければなりません。改葬の手順の一部に、墓じまいが含まれていると考えましょう。
改葬にかかる費用の相場と内訳

改葬にかかる費用は、今あるお墓の大きさや立地、地域、改葬先のお墓の大きさ、形態などによって異なります。費用の内訳は「お墓の撤去に関する費用」「行政手続きに関する費用」「新しい納骨先に関する費用」の3つです。
お墓の撤去に関する費用
お墓の撤去(=墓じまい)に関する費用の相場は、30万円〜50万円。墓石撤去・区画整理やご遺骨の取り出し、墓石の運搬などにかかる費用が含まれています。また、閉眼法要をする場合は、お布施も用意しなければなりません。
ただ実際には、お墓の大きさや立地、遺骨の数などで金額が変わるので注意が必要。たとえば3㎡の区画で、ご遺骨が4名様納められているお墓を改葬すると、およそ80万円くらい必要になります。さらにクレーン車が入れない場所は、すべて手作業でお墓の撤去・現状復帰をするため、人件費が上乗せされます。あらかじめ業者に現地調査をしてもらい、正確な見積りを取っておくのがおすすめです。
行政手続きに関する費用
行政手続きに関する費用の相場は、数百円〜1,000円ほど。改葬許可申請に必要な書類を取得するときにかかる手数料で、自治体や墓地管理者によって金額が変わります。
新しい納骨先に関する費用
新しい納骨先に関する費用の相場は30万円〜100万円ですが、改葬先のお墓によって金額が異なります。
たとえば、永代供養墓や納骨堂、樹木葬など、墓石のないお墓に改葬する場合は、石材費の負担がかりません。そのため一般的なお墓と比べると費用をおさえやすいです。また、墓石だけでなく墓所も不要となる散骨や手元供養は、より費用の負担を減らせます。
主な改葬の方法
- ご遺骨だけを改葬する
- ご遺骨と墓石を改葬する
- ご遺骨の一部を改葬する
- 複数あるご遺骨の一部を改葬する
- 無縁墓を合祀墓に改葬する
改葬で移動できるのは、基本的にご遺骨と墓石だけ。納骨棺や外柵は移動できない場合がほとんどです。また、継承者が途絶えて無縁墓となったお墓を改葬するパターンもあります。
ここでは、お墓の改葬方法について説明します。
1.ご遺骨だけを改葬する
もっとも一般的なのは、ご遺骨だけを改葬する方法です。ご遺骨だけを改葬する場合は、今あるお墓の墓石を撤去し、墓所を更地に戻します。改葬先では、新しくお墓を新設します。
2.ご遺骨と墓石を改葬する
ご遺骨と今あるお墓の墓石を一緒に改葬する方法もあります。
ご遺骨と墓石を改葬する場合は、墓石があった土地は更地に戻し、墓石だけを移動します。そのため、墓石を改葬先まで運搬する工賃が必要。墓石は重量があるので、配送業者に依頼すると想定より費用がかかるかもしれません。また、先祖代々のお墓だと墓石が古く、崩れやすい状態になっています。さらに、今ある墓石が改葬先の墓所の大きさと合わないときは、墓石の加工作業が必要です。
墓石を改葬するときは、墓石の重量や状態、改葬先の墓所によって費用が変わるため、複数の業者に見積りを依頼して、比較検討することをおすすめします。その他、改葬先によっては、今ある墓石の移設受け入れができないかもしれません。墓石を移設したい方は、墓石の持込みが可能な区画か、改葬先の管理者に確認しておいてください。
3.ご遺骨の一部を改葬する(分骨)
今あるお墓からご遺骨の一部を取り出して改葬する方法です。故人のご遺骨を複数の場所で埋葬・供養する方法で、「分骨」と呼ばれています。取り出したご遺骨は改葬先に移動させ、残されたご遺骨はそのまま、現在あるお墓に納骨しておきます。
4.複数あるご遺骨の一部を改葬する
先祖代々のお墓には、複数のご先祖様のご遺骨が納められているのが一般的。複数あるご遺骨のうち、一部の人のご遺骨を新しい改葬先に移動させる方法もあります。複数あるご遺骨の一部を改葬するときは、今あるお墓に残しておくご遺骨と、改葬先に移動するご遺骨を分けます。個人単位で遺骨を分ける「分骨」とは別の埋葬方法です。
昨今、従来型の一般墓から、継承者が不要な永代供養付の永代供養墓や納骨堂、樹木葬などに改葬する方が増えています。お墓の埋葬方法が変わる場合、一般的な改葬の手順が異なるかもしれないため、改葬先の管理者に確認してください。
5.無縁墓を合祀墓に改葬する
ここまで紹介した4つとは別に、無縁墓になったお墓を改葬するパターンもあります。無縁墓とは、後継者がいなくなって維持・管理されなくなったお墓のこと。無縁墓になると、行政によってお墓が撤去され、ご遺骨は永代供養墓や合祀墓に改葬されます。
改葬の手順と流れ
- 親族と話し合う
- 改葬元から「埋蔵証明書」を受け取る
- 改葬先から「受入証明書」を受け取る
- 「改葬許可申請書」を入手・記入する
- 「改葬許可証」の交付申請をする
- ご遺骨を取り出す
- 改葬先のお墓に納骨する
改葬するには、今あるお墓の管理者(霊園・寺院など)の同意が必要です。また、改葬先が決まっている場合は、改葬先の管理者と情報共有しておかなければなりません。ここでは、改葬の一般的な手順と流れを説明します。
1.周囲と相談する
まずは家族・親族と話し合い、改葬の同意を得ておきましょう。また、改葬先のお墓の場所や種類、埋葬方法なども相談しておいてください。親族全員が納得したうえで改葬することで、無用なトラブルを避けられます。
2.改葬元から「埋蔵証明書」を受け取る
霊園・寺院など、現在のお墓の管理者に改葬を申し出て、承諾をもらいます。可能なら、正式に改葬を申し出る前に管理者に相談して、あらかじめ合意を得ておくのがおすすめ。これまでお墓を守り、ご遺骨を供養していただいた霊園・寺院の管理者に感謝を伝え、改葬する理由を丁寧に説明しましょう。
そして、管理者の署名・捺印のある「埋蔵証明書」を受け取ってください。埋蔵証明書は、基本的にお墓に埋葬されている人数分の枚数が必要です。昔からあるお墓は、ご遺骨の確認作業や進捗によって埋蔵証明書の取得に時間と費用がかかります。
3.改葬先から「受入証明書」を受け取る
候補地を複数見学をして改葬先を決定したら、永代使用料(土地の使用権利を得るための費用)と管理料を支払います。お墓の完成予定日を決定し、工事の契約をしてください。また、今あるお墓の撤去工事をする前に閉眼供養(魂抜き)を行うので、その手配も済ませます。また、改葬先の管理者に「受入証明書」を忘れず発行してもらいましょう。
4.「改葬許可申請書」を入手・記入する
現在のお墓がある市区町村役場で「改葬許可申請書」の用紙を取得し、必要事項を記入します。書類の形式は市区町村によって異なるので、場所を間違えないようにしてください。改葬許可申請書は、戸籍課などで配布されています。最近では、ホームページの「申請・届出サービス」のページからダウンロードできる役場もあるようです。
「改葬許可申請書」の記入内容
各自治体から「改葬許可申請書」を取り寄せたら、その書類に必要事項を書き込みます。記入内容は形式によって多少異なりますが、一般的には次のような項目です。事前に確認しておくとスムーズに進められるでしょう。
- 故人の本籍・住所・氏名・性別
- 死亡年月日
- 現在埋葬されている所在地・名称
- 改葬先の所在地・名称
- 申請者(墓地名義人と違う場合、承諾書や委任状が求められる)
5.「改葬許可証」の交付申請をする
ご遺骨を取り出すためには、「改葬許可証」が必要です。現在のお墓がある市区町村役場に、捺印済みの「埋蔵証明書」「改葬許可申請書」「受入証明書」を提出すると、改葬許可証が発行されます。改葬許可証は発行に時間がかかることがあるので、余裕をもって手続きしてください。
6.ご遺骨を取り出す
現在のお墓がある霊園・寺院の管理者に「改葬許可証」を提示します。そして、閉眼供養と呼ばれるお墓から魂を抜く供養をした後、お墓に納められたご遺骨を取り出します。なお改葬許可証は、改葬先の管理者にお渡しするので、手元に用意しておきましょう。
7.改葬先のお墓に納骨する
移転先のお墓の霊園・寺院の管理者に「改葬許可証」をお渡しします。それから、開眼供養と呼ばれるお墓に魂を入れる儀式をした後、ご遺骨を納骨して改葬(お墓の引越し)は終了です。
改葬先によっては、「墓地使用許可書」や「埋葬届」などが求められるかもしれません。改葬先で必要となる書類を、あらかじめ確かめておくと安心です。
改葬のメリット
- お墓の継承者の問題が解決する
- お墓参りの負担を減らせる
- お墓の管理料をおさえられる
お墓の継承者の問題が解決する
少子高齢化や核家族化が進む現代では、お墓の継承は大きな問題のひとつです。お墓の継承者がいないと、先祖代々のお墓は無縁墓となり、撤去されてしまいます。
ですが、新しい改葬先に永代供養付のお墓を選べば、無縁墓になる心配はありません。万が一継承者が途絶えても、お墓を維持・管理してもらえるので、安心して眠れます。永代供養付のお墓には、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などの新しい埋葬タイプのお墓の他、永代供養付の一般墓もあります。
お墓参りの負担を減らせる
遠方にあるお墓を、住まいに近い地域の霊園・寺院に改葬するご家庭が増えています。
住まいの近くにお墓を改葬すれば、お墓参りに行きやすくなり、ご先祖様に手を合わせられる回数も多くなります。またアクセスしやすいぶん、自分の死後も親族や子どもが頻繁にお墓参りに来てくれるかもしれません。
お墓の管理料をおさえられる
霊園・寺院にあるお墓は、維持・管理のための管理料がかかるのが一般的です。管理料は年単位で支払うため、お墓がある間は継続的に費用がかかります。
ただ、改葬先に管理料がかからないお墓を選べば、費用の負担をおさえやすいです。たとえば永代供養付のお墓は、契約時に支払う料金に管理料が含まれている霊園・寺院が多く、継続的な出費がなくなります。
改葬のデメリット
- 改葬の費用がかかる
- 手続きや申請に手間がかかる
- トラブルが起きる可能性がある
改葬の費用がかかる
改葬では、今あるお墓を撤去して、ご遺骨を改葬先に移します。そのため、既存のお墓の撤去費用や工事費用、改葬先のお墓の購入費用などがかかります。改葬後の出費は、お墓の選び方次第で減らせますが、ある程度の予算を確保しておきましょう。
手続きや申請に手間がかかる
改葬では、今あるお墓の管理者である霊園・寺院の同意を得たり、書類を取り寄せて申請したりする必要があります。手続きには時間も手間もかかるため、余裕を持った行動をするのが大切です。
また、改葬手続きは、改葬先のお墓を管理する石材店が代行してくれることもあります。なかなか時間を作れない場合は、一度相談してみるのがおすすめです。
トラブルが起きる可能性がある
先祖代々のお墓は、家族だけでなく、一族全体にとって大切な場所です。そのため、周囲と相談せず独断で改葬を進めてしまうと、周囲の反感を買うかもしれません。
また、今あるお墓が寺院にある場合は、檀家をやめて改葬するため、僧侶と揉める可能性があります。その他、改葬を依頼する石材店とトラブルになった事例もあるので、注意が必要です。
改葬でよくあるトラブルと対応策
改葬は関係する人の幅が広く、進め方によってはトラブルが発生しやすいです。無用なトラブルを防ぐためには、事前に具体的な事例を把握し、対応策を練っておく必要があります。
寺院とのトラブル
移転元のお寺の住職が改葬に同意してくれない
改葬を決めるのはあくまでも墓地使用権者で、お寺の住職は正当な理由なしに改葬を拒否できません。また、改葬で離檀するにあたって、寺院から高額な離檀料を請求される事例があるようですが、離檀料に法的な根拠はないのです。
移転元の寺院と行き違いが起きないよう、改葬を考え始めた段階で住職に相談しておきましょう。前触れなく、いきなり「お墓を移します」と宣言するのは、角が立ちやすいです。改葬したい理由を丁寧に説明し、住職に理解してもらう必要があります。そして、実際に改葬をするときは閉眼法要をお願いし、長年お世話になったお礼としてお布施を渡してください。
お寺に墓地を返還しても永代使用料は返してもらえない
永代使用料とは、お墓の土地使用権を得るための費用で、契約時に支払います。ただ永代使用料は、墓地の使用規則に「理由の如何を問わず返納はしないものとする」といった記述がされている場合が多いです。墓地を返還しても、永代使用料が返還されることはまずないといって良いでしょう。
親族とのトラブル
改葬は本来、墓地の使用権者が決定できるため、親族の承諾を得る必要はありません。ただし、周囲の承諾なしに改葬をすると、お墓に対する思いや墓地の使用権からトラブルに発展するかもしれないので注意が必要。親族の賛同を得ておいた方が、スムーズに改葬を進められます。
親族とのトラブルを避けるためには、事前に丁寧な説明と相談をするのが大切。お墓は一族がご先祖様に手を合わせる場所で、永代に渡って維持が必要です。親族全員が納得して改葬できるよう心掛けてください。
石材店とのトラブル
墓石の撤去や墓所の整地、新しいお墓の設置などの工事は、石材店に依頼するのが一般的です。工事にかかる費用やサービス内容は石材店によって違うため、安易に選ぶと後悔するかもしれません。また、高額な工事費を請求したり、墓石の扱いが雑だったりする悪質業者もあるようです。
石材店とのトラブルを避けるには、複数の業者から見積もりを取って比較検討するのが一番です。比較することで費用感をつかめますし、より条件に合った石材店を選択できます。
改葬の法要にかかる費用とマナー
改葬の法要のマナー
改葬の法要では、男女ともに落ち着いた服装が求められます。男性は黒のスーツに控えめな色のネクタイが基本。女性は黒や紺のスーツ・ワンピース・アンサンブルなどを選び、華やかなアクセサリーは避けます。靴も簡素で上品なものを用意してください。
また、改葬後は、日がたたないうちに親族縁者に対して「挨拶状」を送ります。
開眼供養のお布施の費用相場
改葬では、改葬先のお墓に納骨するとき、僧侶にお越しいただいて開眼供養を行います。
開眼供養で僧侶にお渡しするお布施の相場は3万円〜5万円です。お布施は白無地の封筒に包み、表書きには「御布施」「御入魂御礼」「開眼供要御礼」などと書きます。別途御車料や御膳料が必要な場合は、1万円~3万円ほど用意しておくとよいでしょう。
土葬からの改葬は閉眼供養
土葬から改葬する場合は、ご遺骨を取り出す前に閉眼供養を行います。取り出したご遺骨は、洗骨作業してから火葬し、骨壷に納めます。「改葬許可証」を取得するのと同時に、「火葬許可証」も申請するとスムーズです。土葬だと改葬が一般的な方法と異なるため、専門の業者を探す必要があります。
いいお墓の墓じまい
墓じまい(改葬)は完了するまでの手続きも多く、必要な費用も不透明なところが多いのが実態です。