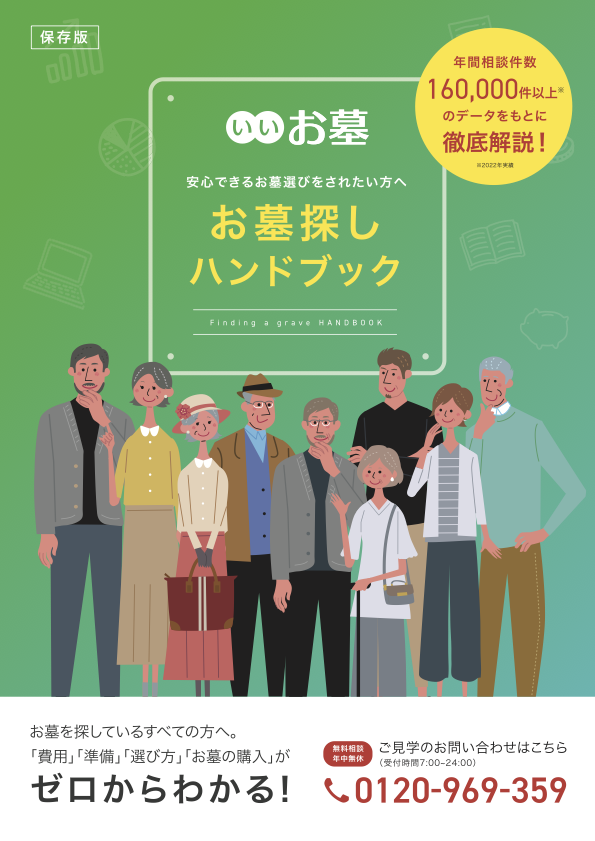分骨とは、故人の遺骨を2ヵ所以上に分けて埋葬、供養することをいいます。通常の埋葬では分骨を行うことはありませんが、近年、手元供養のために分骨を行う人が増えています。
分骨は法律的には問題ありません。また、分骨することは良くないと思われがちですが、古来から行われてきた習慣です。遺された方々の心の支えや励みとなる、とても尊いものであり、お釈迦さまの遺骨も分骨という形で納められています。
ここでは、分骨についての解説や分骨の方法、分骨したお骨の供養方法などを解説します。
分骨とは
分骨とは、故人の遺骨を2ヵ所以上に分けて埋葬、供養することをいいます。
分骨を考えられる人は以下のような理由から分骨を考えるようです。
- お墓が遠方にあり、お墓参りがままならない
- 宗派の本山に遺骨を納めたい
- 親族で遺骨を分けたい
- 納骨する遺骨とは別に手元供養をしたい
分骨をする際に手続きは必要になりますが、改葬のようにお墓や遺骨をすべて移すわけではないため、手続きは比較的簡単です。
ただし遺骨の所有権は、基本的には「祭祀を主催する生存者」になります。それぞれの墓地・墓所に氏名が提出されている形となるので、その所有権者の承諾を得ない限り、分骨を勝手に行うことはできません。
分骨の方法
分骨は大きく2つの方法に分けられます。
既にお墓に埋葬してある遺骨の一部を分骨する方法
お墓の管理者に分骨の意向を伝え「分骨証明書」を発行してもらい、その「分骨証明書」を新たに埋葬する先の墓地管理者に提出します。
遺骨を移動する前には、僧侶に分骨をするための法要を執り行ってもらい、その後に遺骨を取り出すようにします。
火葬場で分骨を行う方法
火葬を行う際に、火葬場の管理者に分骨の旨を話し、「火葬証明書」(火葬のために必要な「火葬許可証」とは別のものです)を発行してもらいます。
平成11年の「墓地、埋葬に関する法律」の改正により、火葬場で発行する「火葬許可証」を埋葬先の墓地管理者に提出すれば、分骨ができるようになりました。受け入れ先の墓地との手続きがスムーズにいくように、空欄の部分に分骨のために発行したということを、火葬場の管理者に一筆添えてもらうとよいでしょう。
葬儀社にも分骨することを事前に伝えておけば、火葬の際、分骨用の小さな骨壺を用意してもらえます。遺骨は骨上げの時に移すようにします。分骨も、骨を納める時には、僧侶にお願いして法要を行います。

分骨を行う際の注意点
- 遺骨の取り扱いに関しては、親族の中でも遺骨の所有権限を持っている方に許諾を得る必要があります。勝手に分骨を行うことはトラブルとなりますので注意しましょう。
- 分骨に関して快く思わない人ももちろんいます。分骨を希望する場合は、あらかじめ意向を伝えておくとよいでしょう。他の親族への配慮も忘れずに。
- 各宗派の本寺で供養を考えている方は本山での埋葬方法をあらかじめ確認しておきましょう。本山納骨では合祀して供養するのが一般的です。合祀となるとお骨を取り出すことができなくなりますので注意が必要です。
手元供養とは?
分骨した遺骨を保管する方法として、お墓に納骨する以外に自宅で保管する方法があります。このような保管方法は手元供養とも呼ばれ、最近増えてきています。
手元供養のため分骨し、保管することに法律上の問題はありません。いつでも身近に故人を感じることができ、広まりをみせています。
こんな方法で手元供養ができます!
- 骨壺・ミニ骨壺
- ペンダント
- ブレスレット
- ブローチ
- ミニ仏壇・ステージ・飾り台
- オブジェ
- 宅墓
残った遺骨の納骨先は?
- お墓
すでにお墓のある人は一部を手元供養、残りをお墓へ納骨します。
火葬場で分骨する時は、分骨証明書または火葬証明書(分骨用)等の書類を受け取っておきましょう。今後、手元供養していた遺骨をお墓へ納骨する必要が生じた場合に必要となるからです。 - 散骨
海や山など、自然の中に遺骨を散骨するケースも増えてきています。散骨と手元供養と併用することで「散骨によって身近に手を合わす場所がなくなる」といった不安を回避できることも増えている理由のようです。 - 樹木葬
墓石の代わりに樹木を目印とした、自然が感じられるお墓の一種です。「自然に還りたい」という願いの叶う葬法で、近年注目を集めています。 - 納骨堂
個人や家族で遺骨を安置できる施設です。恒久的に遺骨を祭祀する施設としての役割も担うことが多くなり、選ぶ人が増えています。 - 合祀・合葬
見知らぬ多くの人たちの遺骨と一緒に埋葬します。費用は抑えられますが、お骨を取り出すことができなくなるため注意が必要です。


まとめ
手元供養が広まってきた近年、分骨は意外と身近なものになってきています。
さまざまな理由で分骨を行うことがあると思いますが、分骨は自分だけで決められるものではありません。親族間でも考え方の違いはあります。他の親族への配慮も必ずしましょう。
とはいえ、まだまだよく知られていない分骨。周囲へ相談できずに悩んでいる人はぜひいいお墓へご相談ください。


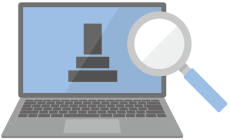
 かんたん
かんたん