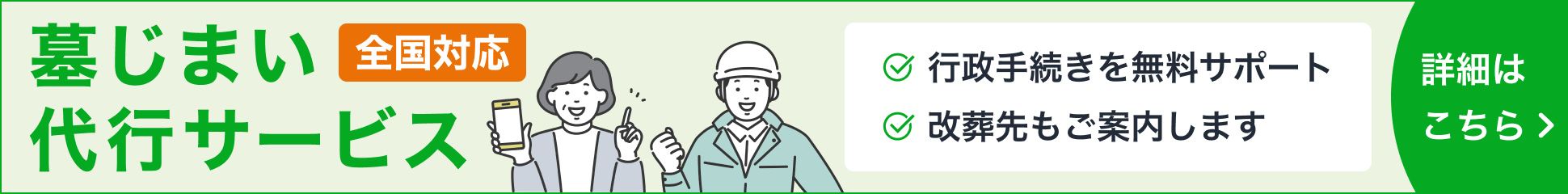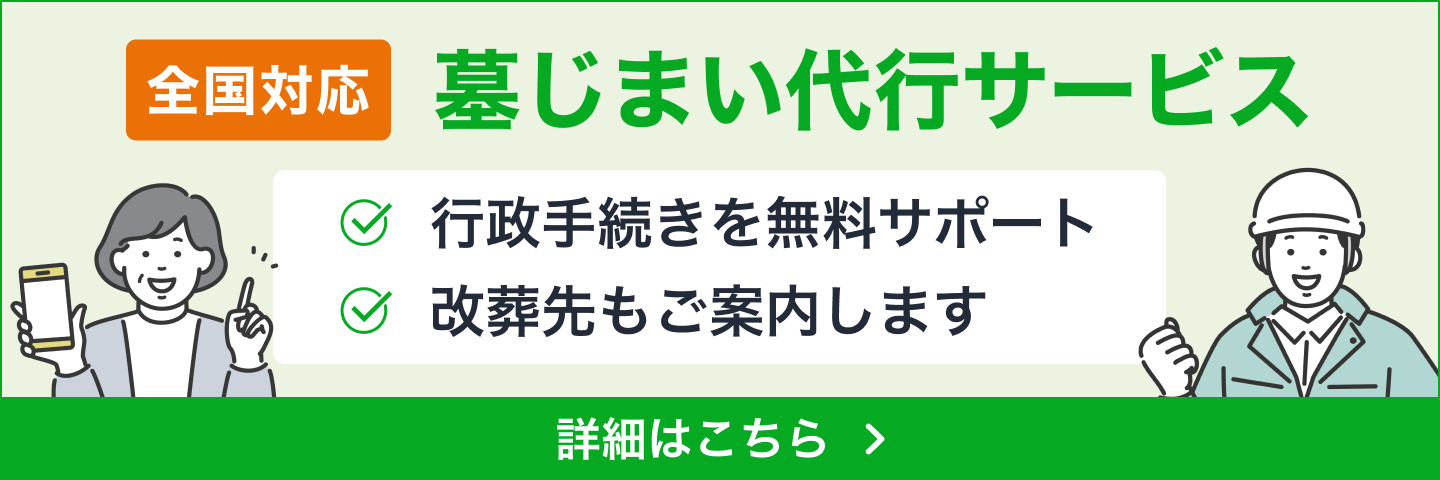近年、墓じまいを行う人が増えてきています。墓じまいで閉眼供養をする際には、僧侶に読経していただきますが、そのとき僧侶にお渡しするお布施はどうすれば良いのか気になっていませんか?
この記事では、墓じまいの際に僧侶にお渡しするお布施の相場金額、お布施を準備する時のマナー、お布施をお渡しする時のマナーなど、墓じまいのお布施事情について解説をします。
お布施以外にも必要な費用がありますので、あわせてご紹介していきます。
墓じまいのお布施の相場
墓じまいのお布施はいくらくらいお包みするのが一般的なのでしょうか。お布施はお寺との関係性や目的によって金額が変わります。ここでは、お布施の相場を目的別にご紹介します。
| お布施の項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 閉眼供養 | 3万円~10万円 |
| 開眼供養 | 5,000円~1万円 |
| お布施に付随する費用 | 1万円~2万円 |
閉眼供養
お墓を撤去しご遺骨を取り出す前に、お墓の閉眼供養を行います。手を合わせる対象だったお墓から魂を抜くための供養です。この時、僧侶にお布施をお渡しするのが通例となっています。
お付き合いのあるお寺の場合は3万円~10万円程度が相場です。ただし、お寺の檀家になっている場合は、離檀料も発生します。離檀料については後ほど説明しますが、閉眼供養のお布施と離檀料を合わせて総合的に金額を判断する必要があります。
寺院墓地ではなく、公営霊園や民営霊園のお墓をお持ちである場合、どこのお寺や僧侶に閉眼供養をお願いをしたらよいのかが分からないという方もいらっしゃるでしょう。そういった時、インターネットで僧侶を手配するという方法があります。単発で依頼する場合に支払うお布施は、3万円~5万円程度が相場であるといえるでしょう。
開眼供養
墓じまい後にご遺骨を新しい納骨先に納める際、開眼供養をします。お墓に魂を入れる供養です。閉眼供養の時と同様、供養を行ってくれる僧侶にお布施をお渡ししますが、納骨先によって事情が異なります。
寺院墓地の個人墓の場合、5,000円~1万円程度が相場であるといわれています。公営霊園や民営霊園の場合は開眼供養をしないこともあります。開眼供養をしない場合はお布施も不要です。
合祀や散骨の場合は開眼供養が不要であることが多いです。ただし、僧侶に読経をしていただく場合は、5,000円~1万円程度のお布施をお渡ししましょう。
お布施に付随する費用
お布施とは別に、費用がかかる場合があります。
交通費として、僧侶に御車代をお渡しするのが一般的なマナーです。相場は5,000円~1万円程度です。ただし、お墓があるお寺で閉眼供養を行う場合、僧侶が交通機関を利用していないので御車代をお渡しする必要はありません。
閉眼供養後に会食があり、僧侶が会食に参加しなかった場合はお食事代として御膳料をお渡しします。相場は5,000円~1万円程度です。会食に参加した場合、御膳陵料は不要です。
墓じまいにかかる離檀料とは
寺院墓地などで檀家としてお寺にお墓を管理してもらっていた場合、墓じまいを契機に檀家を抜ける(離檀する)ことになります。その際に「今までお世話になりました」という感謝の意味を込めてお寺に支払うお金が離檀料です。
離檀料の相場は数万円から、場合によっては数十万円というところもあります。離檀料に法的根拠はなく、感謝の気持ちとして差し出す金銭なので、お寺との関係性によって金額は異なります。
墓じまい後の永代使用料返還について
お墓をお求めになった際に、お墓が建つ土地の永代使用料(土地を使用する権料)を支払っているかと思います。
墓じまいをする時に、この永代使用料が返還されるか否かについては、それぞれの寺院や霊園によって異なります。通常、永代使用料が返還されない場合が多いですが、契約内容によっては永代使用料が返還されるケースもあるようです。
墓じまいを行う際には、永代使用料に関する記述を契約書で確認してみることが必要でしょう。
墓じまいでお布施を準備する際のマナー
お布施を用意する際のマナーについてまとめました。
不祝儀袋で包む
お布施は不祝儀袋で包みます。不祝儀袋とは、葬儀や法要などの弔事の際に現金を包んでお渡しするための封筒です。コンビニや100円ショップなどで売っているもので問題はありません。不祝儀袋が用意できない場合は白い封筒でもよいですが、郵便番号が印刷されていないものを選びましょう。
表書きは「御布施」にする
表書きは、封筒の上段中央に「御布施」と書きましょう。すでに「御布施」が表書きとして印字されている場合はそのままご使用ください。
「御布施」の下には差出人の個人名(フルネーム)ないしは「○○家」と書きます。使用する筆は、悲しみの涙で墨が薄れるとして薄墨で書きます。
お札は肖像画を表側かつ上向きにして入れる
お札は、肖像画を表側かつ上向きになるように袋に入れます。葬儀などの香典の場合は、不幸に対してあらかじめ準備していた印象を与えるので新札は避けるべきですが、墓じまいの閉眼供養では新札でも古いお札でも構いません。ただし、汚れているお札は避けるようにしましょう。
裏書も忘れずに
裏書には、お布施の金額、差出人の住所や名前を書きます。中袋がある場合は裏面ではなく中袋に書きましょう。金額は旧字の漢数字を使用します。1万円の場合は「金壱萬円也」となります。
友人や知人は墓じまいの香典は不要
故人の友人や知人として墓じまいに立ち会う場合、香典は不要です。
ただし、墓じまいの後に改葬(お墓のお引越し)をする場合、建碑祝いは祝儀袋を使って用意するのがマナーです。
まだお墓が建っていない場合、改葬式や納骨式が行われた時は、不祝儀袋を使って金銭をお包みします。表書きは「御仏前」ないしは「お供え」としましょう。
墓じまいでお布施を渡す際のマナー
お布施を僧侶にお渡しするタイミングや方法について紹介します。
供養の前後に渡す
お布施を渡すタイミングは、儀式の途中など僧侶の忙しいときは避け、供養の前後に渡すのが望ましいです。
供養の前に渡す場合は、僧侶がお見えになり挨拶するタイミングで「本日はどうぞよろしくお願いいたします」などとお伝えしながらお渡ししましょう。
供養の後に渡す場合は、読経が終わった後に「本日はお越しいただきありがとうございました。些細ではございますが、こちらは御礼でございます」などとご挨拶をしながらお渡しするのがよいでしょう。
切手盆を使用する
お布施は切手盆(きってぼん)に乗せてお渡しするのがマナーです。切手盆とは冠婚葬祭などで使われる黒塗りのお盆のことを言います。
切手盆に家紋がある場合は、家紋を自分の方に向けて置きます。家紋がない場合はどちら向きでも大丈夫です。切手盆に、自分が文字を読める向きにお布施を置きます。そして、切手盆を180度回転させて、僧侶に読める方向にお布施を向けてお渡しします。
切手盆がない場合は、袱紗(ふくさ)を使用しましょう。袱紗とは、冠婚葬祭で使用する香典やご祝儀を包む布のことです。お布施を袱紗に包んでおき、お渡しする時に袱紗を広げて、切手盆の時と同様の流れで、僧侶にお布施をお渡しします。
墓地のタイプ別にみる、墓じまいの捉え方の違い
墓地のタイプは、「寺院墓地」「公営霊園」「民営霊園」の、大きく3タイプに分けられます。それぞれのタイプにより、墓じまいに対する捉え方が異なることがあります。
寺院墓地
寺院墓地は、お寺が管理・運営を行う墓地です。寺院墓地で墓じまいをする際、閉眼供養は必ず必要となってきます。お布施のほか、離檀料をお渡しするのが一般的です。また、状況次第で、御車代や御膳料なども必要になってきます。
公営霊園
公営霊園は、自治体が管理・運営を行う墓地です。閉眼供養は必ず行わなければならないものではありませんが、行っておくのが良いのではないでしょうか。僧侶にお越しいただく場合は、お布施のほか、御車代や御膳料をお渡しする準備をしておく必要があります。
民営霊園
民営霊園は、宗教法人や社団法人から委託された民間企業が管理・運営を行う墓地です。閉眼供養は必須ではありません。ただし、墓じまいをする際に、閉眼供養を行っていないと撤去作業を行う業者に敬遠される可能性があります。そのため、閉眼供養を行っておくことに越したことはありません。僧侶にお越しいただく場合は、お布施のほか、御車代や御膳料をお渡しする準備をしておく必要があります。
墓じまいに参列する際などの服装
墓じまいの閉眼供養を行う際には、僧侶にお越しいただくことになりますので、基本的には喪服を着て参列しましょう。納骨式も同様です。喪服でない場合でも、略式喪服や、ダークカラーの落ち着いた色合いの装いを選びましょう。
お子さまの場合は、学生服ないしは黒や紺の服装を身に着けるようにしましょう。
開眼供養や建碑祝いはお祝いごとなので、喪服を着る必要はありません。ただし、派手な服装を控えるのが無難です。
墓じまい後にご挨拶状を送付
閉眼供養後には、親族、故人の知人や友人の方々にご挨拶状をお送りしましょう。ご挨拶状の内容は、「時候の挨拶」から始まり、「墓じまいをしたお墓の住所や時期」「新しい納骨先(お墓)の住所」「墓じまいをした理由」、そして「結びの言葉」で締めましょう。ご挨拶状は、慌てず発送できるように、閉眼供養を行う前に用意しておくのが良いでしょう。
墓じまいで後悔しないために、事前準備をしっかりしましょう
墓じまいを行うことで、子どもたちへの負担も軽減でき、お墓を無縁墓にする心配もなくなるというメリットがあります。ただしお墓には、納められている方々の魂が宿っているので、撤去前には閉眼供養を行い、亡き人の魂を抜く必要があります。また、新しいお墓に納骨をする場合、お墓に魂を入れる開眼供養を行います。閉眼供養、開眼供養の際は僧侶に読経してもらうため、お布施をお渡しするのが通例です。
お布施以外に御車代や御膳料、そのほか不随する費用が必要になる場合もあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
墓じまいについて分からないことは多くあると思います。スムーズに墓じまいができるよう事前準備はしっかりしておきたいものです。
いいお墓の墓じまい
墓じまい(改葬)は完了するまでの手続きも多く、必要な費用も不透明なところが多いのが実態です。