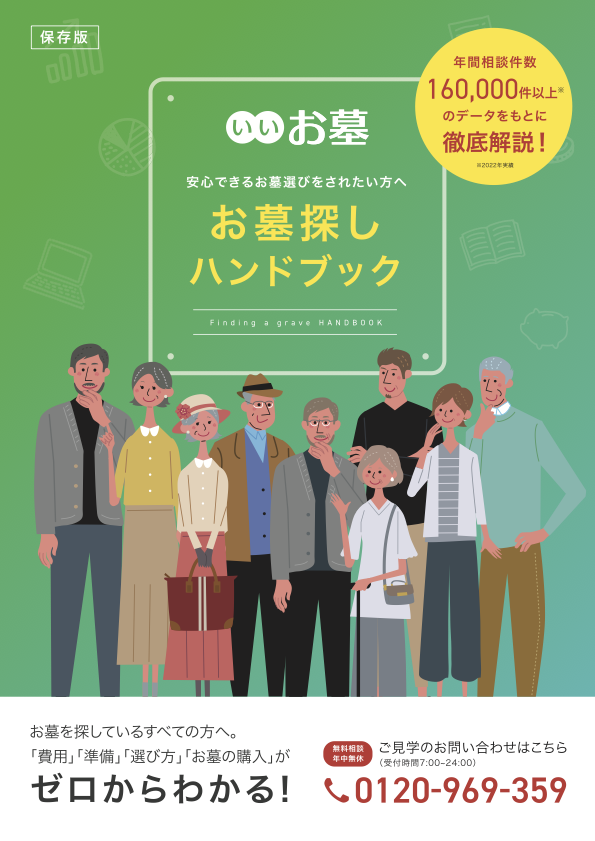寺院墓地(じいんぼち)とは、各宗派のお寺によって管理・運営されている墓地のことです。
お寺との繋がりが強いことから、檀家になれば手厚い供養や節目ごとの法要を安心して任せられるのがその他の霊園との違いですが、気になるのは管理費や、そういった費用に関するトラブルです。
ここでは、寺院墓地で永代供養をするための費用や管理費の相場、利用するメリット・デメリットについて解説しています。
寺院墓地とは?/寺院墓地の特徴
寺院墓地とは、お寺の境内または寺院に隣接する敷地に設けられている、お寺が主体となって管理・運営する墓地です。次のような特徴があります。
境内にお墓がある
お寺にお墓があるという光景は、日本人が昔から見てきた、なじみ深い景色ではないでしょうか。このようにお寺とお墓が同じ場所にある墓地が寺院墓地です。寺院墓地の場合、そのほとんどが寺院の敷地内である境内、または寺院に隣接する敷地に設けられています。
寺院が管理・運営を行う
寺院墓地という名前のとおりお墓の管理や運営は寺院が直接行います。寺院が直接運営しているため、葬儀・法要・供養などはすべて寺院に任せておけます。お墓も寺院の敷地内にあることがほとんどなので、管理面での安全性も期待できます。
基本的に檀家のための墓地
寺院墓地は、原則としてそれぞれの寺院の檀家や門徒・信徒のための墓地です。お寺とのつながりが深いというのも、ほかの種類のお墓にはない特徴といえるでしょう。
寺院と檀家の歴史には江戸時代の寺請制度にまでさかのぼります。当時はすべての世帯が特定の寺院に所属することが義務づけられていて、双方はお互いを支えあう存在でした。
特定の寺院の檀家になると、経済的に寺院を援助するかわりに葬祭や供養を専属で優先的に行ってもらえるため、お盆などの繁忙期でも困ることはありません。必ずしも檀家になる必要のない寺院墓地もありますが、寺院と檀家の関係は寺院墓地の大きな特徴のひとつです。
ある特定の寺院に所属している家のこと。浄土宗においては「信徒」、浄土真宗では「門徒」とも呼ばれます。また、寺院墓地に新しくお墓をもつために檀家に入ることを「入檀する」といいます。
仏様と僧侶が身近にいる
寺院墓地はお墓が寺院の境内にあるので、ご本尊と僧侶が常に近くにいます。
常に仏様が近くにいてくださる安心感と、毎日のように聞こえてくる住職さんの読経の声は、お墓に眠るご先祖にも大きな安らぎを与えられるのではないでしょうか。

他にも、法要や供養のことで疑問や困ったことがあれば、面と向かって直接相談できるという利点もあります。
また、法要の際や、不幸があって葬儀を行う場合にも本堂を利用することができるので、一般的な葬儀会場に比べると格式の高い葬儀になります。
寺院墓地の費用相場は?
寺院墓地にかかる費用は、永代使用料・管理料・墓石代があります。そのほか、寺院墓地に特有な入檀やお寺を支えるための費用が必要になることもあります。
絶対に必要な永代使用料
永代使用料は墓地を契約する際に必ずかかる費用で、契約時に一括で支払う場合がほとんどです。
現在の法律では墓地を勝手に造ってお墓を建てることはできないので、お墓を建てるためには霊園や墓地の土地を使用することになります。場所代として永代使用料を支払うことで、使用者や継承者がいる限りその場所を使い続けることができます。
永代使用料の相場は20万円~200万円とかなり幅があり、この幅には不動産と同じように立地条件や選ぶ区画の広さ、寺院の設備の状態などが影響しています。
寺院墓地の運営に必要な管理料
管理料は墓地の運営や共有設備の維持・管理に必要な費用で、だいたい一年に一度支払います。
これも寺院により幅がありますが、相場は6千円~2.5万円程度です。それぞれの寺院の運営方針にもよりますが、寺院墓地の場合、その他の霊園よりも割高に設定されていることが多いようです。寺院施設使用料、お布施や冥加金という名目で納めることもあります。
お墓を建てる墓石代
お墓を建てる際に必要となる墓石代は、選ぶ墓石の種類やデザインで価格も変わります。

入檀料、護持会費、お布施
特徴的な費用として、檀家になるために必要な入檀料、護持会費、お布施などがあります。
- 入檀料
寺院墓地特有の費用です。檀家になる際に支払いますが、寺院によっては入檀料がかからないこともあります。宗派や寺院によって異なりますが、10万円~30万円が相場です。 - 護持会費
お寺を管理維持・運営していくための費用です。年間で定額制にしている寺院もあれば、お布施などそれぞれの檀家の任意としている寺院もあります。またお寺によっては、寺院墓地の管理費を護持会費と呼ぶこともあります。 - お布施
檀家になるとお布施を支払う機会が多くあります。お布施はお礼や感謝の気持ちとして支払うものなので、決まった金額というものはなく、できる範囲でというのが前提です。お通夜や葬儀の読経・供養が15万円~50万円、回忌法要が3万円~10万円、月命日の読経が3千円~1万円がだいたいの目安です。
寺院墓地にかかる費用の相場は、それぞれの寺院によっても大きく異なります。詳しくは墓地を管理・運営する寺院に確認しましょう。
寺院墓地を選んだ時の宗派の制約は?
宗派・宗旨が限定されることがある
寺院墓地では宗派や宗旨が限定されることが多いです。すでに特定の宗派をもっていたり檀家であった場合にも、墓地を管理・運営する寺院の宗派に改宗しなければならない可能性があります。
また、宗派・宗旨不問の場合も、前提として在来仏教徒が条件である場合がほとんどです。仏教徒以外のお墓は建てられないこともありますので注意しましょう。
寺院墓地に多いのは過去の宗派・宗旨不問
「宗派・宗旨不問」の解釈は、寺院によってさまざまです。
寺院墓地において多い解釈は、「過去つまり納骨前の宗派や宗旨は不問だが、納骨後はその寺院の宗派や宗旨にしたがって葬儀・供養を行う」です。そのため、墓地を購入した後はその墓地をもっている寺院の檀家になる必要がある場合が一般的です。
ただし、納骨後も自由に供養できる寺院もあります。寺院墓地だからといって必ずしもその寺院の檀家にならなければいけないわけでもありません。それぞれの寺院によっても運営方針は異なるので、購入前にきちんと確認しましょう。
寺院墓地のメリット・デメリット/公営・民営霊園と比較
メリット
寺院墓地のメリットには、管理・運営の主体が寺院であるが故の安定感が挙げられます。また身近にある寺院の墓地などを選べば、お墓参りも簡単です。
安心感がある
寺院墓地は運営や管理をしている寺院と直接つながりがもてるため、お墓の管理や葬祭、供養をすべて任せられ、相談にものってもらえるというメリットがあります。
また、回忌法要の管理などもお寺がしてくれます。もし忘れてしまっていても安心ですし、檀家はその寺院で法要を執り行うこともできます。
手厚い供養が受けられる
檀家になると住職と直接会話を交わすことも多くなるため、親密な関係を築くことが可能になり、強いつながりと信頼関係がうまれます。そのため供養も手厚く、繁忙期でも優先して供養が受けられます。
もし墓地の継承者がいなくなっても、遺族に代わってお寺が供養してくれる永代供養を受けることも可能です。
一般的には霊園や寺院が遺族に代わって供養・管理をしてくれるお墓という意味で使われています。

立地条件が良い
主に首都圏などの寺院墓地は、比較的アクセスしやすい場所にあることが多いです。寺院墓地は地域に密着していて身近にも多くあるので、お墓参りなどもしやすいといえるでしょう。
デメリット
寺院墓地のデメリットには、他の公営霊園や民営霊園と比較すると自由度が低いといった点が挙げられます。それぞれの寺院によっても異なるので、購入前の準備が大切です。
比較的自由度が低い
宗派の制約でも述べたように宗派や宗旨の限定がある寺院墓地も多く、宗派や宗旨が不問の場合でも、法要はその寺院の宗派や宗旨で行われるのが一般的です。
またお墓を建てる際の墓石は、大きさ、形、デザインに指定や範囲の限定がある場合があります。寺院によっては決められた石材店で墓石を購入しなければならないこともあるので、そうなると好きなように墓石を選ぶことが難しくなります。
費用が比較的割高
その寺院の格式や設備などで異なりますが、お墓を購入する際にかかる永代使用料や毎年支払う管理料が、寺院墓地ではその他の霊園などに比べて割高になることが多いです。
またその寺院の檀家になる場合には、入檀金を納めなければならないこともあり、その他には寺院の管理や維持のための護持会費やお布施、寄付が必要なこともあります。
それぞれの寺院や住職で運営に差がある
寺院墓地は寺院が運営を担っていて、サービスよりも信仰に重きを置く傾向があるので、それぞれの寺院や住職によって運営の方針に差が出ます。
墓地を気に入っても、寺院の運営方針や住職の人柄があまり合わない、という可能性もあります。
寺院墓地の他にはどんなものがあるの?メリット・デメリットの比較
お墓を経営主体ごとに分けると、都道府県や自治体による「公営霊園」と、宗教法人あるいは公益法人による「民営霊園」、そして、宗教法人である寺がその敷地内で運営する「寺院墓地」があります。
公営霊園とは
都道府県・市区町村などの自治体によって管理・運営されています。地方では昔から村落(旧行政村)が運営する「共同墓地」という形態もあります。
- 宗旨・宗派の宗教的制約がない
- 永代使用料や管理料が低めに設定されていることが多い(ただし、都立霊園で一等地にある場合などは民営霊園より高額となる)
- 担当の石材店を自由に選べる
- 自治体など公的機関による管理運営のため安心感がある
- 申し込み条件が定められている(以下は条件例)
・申込者の住所が霊園を管理運営する自治体の管轄にあること
・遺骨があること
・親族に承継者がいること - 募集受付期間が限定されており、応募多数により抽選になることもある
- お墓の形状や大きさが指定されていることがある
- 募集区画がない場合がある

民営霊園とは
民営霊園は、財団法人や社団法人、宗教法人またはそこから運営委託を受けた民間企業によって管理・運営される霊園です。
- 個性的な特色や雰囲気、サービスなど利便性向上のための工夫をしている所が多い
- 申し込み条件は、寺院墓地・公営霊園と比較すると緩め
- お墓のデザインや大きさなどが自由に選択できる
- 担当の石材店(指定石材店)が決められていることが多い
- 価格面において割高になる場合がある

寺院墓地に入るには?
入りたい寺院墓地に申し込む
入りたい寺院墓地を見つけたら、まずは見学を申し込みます。見学をとおして、その寺院のもつ独特な雰囲気や、住職さんの人柄などが合っているか確認することが大切です。
申し込みなどの情報収集手段としては、寺院のホームページから探す方法や、専用の資料がある場合は資料を請求する方法、または墓石を取り扱う石材店に聞いてみるという方法もあります。
基本的に檀家になる
必ずしも檀家になることが条件の寺院墓地だけではありませんが、一般的には入檀が必要な寺院が多いです。したがって、宗派や宗旨を事前に確認しておくことも重要です。
檀家になることで、寺院墓地ならではの恩恵を最大限に受けることができます。
寺院墓地の代表的な例
寺院墓地は、お墓の種類の中でも数が多く、日本全国にさまざまなお墓があります。ここでは代表的な寺院墓地についてご説明します。

お墓といえばお寺、お寺といえばお墓
規模の大小はありますが、寺院墓地はお寺の数と同じくらいに多く点在しています。そのため、寺院墓地を目にする機会も多く、お寺とお墓を連想させてイメージをもっている方も少なくないと思います。
寺院墓地は多くの方がイメージとしてもっているように、いわゆるお墓として身近に存在していて、その数も日本の墓地や霊園では最多です。
世界遺産などの有名寺院も
寺院墓地は文字どおり、寺院の存在なくしては成り立ちません。例えば京都にある、歴史上でも有名な天台宗の総本山である比叡山延暦寺も、墓地をもつ寺院のひとつです。
その他にも京都の嵯峨嵐山にある臨済宗大本山天龍寺や、浄土宗総本山知恩院、真言宗大本山隨心院など、世界遺産に登録されている寺院の中にも、大本山や塔頭で墓地の運営を行っている寺院はあります。
寺院墓地の管理者は?
経営主体は寺院
これまで何度か説明してきたように、寺院墓地の経営や運営は寺院が直接行っています。墓地の開設にあたっては、地方自治体など行政の許可を受けて行っています。墓地をどのように運営していくか、それぞれの寺院でその方針が決められています。
管理者は住職
これまで寺院墓地の管理・運営は寺院が行っていると説明してきましたが、厳密にいうと墓地の管理はその寺院の住職が行います。寺院が直接行っていることにかわりはありませんが、墓地や埋葬などに関する事務管理、使用者の方のケアなどは住職がその役割を担っています。例えばすべての方の回忌法要の管理も含まれているので、そういった細かい管理ができるのも、寺院の住職が直接関係しているからだといえるでしょう。
まとめ
寺院墓地を選ぶ際にポイントとなるのは
- 寺院の宗派や宗旨
- 入檀の条件
- 寺院の規則・運営方針
- 立地条件
- 寺院の雰囲気・住職の人柄
があげられます。
他の霊園と違い、使用者は定期的に寺院に足を運び住職と顔を合わせることが多いので、寺院の雰囲気や住職の人柄が合うかは、特に重要なポイントともいえます。また、寺院や住職と使用者の間にはとても密な関係性があり、お互いの信頼も得られやすいため、より良い供養を安心して受けることができます。
お墓選びは人生の中で最も大きな選択のひとつです。その決断が次の世代にも受け継がれる可能性があるからこそ、寺院墓地という選択を考えてみてはいかがでしょうか。