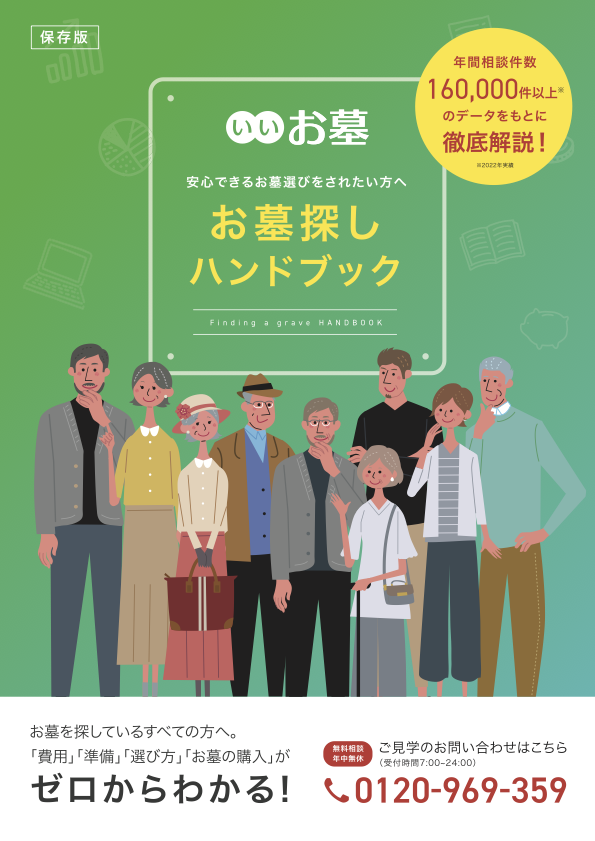霊園・墓地は、経営母体によって公営霊園・民営霊園・寺院墓地の3つの種類にわけられます。
公営霊園は、都道府県や市区町村などの地方公共団体が運営する霊園。「安心感がある」「価格が安い」といった理由から人気です。
この記事では、公営霊園の特徴や費用相場、メリット・デメリットなどを解説します。
公営霊園とは?公営墓地の4つの特徴
公営霊園は、都道府県・市区町村などの地方公共団体や自治体が管理・運営している霊園のことです。また、自治体から委託された企業や財団法人などが管理や運営を行っている場合もあります。
公営霊園には次のような特徴があります。
経営が安定している

お墓は長期にわたって利用するものなので、霊園の経営が安定しているかどうかは大変重要です。
公営霊園は、自治体またはそれに準ずる機関が管理運営をしています。そのため他の霊園と比較して、倒産や閉鎖などの危険性は少ないといわれています。合併などで自治体がなくなった場合にも、新しい自治体が経営を引き継いでくれます。
公営霊園の主な運営資金は税金です。このほか公営霊園の使用者からの使用料、管理料などがあります。
石材店の制限がない
民営霊園や寺院墓地では、墓石を販売している石材店などと提携している場合があります。そういった場合、墓石を建立する際、依頼先の石材店を指定されることがあります。
一方、公営霊園では特定の業者に有利にならないよう、平等にする必要があることから、基本的にどの石材店に墓石の建立を依頼しても問題はありません。
宗教による制約がない
公営霊園の使用に関しては、宗旨・宗派は不問です。どのような宗教を信仰していても制約なく利用できるのは、公営霊園の大きな特徴です。
公営霊園の管理、運営は行政サービスの一環として行っているものです。そのため、「信教の自由」が保証されています。また、その地域で亡くなった身寄りのない方や、身元不明の方が公営霊園に埋葬されることもあります。宗教についての制約がないため、そういった方たちがどのような宗教を信仰していても受け入れることができます。
区画が大きめの霊園が多い
例外もありますが、基本的に公営霊園は民営霊園より1区画の面積が広いところが多いようです。
区画が広いと解放感もあり嬉しく感じますが、一方で大きな区画に釣り合う墓石を用意しようとするとコストがかかります。また、広いので雑草の処理など、管理には手間がかかってしまいます。
公営霊園・墓地の費用相場と内訳
公営霊園のコストは民営霊園と比較して費用は安いといわれます。しかし、使用料についてはその土地の地価などとも関係してくるため、一概に安いとはいえません。
お墓を購入するためには、管理費・永代使用料・墓石の費用がかかります。それぞれについてみていきましょう。
管理費
管理費とは、霊園の維持・運営管理の費用として毎年支払う費用です。
各自治体や霊園・区画の種類によっても異なりますが、年間1,000~10,000円の範囲に収まるのが一般的です。公営霊園の管理費に関しては、民営霊園や寺院墓地より費用を抑えやすいといえるでしょう。

- 公営霊園
年間管理費の目安:620円~(東京都の場合)
※自治体運営のため、負担の経費が低目に抑えられている - 民営霊園
年間管理費の目安:5,000円~15,000円程度
※永代使用料と同様、都市型霊園の方が郊外の霊園より高くなる傾向あり - 寺院墓地
年間管理費の目安:6,000円~25,000円程度
※寺院施設使用料、お布施や冥加金という名目で納めることもあり
※上記はあくまで参考金額であり、実際の管理料に関しては、霊園・墓地それぞれ異なります。
※長期間にわたって管理費を滞納した場合、管理運営主が一定期間告知を行った上で、永代使用権が取り消されることもあります。
永代使用料
| 霊園名 | 種別 | 募集数 | 使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|---|
| 青山霊園 | 一般埋蔵施設 (1.60~3.65 ㎡) | 60カ所 | 4,752,000~10,840,500 円 | 1,500~3,000 円 |
| 谷中霊園 | 一般埋蔵施設 (1.50~3.70 ㎡) | 65カ所 | 2,817,600~6,515,700 円 | 1,500~3,000 円 |
| 雑司ヶ谷霊園 | 一般埋蔵施設 (1.55~1.65 ㎡) | 60カ所 | 3,138,750~3,341,250 円 | 1,500 円 |
| 染井霊園 | 一般埋蔵施設 (1.50~2.00 ㎡) | 75カ所 | 2,434,500~3,246,000 円 | 1,500 円 |
| 立体埋蔵施設 | 25カ所 | 597,000 円 | なし | |
| 多磨霊園 | 一般埋蔵施設 (1.75~7.95 ㎡) | 300カ所 | 1,613,500~7,329,900 円 | 1,500~6,000 円 |
| 合葬埋蔵施設 (合葬式墓地) | 640体 | 60,000円/体 | なし | |
| 樹林型合葬埋蔵施設 (樹林墓地3号基) | 2,360体 | 91,0000円/体 ※粉骨の場合は 30,000円/体 | なし | |
| 八柱霊園 | 一般埋蔵施設 (1.50~5.90 ㎡) | 315カ所 | 307,500~1,209,500 円 | 1,500~4,500 円 |
| 合葬埋蔵施設 (合葬式墓地) | 1,440体 | 117,000 円/体 | なし | |
| 小平霊園 | 一般埋蔵施設 (1.85~5.85 ㎡) | 95カ所 | 1,561,400~4,937,400 円 | 1,500~4,500 円 |
| 芝生埋蔵施設 (4.00 ㎡) | 5カ所 | 3,504,000 円 | 3,720 円 | |
| 合葬埋蔵施設 (合葬式墓地2号基) | 300体 | 53,000 円/体 | なし | |
| 八王子霊園 | 芝生埋蔵施設 (4.00 ㎡) | 120カ所 | 1,288,000 円 | 3,720 円 |
公営霊園の区画を使用する権利を得るための費用です。こちらは霊園によって大きな差があります。
都立霊園を例にみると、青山霊園の一般埋蔵施設の使用料は4,752,000~10,840,500円。1千万円以上の区画もあり、非常に高額です。一方、八柱霊園の一般埋蔵施設の使用料は307,500~1,209,500円と、他の霊園と比べると比較的安価といえます。
地方についても、各地域の一等地やそれに近い場所にある公営霊園の場合、使用料は高めです。一等地を外れたところにある公営霊園だと使用料は安くなり、中には数万円の霊園もあります。
また、区画や埋蔵・収蔵の形態によっても使用料は変化します。公営霊園内にも一般墓だけでなく、芝生墓地や樹木葬墓地、納骨堂、合祀墓地・合同墓地などさまざまな施設があります。これらの施設によっても使用料は大きく変化します。
墓石費用
墓石費用の相場は、約50万円~100万円。お墓を建てる際に必要となる墓石代は、選ぶ墓石の種類やデザインで価格も変わります。
2024年にいいお墓が実施した「第15回お墓の消費者全国実態調査」によると、一般墓の平均購入価格は149.5万円。平均購入価格のうち、永代使用料(土地利用料)は平均47.2万円、墓石代は平均97.4万円を占めています。
公営霊園・墓地のメリット
公営霊園(公営霊園)にはさまざまなメリットとデメリットが混在します。
低コストの公営霊園が多い
一般的には、民営霊園より公営霊園の方が使用料や管理料が安くなる傾向があります。
もちろん前述のように地域や霊園の立地条件、希望する区画の形態などによっては、大きな差があります。あくまで目安として費用が抑えられるのは公営霊園と考えても問題ないでしょう。
経営主体が安定している
自治体が管理しているため、倒産や廃寺といったリスクが他の霊園・墓地と比べて少ないといえます。
もし、霊園がなくなれば、高額な永代使用料は戻ってきませんし、新たに墓地を求める必要も生まれます。そうした点では、経営主体が安定している点は、霊園、墓地を選ぶにあたっても非常に重要です。
宗旨・宗派・宗教の縛りがない
公営霊園は、その自治体に住んでいる人であれば、宗旨宗派にかかわらず利用できます。宗教的な制限がないというのは、公営霊園の大きなメリットのひとつといえるでしょう。
石材店の指定がない
公営霊園でお墓を建てる場合、依頼する石材店を指定されることはありません。石材店の比較検討の幅も広がり、コストを抑えることができます。また、オリジナルな形の墓石を作りたい場合など、そういったことが得意な石材店に依頼ができます。
墓石を選ぶ際の自由度が多いというのは、公営霊園の魅力のひとつです。ただし、霊園や区画によっては規格化された墓石が既に存在するところもあります。必ず事前に確認してください。
公営霊園・墓地のデメリット
申し込み条件が定められている
それぞれの公営霊園や区画によっても異なりますが、申し込みには条件が定められています。例として以下のようなものがあります。
- 申込者の住所が霊園を管理運営する自治体の管轄にあること
- 遺骨があること
- 親族に承継者がいること
条件を満たしていない場合、お墓を持つことはできませんのでご注意ください。申込み条件は、各公営霊園の申し込み要項を確認しましょう。
申込み期限が限定されている・応募多数だと抽選になる
多くの公営霊園は、使用するための申込みをする期限が定められている場合が多いです。また、応募多数となった場合は抽選となります。たとえ応募し続けても、当選しなければお墓を建てることができないのです。
施設が不十分なことがある
多くの民営霊園には法要施設が併設されていますが、公営霊園にはないところも多いです。
法要施設がないと、お寺などで法要をあげてもらってから墓地に移動して納骨する必要があります。場合によっては休憩所がないところや、桶と杓子や水場などがないところもあります。
ルール・制約が多い
公営霊園では、墓石の幅や高さを制限されることがあります。
樹木を植えていい霊園もありますが、その場合でも高さや大きさの制限があります。何かと決まりごとが多いので、申し込み前によく確認しておきましょう。
公営霊園と民営霊園・寺院墓地の違い
お墓を経営主体ごとに分けると、宗教法人あるいは公益法人が運営する「民営霊園」と、宗教法人である寺がその敷地内で運営する「寺院墓地」、そして、都道府県や自治体による運営の「公営霊園」があります。
民営霊園とは
民営霊園は、財団法人や社団法人、宗教法人またはそこから運営委託を受けた民間企業によって管理・運営される霊園です。
- 個性的な特色や雰囲気、サービスなど利便性向上のための工夫をしている所が多い
- 申し込み条件は、寺院墓地・公営霊園と比較すると緩め
- お墓のデザインや大きさなどが自由に選択できる
- 担当の石材店(指定石材店)が決められていることが多い
- 価格面において割高になる場合がある
寺院墓地とは
お寺の境内地に墓地があり、主に寺院によって管理・運営されています。
- 境内地に本堂、仏様(ご本尊)がある安心感
- 僧侶・住職がいるため、葬儀や法要など供養面では困らない
- 歴史や境内地の醸し出す風格や独特の雰囲気
- 墓地の継承者がいなくなった場合でも永代供養を受けられることが多い
- 宗旨・宗派が限定されることが多い
- 檀家になること(入壇)を前提条件とする場合がある
- お寺の行事や活動への参加、寄付等を求められることがある
- 担当の石材店(指定石材店)が決められていることが多い
- お墓の形状やデザイン、大きさなど墓石選択の自由度が低い場合がある
- お寺や住職によって運営面での差が生ずることがある
公営霊園に入るには?申し込みの条件
公営霊園に入るには、基本的にその自治体に住んでいなければなりません。住んでいる期間にも制限があり、3年以上居住または5年以上居住などの条件があります。
これの条件をクリアしたうえで、自治体が定めた申込期間中に申込まなくてはなりません。申込期間は、自治体のホームページや役所の窓口などで確認してください。自治体によっては毎年ある程度決まった時期から募集が始まりますが、不定期の場合や募集を行わない年もあります。
また、申込者が多い場合は抽選になります。抽選に当選したら、申込資格を本当に満たしているかを確認されます。このときに身分証や戸籍謄本などの必要書類を提出することが多いです。その後は永代使用料や管理費を支払い、使用の許可が下りたらお墓を使うことができます。
公営霊園の管理者は?指定管理業者や使用者
公営霊園の指定管理業者とは
公営霊園は自治体が管理していますが、各自治体の公務員が直接管理しているとは限りません。
民間の業者に管理と運営を委託していたり、自治体が民間人を雇っていたりするケースも多くあります。管理を委託された業者のことを指定管理業者などと呼びます。
しかし、間接的にとはいえ自治体が管理を行っていることに代わりはありません。要望や問題点などがあれば自治体に問い合わせれば解決することがあります。ただし「指定管理業者へお尋ねください」とかわされることもあるので注意してください。民間の業者と言っても行政側が定めたルールに則って管理をしているので、規則に則った安定したサービスを受けることができます。
一方で、サービスの内容が他の民営霊園、寺院霊園に劣る場所もあります。どのような管理体制なのかを事前に確認し、現地へ足を運んで霊園の様子を確認しておくことが大切です。
使用者が共同で管理する公営墓地もある
各自治体の条例をみてみると、たくさんの公営霊園を有している自治体もあります。このような公営霊園の中には、共同墓地(集落墓地、部落墓地、村墓地、みなし墓地などと呼ばれることもあります)もあります。
これらは、現在の墓地や埋葬に関する法律が作られる以前から、村落など地域の共同体によって使用、管理・運営されていた墓地です。法律ができ、地方公共団体の管理するお墓となりましたが、実質的な管理・運営は現在も、地域の人々や使用者などによって行われているところも、数多くあります。
代表的な公営霊園の例
都立青山霊園
おそらく誰もが一度は聞いたことがある霊園なのではないでしょうか。東京都港区にある霊園で、日本初の公営霊園として知られています。
歴史ある霊園なので、多くの著名人のお墓が存在します。例を挙げると大久保利通、犬養毅、乃木希典、国木田独歩、志賀直哉、北里柴三郎などが青山霊園で眠っています。忠犬ハチ公のお墓もありますが、遺体は剥製になっているのでお墓には何も埋まっていません。
桜並木が有名で、お花見のシーズンには多くの花見客が訪れます。

都立多磨霊園
東京都府中市と小金井市をまたぐように存在する霊園です。
近代日本におけるお墓のフォーマットを作ったと言われる霊園で、東郷平八郎や山本五十六が眠っている場所としても知られています。
人気の高い霊園ですが、新規に区画を作っておらず、募集は改葬などで移転者が出たときのみ行われます。そのため抽選倍率がものすごく高いことでも知られます。

主要都市の主な公営霊園
北海道・東北


関東
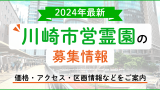


中部

関西

中国・四国

九州・沖縄

公営霊園をお探しなら「いいお墓」へ
公営霊園は自治体が管理しているので、安定性とコストの安さが魅力です。しかしエリアによっては、コストが高くなる場合もあるので注意してください。
民間の霊園より設備が整っていない霊園や、独自のルールを守らなければならない公営霊園もあるので、よく検討した後に申し込みを行ってください。


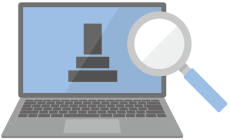
 かんたん
かんたん