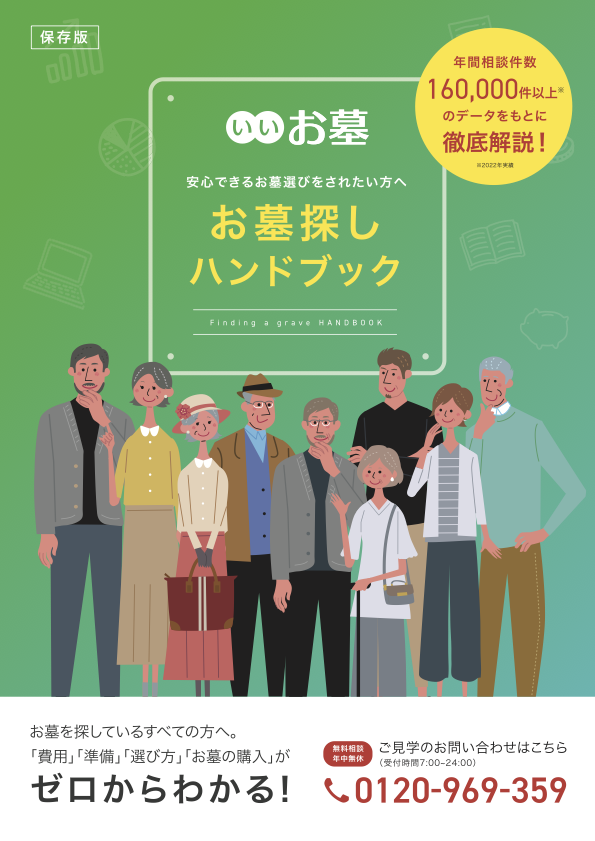この記事はこんな方におすすめ:お盆の日程、意味や過ごし方について知りたい方
- 2024年の7月盆(新暦のお盆)は、7月13日(土)から7月16日(火)までの4日間
- 2024年の8月盆(月遅れ盆)は、8月13日(火)から8月16日(金)までの4日間
- 2024年の旧盆(旧暦のお盆)は、8月16日(金)から8月18日(日)までの3日間
お盆とは、故人やご祖先の霊魂を供養する期間のことです。この時期には浄土=あの世にいる霊魂が、生前過ごしていた地上に帰ってくるといわれています。この記事では、お盆のスケジュールを紹介するとともに、どのように霊魂をお迎え・供養をすればよいのか、お盆の成り立ちや作法、過ごし方などについて紹介していきます。
お盆の意味とは

正式には「盂蘭盆(うらぼん)」や「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、サンスクリット語である「ウラバンナ(逆さ吊り)」を漢字に置き換えたものという説が一般的です。また一方では、イランなどアラブの地域で死者の御霊を祀る行事が中国に伝わり、収穫祭とあいまって日本に伝わったという説もあります。また、祖霊信仰と仏教が融合した行事だともいわれています。
日本に伝わった後も、お盆は神道や農耕儀礼、ご先祖様をお祀りする習慣などさまざまな要素が融合されて、現在の形に発展しました。そのため地域や家庭の宗教で違いがあり、お盆の準備はそれぞれの地域や家庭の宗教に伝わる方法でおこなう必要があります。春(春分の日)と秋(秋分の日)の年2回の彼岸と、お盆は異なるものです。また七夕は先祖供養のためのお盆の行事だったともいわれています。
人が亡くなってから四十九日を過ぎた後、初めて迎えるお盆のことを初盆と言います。地域によっては新盆と呼ぶこともあります。四十九日よりも前にお盆を迎えた場合には、その年ではなく翌年が新盆となります。
お盆の時期は新盆・月遅れ盆・旧盆の3つ
お盆の時期は、7月盆(新暦のお盆)、8月盆(月遅れ盆)、旧盆(旧暦のお盆)の3つに分かれます。以下では、それぞれの意味と時期についてご紹介します。
①7月盆(新暦のお盆)
7月盆は、新暦の7月15日を中日に、7月13日から16日までの期間のお盆です。
東京など首都圏の多くの地域では7月13日から16日までをお盆の期間としていることが多いです。
②8月盆(月遅れ盆)
月遅れ盆というのは、ひと月遅れのお盆で、8月15日を中日に、8月13日から16日までの期間のお盆です。
首都圏以外(主に西日本)では、8月13日から16日までをお盆の期間としていることが多いです。ちょうどお盆休みの時期で、この時期に合わせて連休をとり帰省する人も多いのではないでしょうか。
首都圏と他の地域で1カ月違いがある理由としては、住まいの問題が考えられます。東京と地方で同じ時期がお盆になってしまうと帰省ができなくなるため、あえて時期をずらしているという説があります。
③旧盆(旧暦のお盆)
こちらは旧暦の7月15日を中日としたお盆で、旧暦なので年度によって日付が前後します。
沖縄と鹿児島県奄美地方では、今も旧暦にのっとってお盆が行われます。お盆の期間は他の地域より1日短く、旧暦7月13日~15日の3日間が一般的です。
お盆にすること:精霊馬や御霊膳の準備など
時期や習慣にはそれぞれ伝統の違いがありますが、準備や過ごし方、供えるものは主に次のようなことがあげられます。
- 精霊棚または真鍮の盆棚などを用意する。
- 御霊のためにお食事=膳を用意する。
- なすと賽の目に刻んだきゅうりで精霊馬(しょうりょううま)をつくる。
- お墓や仏壇をきれいにして果物などのお供え物やお飾りをする。仏壇の掃除を行い仏具に不具合がないか確認をする。
- 仏壇には位牌も安置し、線香をたてる。香炉の灰を交換する。
- 空間を清め、迎え火を焚いて霊魂を迎える。
- 精霊棚には欠かさずにお供え物をおく。
- 送り火を焚いて霊魂を送る。
お盆の時期に、菩提寺のお寺からお坊さんを呼んで読経をしてもらうお盆法要を執りおこなうこともあります。その際は、僧侶にお礼としてお布施をお渡しすることになります。
夏の風物詩として今でも各地で開催される盆踊りは、お盆の時期に祖先を供養するための行事が由来となっています。元来、地域全体で精霊をお迎えし、お送りするためのイベント的な意味合いがあり、町をあげて踊り明かした阿波踊りはその代表格です。沖縄の伝統芸能の「エイサー」はいわゆる盆踊りで、ウークイと呼ばれる3日目に演舞が披露されます。
お盆のはじまり・起源
お盆の歴史は古く、日本書紀によると、初めて行われたのは飛鳥時代が起源だとされています。推古天皇が初めてお盆の法要をおこない、その後、聖武天皇の時代に宮中でのお盆行事が流行しました。次第に武家や貴族などの上層階級に広がり、江戸時代に入ってからは一般庶民にも普及しました。
日本ではお盆の時期にご先祖様が帰ってくるとされ、故人の霊をお迎えするためのお供えや儀式をおこなうことで、生きている人も幸福を得られると考えられています。
日本の仏教では、お盆はお釈迦様の弟子である目連が、餓鬼道に落ちて苦しんでいる母親の魂を救うために、修行を終えた僧たちを供養したことがはじまりだといわれています。このときお釈迦様は、僧侶たちが修行を終える7月15日に、仏や僧など大勢の人を供養し、その功徳により多くのご先祖が救われたとされ、これがお盆の起源となっています。
お盆にお墓参りをする意味とは?

お墓がある方の多くは、お盆にはお墓参りをすると思います。しかしお盆期間中はご先祖様の霊は家に帰っているはずなのに、なぜお墓にお参りに行くのでしょうか。
お墓参りは供養のためにおこなうもの
昔からご先祖様は、いつもわたしたちを見守り導いてくれる存在として、敬意をもって大切に扱うべきだとされてきました。お墓はご先祖様が眠っている場所でもあり、魂をお祀りするためのものです。したがって、お墓に足を運んで手を合わせることは、ご先祖様を供養するための大切な方法のひとつです。
お墓参りとは亡くなられた人へのあいさつであり、敬う気持ちを示すためにおこなうものです。宗派によって考え方は異なりますが、古来より人間は亡くなった後に輪廻をすると考えられています。お墓参りとはその輪廻から解き放ち極楽浄土に旅立たせてあげる方法の一つです。墓前に足を運ぶことによって、故人、ご先祖様との結びつきを再確認できる機会でもあります。
感謝の気持ちを示すことが何よりも重要
もともとお盆のお墓参りには、「亡くなった方やご先祖様の霊魂を迎えに行き、一緒に帰って数日を共に過ごしたあと、送り届ける」という風習がありました。したがって、本来ならば2回お参りをすることがよいとされていましたが、お墓が遠いなどの理由から実施が難しい場合も増えています。
お墓参りでは、本来のしきたりにこだわらず、感謝と供養の気持ちを込めて墓前にお供え物をし、手を合わせることが大切です。お墓は浄土と現世の玄関口の役割があるともいわれているので、きれいに磨くことでご先祖様の霊魂を気持ちよく迎え、送り出すことができると考えられています。
お盆にお墓参りに行く時期について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
お盆の行われる月(7月、または8月)の1日を「釜蓋朔日(かまぶたついたち)」と呼びます。これは、「地獄の釜のふたが開く日」という意味です。お盆に合わせ、各家のご先祖様が戻ってくる様子を表現した呼び名として関東で使われています。
お盆でよくある疑問
Q. お盆のお墓参りは、13日に行かないといけませんか?
13日は迎え盆と呼ばれる、ご先祖様をお迎えに行く日です。そのため13日にお墓参りをし、ご先祖様の霊を迎えるための「送り火」を焚きます。お盆の墓参りは、13日に行くのが一般的と言われていますが、必ず13日に行かなければいけないという訳ではありません。もし、お墓のある実家が遠い場所にある場合や仕事の都合で行くことができない場合、お盆期間の他の日にお墓参りをしましょう。
Q. 新盆(初盆)は故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことですか?
故人が亡くなって四十九日を過ぎた後にお盆が来る場合には、亡くなった年が新盆(初盆)となりますが、四十九日より前にお盆が訪れる場合は、翌年のお盆が対象となります。間違えやすいので気をつけましょう。
まとめ
お盆とは感謝と供養の気持ちをもって霊魂を迎え、送り出す期間のこと
- 2024年の新盆(新暦のお盆)は、7月13日(土)から7月16日(火)までの4日間
- 2024年の月遅れ盆は、8月13日(火)から8月16日(金)までの4日間
- 2024年の旧盆(旧暦のお盆)は、8月16日(金)から8月18日(日)までの3日間
お盆は故人やご先祖様の霊魂が家に帰ってくることのできる、年に一回の行事です。習慣や時期、供物や飾りつけのしかたなどは地域や家庭によって違いがありますが、感謝の気持ちをもって心を込めて霊魂を迎え、送り出す供養をおこなうことが重要です。意味や役割をしっかり理解したうえで、お盆を迎えることは、より良い供養につながるのではないでしょうか。
また、お盆は家族や親族が一同に会する絶好の機会です。この好機に、今後、お墓をどうするか家族で話し合ってみてはいかがでしょう。


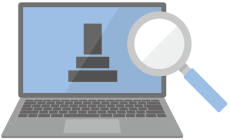
 かんたん
かんたん