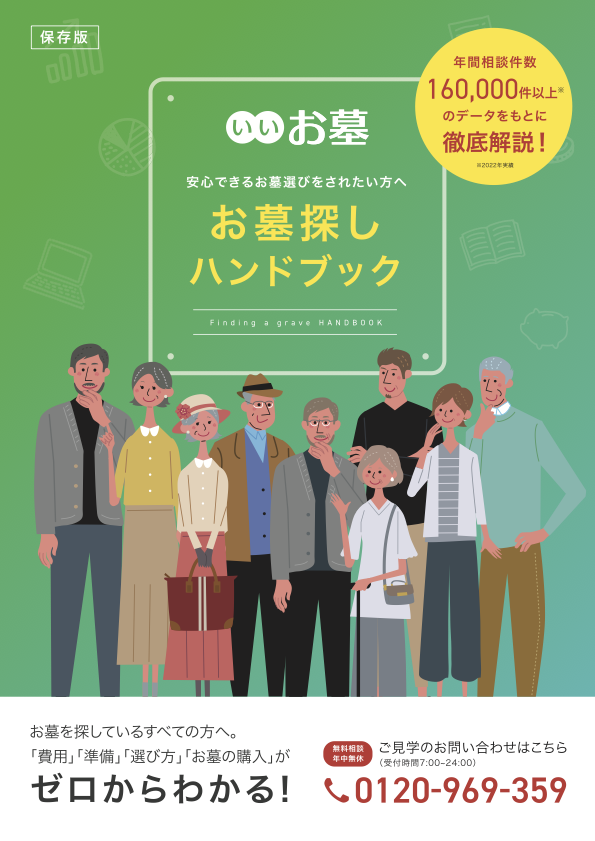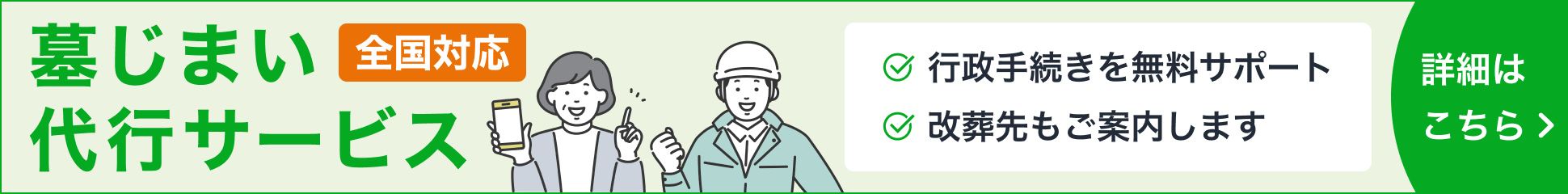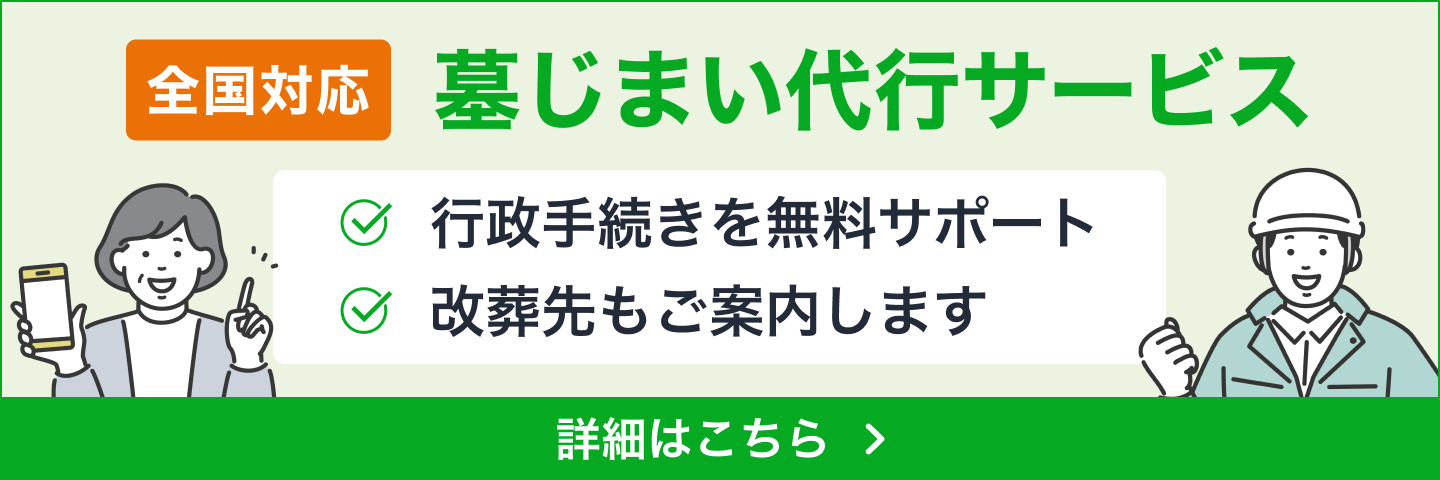合祀墓(ごうしぼ)とは、複数人の遺骨を1か所にまとめて埋葬するお墓。個々の墓石がなく、管理・供養の手間がかからないため、費用相場は3万円〜30万円と安価です。
この記事では、合祀墓の費用相場や内訳、墓じまいして合祀墓に移すときの価格などをご紹介。あわせて、知っておきたい合祀墓の種類やメリット・デメリットもまとめています。
合祀墓にかかる費用は3万円~30万円
合祀墓にかかる費用は3万円〜30万円が目安です。
2024年にいいお墓が実施した「第15回お墓の消費者全国実態調査」によると、一般墓の平均購入価格は149.5万円。通常のお墓と比べると、合祀墓は費用を大幅におさえられます。
合祀墓によっては、1体3万円〜5万円で納骨することも可能。さらに最初から合祀する合祀墓は、年間管理費が不要なため、お墓の維持費もかかりません。
一方、一定期間個別で納骨したあとに合祀する合祀墓も存在します。個別で遺骨を管理・供養する期間があるぶん、かかる費用も50万円前後まで上がります。
合祀墓にかかる費用の内訳

| 合祀墓にかかる費用の内訳 | 費用の目安 |
|---|---|
| 永代供養料 | 3万円~30万円 |
| 納骨料 | 3万円〜10万円 |
| 刻字料 | 3万円~ |
合祀墓にかかる費用の主な内訳は、永代供養料・納骨料・刻字料の3つです。
永代供養料とは、墓地管理者にお墓を維持・管理・供養してもらうための費用で、相場は3万円〜30万円。納骨料は納骨時に僧侶へ渡すお布施で、3万円〜10万円が目安です。また、墓誌に故人の名前を記録する刻字料は、3万円〜が相場となっています。
霊園・寺院によって、永代供養料に納骨料が含まれていたり、刻字料がオプションだったりするため、金額が大きく異なります。さらに、一定期間個別で納骨したり戒名を授与したりすると、別途料金がかかる合祀墓もあるので注意しましょう。
墓じまいをして合祀墓に移す費用

| 墓じまいにかかる費用の内訳 | 費用の目安 |
|---|---|
| お墓の撤去に関する費用 | 30万円〜50万円 |
| 行政手続きに関する料金 | 数百円~1,000円程度 |
| 墓じまいにかかる費用の総額 | 35万円~50万円 |
墓じまいとは、既存のお墓を解体・撤去したあと、更地にして墓地管理者に返すこと。
先祖代々のお墓があるご家庭では、今あるお墓を墓じまいしてから、新たに購入した合祀墓へ納骨するのが一般的です。墓じまいをして合祀墓に移すときは、「合祀墓の費用」に「墓じまいの費用」が上乗せされます。
墓じまいにかかる費用の目安は35万円〜50万円ほど。内訳は、お墓の撤去にかかる費用と墓じまいの行政手続きにかかる費用、大きく2つにわけられます。墓じまいするお墓の立地や敷地面積などによって金額が変わるので、あくまで目安として参考にしてください。
いいお墓では墓石の撤去から各種手続き、改葬先のご案内まで墓じまいの全工程をサポートし、明朗な見積もりを提示しております
合祀墓・合祀とは
合祀墓(ごうしぼ)とは、複数人の遺骨を1か所にまとめて納める共同のお墓のこと。また、そもそも合祀(ごうし)とは、複数人の遺骨を一緒に埋葬することです。
合祀墓によって遺骨を合祀するタイミングが違い、最初から合祀するか、一定期間個別で埋葬したあと合祀するかのどちらかにわかれます。骨壺から遺骨を取り出して埋葬するため、一度合祀すると個々の遺骨は取り出せません。
合祀後は、墓地管理者がお墓の清掃や供養をしてくれるので、家族は定期的なお墓参りをするだけでOK。複数人の遺骨がまとめて埋葬される合祀墓は、墓標や参拝スペースが共用なのが基本です。参拝スペースに線香やお供え物を置き、手をあわせてお参りをします。線香・供花・お供えの可否や法要の回数・内容などは、合祀墓によって違うため、必ず確認するようにしてください。
合祀墓を選ぶ理由・向いている人
- お墓の維持・管理が難しい
- お墓の費用をおさえたい
- 先祖代々の遺骨を整理したい
合祀墓は、墓地管理者がお墓の管理・供養を代行してくれます。そのため、定期的なお墓参りや清掃が難しかったり、跡継ぎがいなかったりするご家庭に向いています。また墓石がないぶん初期費用をおさえやすく、維持・管理費もかからないので、コストを削減したい方にもおすすめです。
その他、先祖代々のお墓の遺骨を整理するために合祀墓を選ぶ方もいらっしゃいます。古い遺骨を合祀墓に移すことで、既存のお墓の納骨スペースを新たに確保できます。
合祀墓の種類

- 慰霊碑型合祀墓
- 樹木葬(自然葬)型合祀墓
- 納骨堂型合祀墓
- 立体型合祀墓
- 個別集合型合祀墓
- 区画型合祀墓
合祀墓は、埋葬方法によって大きく6つの種類にわけられます。
慰霊碑型合祀墓
納骨室の上に碑や仏像、仏塔などのモニュメントを建てる合祀墓。
樹木葬(自然葬)型合祀墓
墓石の代わりに樹木を墓標(シンボルツリー)とした合祀墓。
納骨堂型合祀墓
納骨専用の屋内施設に合祀スペースが用意されている合祀墓。
立体型合祀墓
地上納骨室に骨壺を埋葬し、一定期間保管したあと、地下納骨室に埋葬する合祀墓。
個別集合型合祀墓
大きな墓の周囲に個々の納骨室が設けられている合祀墓。
区画型合祀墓
個人別の区画・納骨室に埋葬し、一定期間保管したあと、合祀用納骨室に埋葬する合祀墓。
合祀墓のメリット・デメリット
合祀墓のメリット
- お墓の継ぐ家族の負担を減らせる
- 無縁仏・無縁墓になる心配がない
- 墓石を購入するより費用をおさえられる
- 墓標や埋葬方法などお墓の選択肢が多い
- 宗旨宗派不問で誰でも利用できる
永代供養つきの合祀墓は、墓地管理者がお墓を管理・供養してくれるので家族の負担を減らせます。また将来お墓の承継者がいなくなっても、無縁仏・無縁墓になる心配は不要。さらに低コストで種類が多く、宗旨宗派不問なのもメリットです。
合祀墓のデメリット
- 故人・家族単位のお墓がなくなる
- 一度合祀すると遺骨を取り出せない
- 家族・親族など周囲の理解が不可欠
- 既存のお墓を墓じまいする必要がある
合祀墓は、他人の遺骨とまとめて1つの墓標に埋葬するため、個別のお墓がありません。さらに一度合祀すると遺骨を取り出せないので、埋葬前に家族・親族としっかり話し合って理解を得ておくのが重要です。また、先祖代々のお墓を合祀墓に移す方は、墓じまいの費用も別途かかるため注意しましょう。
合祀墓をお探しの方は「いいお墓」へ
核家族化や少子高齢化、生涯未婚率の上昇といった時代背景において、合祀墓は今後ますますニーズが高まっていくと考えられます。
ですが合祀墓は、従来のお墓と埋葬やお墓参りの方法が違うため、受け入れるのが難しい方もいらっしゃるかもしれません。一度合祀すると遺骨を取り出せないので、埋葬する前にご家族やご親族と十分話し合い、全員が納得したうえで決定するのが大切です。
また合祀墓を選ぶときは、資料請求や現地見学を行い、複数の霊園・寺院を比較することで、後悔の少ない選択ができます。「いいお墓」では、エリアや条件にあわせて全国の合祀墓を一覧で確認可能。資料請求や現地見学も無料で申し込めるので、合祀墓をお探しの方はぜひ「いいお墓」をご活用ください。


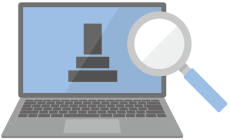
 かんたん
かんたん