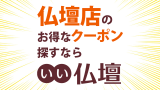墓石の値段は、石碑の種類や加工、デザイン、大きさなどによって変動します。そのため、墓石の値段を明確にしていなかったり、最低価格しか表示していなかったりする石材店がほとんど。後悔のない墓石選びをするには、墓石の適正価格や値段を決める要素を知っておくのが重要です。
この記事では、墓石の値段や内訳、価格を決める要素、お墓の費用をおさえる方法などを紹介します。
墓石の値段はいくら?一般墓の費用相場は平均149.5万円

| 項目 | 平均購入価格 |
|---|---|
| 墓石代 | 平均97.4万円 |
| 永代使用料(土地利用料) | 平均47.2万円 |
| 一般墓の購入費用 | 平均149.5万円 |
「第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)」によると、一般墓の平均購入価格は149.5万円。墓石代は平均97.4万円、永代使用料(土地利用料)は平均47.2万円です。
一般墓の購入にかかる費用は主に「墓石代」「永代使用料」「その他諸経費」の3つで、費用の約6割を墓石、約3割を永代使用料が占めています。
ただし墓石の値段は、地域や立地、種類、デザインなどによって相場が変わるので注意が必要。墓石の正確な値段を知りたいなら、建立する地域の石材店に相談してみましょう。
墓石の値段内訳と費用相場

| 墓石の値段内訳 | 費用の相場 |
|---|---|
| 墓石代 | 約50万円~150万円 |
| 永代使用料 | 約30万~100万円 |
| 管理料 | 約1万円/年間 |
墓石代:約50万円~150万円
墓石代とは、墓石の本体や外柵・納骨棺(カロート)、施工費などにかかる費用。墓石代の値段は約50万円〜150万円ですが、墓石の種類や加工費・施工費(工事代)によって大きく変動します。
永代使用料:約30万~100万円
永代使用料とは、霊園・墓地にある墓所の土地を借りる費用。墓所の土地を使用する権利を購入しているだけで、土地を購入している訳ではありません。
永代使用料の費用相場は、約30万〜100万円です。「永代使用料」と「墓石代」を合算した金額がお墓の価格になります。
管理料:約1万円/年間
管理料(管理費)とは、霊園・墓地に墓所を管理してもらうために定期的に支払う費用。墓所の水道・電気代の支払いや清掃、共有施設(休憩所・トイレ・水汲み場)の維持管理に使われます。
管理料(管理費)の費用相場は、年間約1万円。毎年納めるのが一般的ですが、中には数年分まとめて納める霊園・墓地もあります。ただし、寺院墓地はお布施が必要になる可能性があるため、確認しておきましょう。管理料(管理費)と永代使用料を納めることで、先祖代々お墓を引き継げます。
墓石の値段はなぜわかりにくい?価格が明記されない理由
墓石の値段を明示しない理由
店頭やホームページで、墓石の値段を明示していない石材店がよく見られますが、なぜなのでしょうか。お墓はオーダーメイド製品の一種で、立地や墓石の条件によって価格が大きく変わります。個々のお客様によって値段が違うので、混乱を避けるためにあえて明記していない石材店が多い様子。墓石・お墓の正確な値段を知りたいなら、複数の石材店から見積もりを取得して比較・検討するのが一番です。
墓石の値段に幅がある理由
- お墓の墓所の大きさ:使う石材の量によって値段が変わる
- 和型か洋型か:竿石の形態やデザインによって石材の量が変わる
- 石の種類や材質:石の等級や産地によって値段が変わる
- 墓石の細工:彫刻や加工の作業によって値段が加算される
墓石は、さまざまな要因によって値段に幅が生まれます。どの項目にもはっきりとした定価がないため、石材店に見積もりを依頼して、正確な値段を確認しましょう。
墓石の値段を決める8つの要素

- 石の種類・産地
- 石の使用量
- 墓石の加工・デザイン
- 墓石の彫刻
- 墓石の付属品
- 基礎工事費
- 耐震免震工事費
- 墓地の立地・状況
墓石の値段は、主にこちらの8つの要素によって変動します。
石の種類・産地
茨城県産の稲田御影(いなだみかげ)、真壁小目御影(まかべこめみかげ)、福島県産の浮金石(うきがねいし)、山梨県産の甲州御影(こうしゅうみかげ)、愛知県産の三州御影(さんしゅうみかげ)、愛媛県産の大島石(おおしまいし)、香川県産の庵治石(あじいし)、山口県産の徳山御影(とくやまみかげ)、佐賀県産の天山御影(てんざんみかげ)、神奈川県産の本小松石(ほんこまついし)
インド産の黒系の花崗岩「クンナム」、グリーン系グレーの御影石「アーバングレー」、赤系の「インペリアルレッド」、スウェーデン産の黒御影石「ファイングレイン」、南アフリカ産の黒御影石「インパラブルー」
石材の種類はもちろん、等級や産地によって墓石の価格は変化します。墓石の原石は、国産の石で約50種類、中国産やインド産など外国産の石で約100種類あります。お墓は何代にも渡って子孫に受け継がれていくため、硬度が高く、吸水性の低い石材ほど高価です。
耐久性が強く、磨くと光沢が出る石材として有名なのは、花崗岩(かこうがん)、安山岩(あんざんがん)、閃緑岩(せんりょくがん)、斑糲岩(はんれいがん)など。よく耳にする「御影石(みかげいし)」は、日本だけで使われる石の名称で、花崗岩の総称です。地下深くでゆっくり冷やされてできる「深成岩(しんせいがん)」に含まれ、六甲山嶺の神戸市御影付近が産地として有名だったので「御影石」と呼ばれるようになりました。御影石は経年劣化に強いため、墓石として最も人気です。また、国産の石材は海外産のものと比べて、高価になる傾向があります。
現在では多くの石材を外国から輸入していて、中でも中国産の石材輸入が大半を占めています。中国産の墓石の製品化が本格化したのは1990年代で、福建省で日本の業者との合弁工場が作られたのがきっかけ。そのほか、インドやスウェーデン、南アフリカも石材の産地として有名です。
石の使用量
お墓の大きさや形状、デザインによって、使用する石材の量が変わります。石材の量が増えるほど、墓石の値段も上がるのが一般的。とくに採取量の少ない貴重な石は、墓石にふさわしいサイズの石がなかなか出てこないため、より値段が高くなりやすいです。
墓石の加工・デザイン
墓石は、切り出した石のブロックを削り、加工して作ります。現在、外国で墓石を加工している工場の約9割を中国が占めていて、外国加工より国内加工の方が高額です。
また、凝ったデザインの墓石は、手間がかかるぶん値段が高くなりがち。本やピアノ、サッカーボールなど、故人の好きだったモチーフを作成するデザイン墓は、費用がかさみやすいです。
墓石の彫刻
文字の彫刻代は、購入した墓石に家名・題字・題目・建立者名・建立日などを彫るためにかかる費用。基本的な彫刻費用は墓石の値段に含まれていますが、家紋やペットのイラスト、肖像画などの特別なデザインを彫刻すると、費用がかさみます。
戒名彫刻をはじめとする字彫りにかかる費用は、約3万円〜5万円。墓石の正面に模様や文字を彫るなら、10万円〜が費用の目安です。棹石と墓碑のどちらに彫るか、どんな文字や絵柄を彫るかなど、オーダー状況に応じて値段が変化するので、事前に石材店に確認してください。
墓石の付属品
お墓の周辺に置く付属品によっても、墓石の値段は変わります。お墓の前に左右一対で設けられる花立て、線香を立てる香炉、ご先祖に水をお供えする水鉢、故人の名前を刻む墓誌などを設置すると、お墓の値段が上がります。また、付属品のサイズが大きかったり、装飾が複雑だったりすると、より費用が高額になるでしょう。
基礎工事費
基礎工事費とは、墓石を設置するときにかかる費用で、墓石代に含まれるのが一般的です。家を建てるときに基礎を打つように、お墓を建立するときも地盤をきちんと作らなければなりません。また、遺骨を納める納骨室の作成や外柵の設置も必要です。
お墓の基礎工事は見えない部分ですが、先々を考えると一番大切。地盤の強度や墓石の大きさにあわせた工事をしてください。
耐震免震工事費
耐震免震工事も、墓石の値段に影響を与えます。墓石を支えるボルトを取り付けたり、ゲル状の緩衝材を使用したりすると、内容によって費用が追加されるため確認しましょう。耐震免震工事で地震や災害による倒壊を防ぐのは、将来的な費用の削減にもつながります。
墓地の立地・状況
墓石を運搬する距離や道幅、区画の状況など、お墓を建立しやすい立地かどうかで、値段が変わります。駐車場から墓所までの距離が近かったり、クレーン車が通れる道幅だったりすると、石材を運ぶ工程が少なくて済むため、費用をおさえやすいです。
一方、墓所の区画が整備されていないと、運搬方法を別途手配しなければならないため、値段が加算されます。
墓石の値段を判断するときの3つの注意点
- 霊園・寺院が石材店を指定しているか
- 年間管理費がかかるか
- お墓の引越し・改葬が必要か
墓石に限らず、お墓はさまざまな要素が集約されて値段が決まります。墓石の値段だけに注目してお墓を購入するのは、リスクが大きいです。ここでは、墓石の値段を判断するときにあわせて確認したい3つの注意点を紹介します。
霊園・寺院が石材店を指定しているか
霊園・墓地によっては、石材店が指定されているかもしれません。指定の石材店があると、自分で安い墓石を探せないため、お墓の値段が高くなる可能性があります。
一般的に、民間墓地は石材店を指定している霊園がほとんど。寺院墓地はどちらの可能性もあるため、お寺に確認しましょう。一方、公営墓地には石材店が指定されていません。安い墓石を探すときは、必ず見積もりを取得して、信頼できる業者を選んでください。
年間管理費がかかるか
一度お墓を建ててしまえば、費用はもうかからないと思われがち。ですが公営霊園や民営霊園は、園の維持管理のために年間管理費を設定しているのが一般的です。また、寺院墓地はお布施が必要な可能性があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
お墓の引越し・改葬が必要か
お墓の引っ越し・改葬をするときは、既存の墓所の墓じまいをして、引っ越し移転先の墓所を確保しなければなりません。お墓の引越し・改葬にも費用がかかるため、必要なら事前に費用を用意しておくと安心です。
墓石以外にかかる費用の一覧と相場
| 墓石以外にかかる費用 | 費用の相場 |
|---|---|
| 納骨法要のお布施 | 約3万円〜5万円 |
| 埋葬手数料(納骨作業費) | 約2万円~5万円 |
| 開眼供養のお布施 | 約3万円〜5万円 |
| 入檀家料・志納金 | 約10万円~30万円 |
| 戒名料 | 約5万円〜100万円 |
| 仏壇の購入費 | 約20万円~100万円 |
| お墓のリフォーム・建て替え費用 | 約50万円~200万円 |
| 改葬・墓じまい費用 | 約35万円~150万円 |
お墓を建てるには、墓石以外にもさまざまな費用が必要です。ここでは、墓石以外にかかる主な費用を一覧で紹介します。
納骨法要のお布施:約3万円〜5万円
お墓へ納骨するときは、納骨法要(納骨式)を開く必要があります。納骨法要で僧侶に読経をお願いした場合、お布施の相場は約3万円〜5万円。地域や状況によりますが、必要なら御車代5千円〜1万円、御膳料1万円~もお渡しします。
埋葬手数料(納骨作業費):約2万円~5万円
遺骨を納骨するには、お墓の下部にある納骨室(カロート)を開けなければなりません。石材店に依頼する場合は、遺骨の取り出しと埋葬で、埋葬手数料(納骨作業費)として約2万円〜5万円支払います。
開眼供養のお布施:約3万円〜5万円
新しいお墓に納骨するときは、「開眼供養」と呼ばれる法要を行います。開眼供養は、個別ではなく、納骨法要や四十九日法要とまとめて行うのが一般的になってきています。
開眼供養のお布施の相場は、約3万円〜5万円。他の法要と同時に行った場合、お布施は法要ごとに各3万円〜5万円お渡しします。納骨法要と同様、遠方から僧侶を呼んだなら御車代が、会食に参加されないなら御膳料が必要。また、出席者への会食代や引き出物代として、1人1万円ほどかかります。
入檀家料・志納金:約10万円~30万円
入檀とは、特定のお寺を菩提寺にして檀家になること。入檀すると、そのお寺が菩提寺となり、法要・葬儀で読経や戒名の授与を依頼します。入檀して檀家になるには入檀料が必要で、相場は約10万円〜30万円です。入檀料以外に運営費を支払う寺院もあるため、確認しておきましょう。
ただし入檀料は、地域や宗旨宗派によって違います。また、お寺はお布施という扱いで入檀料を受け取るため、直接確認しても明確な回答を得られないかもしれません。
戒名料:約5万円〜100万円
仏教では、亡くなったあと菩提寺に戒名をつけてもらうのが一般的。戒名を授与していただくには、戒名料(お布施)を菩提寺に支払わなくてはいけません。
戒名料の相場は約5万円〜100万円と幅があり、寺院や戒名のランクによって金額が大きく異なります。お寺によっても金額設定がまちまちで、戒名料を尋ねても「お気持ちで」と返される寺院があるので、金額の目安がわかりにくくなっています。
仏壇の購入費:約20万円~100万円
仏壇は、故人を悼むために位牌を安置する場所。仏壇にもさまざまな種類があり、相場は約20万円〜100万円と幅広いですが、よく購入されている価格帯は20万円〜30万円です。
仏壇は、毎日手をあわせて故人を偲ぶ大切な空間。値段よりも、長く使える丈夫な材質や飽きのこないデザインなどを重視して選ぶのがおすすめです。
お墓のリフォーム・建て替え費用:約50万円~200万円
常時日差しや雨風にさらされる墓石は、経年劣化で汚れや腐食が出てきます。墓石のクリーニングや磨き直しで修復できない場合は、お墓のリフォーム・建て替えが必要です。
お墓の建て替えには、今ある墓石の撤去と新しい墓石の建立費用がかかります。さらに、閉眼法要・開眼法要なども必要で、費用相場は200万円ほど。お墓の建て替えではなく、リフォームや修繕で収まるなら50万円ほどが目安です。
お墓の建て替えにせよ、リフォームにせよ、高額な費用がかかります。複数の石材店に現地調査を依頼して見積もりを取得し、比較検討することで費用をおさえやすいです。
改葬・墓じまい費用:約35万円~150万円
改葬・お墓の引っ越しをする場合、もとある墓所の墓じまいを行い、引っ越し移転先に建立する墓所を確保しなければなりません。既存の墓石を解体・墓所を更地にして霊園管理者に返還し、新しいお墓を建立するのにかかる費用の目安は、約35万円〜150万円です。
墓石の値段が負担な方へ。費用を安くおさえる供養方法
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 樹木葬
墓石代はお墓の値段の半分以上を占めるため、負担が大きいです。しかし最近は、墓石を墓標にしない新しいタイプのお墓も登場しています。墓石の値段がかからないぶん、費用を安くおさえられるのが魅力。ここでは、墓石代のかからない3つの供養方法を紹介します。
永代供養墓
永代供養墓とは、遺族に代わって霊園・寺院が遺骨を管理・供養するお墓。
従来のお墓は、先祖代々受け継いでいくのが通例でした。ですが、核家族化や少子高齢化によって家族形態が変化したり、「子どもがいない」「子どもに負担をかけたくない」と考える人が増加したりした結果、後継者のいらないお墓が求められるようになりました。
永代供養墓は、お墓の後継ぎがいなくても契約でき、永続的に供養と管理を受けられます。そのため「自分が死んだあと、誰が供養してくれるのだろう」と心配する必要はありません。また、遺骨の有無に関係なく生前に申し込みできるのも魅力です。
納骨堂
納骨堂とは、遺骨を安置・供養するための施設で、建物内・屋内に多いです。元々は遺骨を一時的に納める施設でしたが、最近は遺骨を祭祀する施設として認識されています。
納骨堂は、広大な敷地が不要なので、主に都市部を中心に広がっている新しいタイプのお墓です。また、宗旨宗派に関わらず、納骨が可能な施設も増えています。
樹木葬
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓のこと。 「自然に還りたい」と考える自然回帰志向の人を中心に人気を集めていますが、永代供養つきの樹木葬が多く、お墓の後継ぎや墓地の管理者がいない人にもメリットが大きいです。樹木葬は寺院のほか、都立霊園のような公営霊園や民営霊園でも近年多く導入されています。
お墓の構造と付属部分の名称
- 石塔(せきとう)
- 棹石(さおいし)
- 上台(じょうだい)
- 中台(ちゅうだい・なかだい)
- 下台(げだい)
- 納骨室(カロート)
- 墓誌(ぼし)
- 外柵(がいさく)
- 水鉢(みずばち)
- 香炉(こうろ)
- 卒塔婆立て(そとばたて)
- 花立て(はなたて)
- 蓮華台(れんげだい)
- 灯篭(とうろう)
墓石の値段を調べるとき、お墓の専門用語がわかっていると理解がスムーズです。ここでは、一般的なお墓の構造と付属部分の名称を紹介します。
石塔(せきとう)
お墓の墓石全体を石塔(せきとう)と呼びます。石塔は「棹石」「上台」「中台」「下台」の4つの石から構成されています。
棹石(さおいし)
棹石(さおいし)は、お墓の一番上にある墓石で、一般的に家名が彫刻されている部分です。お墓と聞くと、棹石をイメージする方が大半でしょう。
上台(じょうだい)
上台(じょうだい)は、和型墓石の竿石や蓮華台の下にある石のこと。台石(だいいし)とも呼ばれ、家紋などを彫刻するお墓もあります。
中台(ちゅうだい・なかだい)
中台(ちゅうだい・なかだい)とは、お墓の一番上にある竿石の下に位置している石のこと。骨壺を納めるスペース(カロート)の上によくある部材です。
洋型墓石やデザイン墓石は、中台があることで、竿石正面に彫刻された文字が花立てや水鉢などに隠れて見えなくなるのを防げます。
下台(げだい)
下台(げだい)とは、お墓の一番下の土台となる石を指し、芝台(しばだい)とも呼ばれます。下台は棹石・上台・中台の下に位置しています。
納骨室(カロート)
納骨室(カロート)は、遺骨を納骨するスペースのこと。石やコンクリートで作られていて、形状は地域によって異なります。下台の地下に遺骨を埋蔵する納骨室を作るのが一般的ですが、地上に納骨室を作る陸・丘カロートもあります。
墓誌(ぼし)
墓誌(ぼし)とは、お墓の横に建立される石碑で、宗旨や宗派、地域の習わしなどによって墓標・霊標・戒名板・法名碑など、さまざまな呼び方があります。墓誌には、お墓に納骨されている故人の名前や戒名、没年月日などが彫刻されます。
墓誌の建立にかかる相場は約5万円〜50万円。宗旨宗派や墓地のスペースによっては墓誌の建設が難しかったり、安くするために設置しなかったりする方法もあります。
外柵(がいさく)
外柵(がいさく)とはお墓の周りを囲う柵で、隣の墓地との境界線となる役割があります。
水鉢(みずばち)
水鉢(みずばち)とは、先祖に水を供えるための鉢で、墓石の手前によく作られます。
香炉(こうろ)
香炉(こうろ)は、墓石の手前にあるお線香をあげる小型の炉。線香を立ててお供えする「立ち置き型」と、線香を寝かせてお供えする「くりぬき型」があります。
卒塔婆立て(そとばたて)
卒塔婆立て(そとばたて)とは、卒塔婆を立てておくためのスペース。卒塔婆とは、先祖を供養するためにお墓に建てる木の長い板です。石製や金属製など、さまざまな種類がありますが、機能に変わりはありません。卒塔婆・卒塔婆立てを使用しない宗派もあります。
花立て(はなたて)
花立て(はなたて)は、墓石下に左右一対で備え付けられている仏花を立てるスペースです。お墓参りや供養のときは、花立てにお花を供えます。
蓮華台(れんげだい)
蓮華台(れんげだい)は蓮の花をかたどった台座で、竿石の根本に設置されるお墓が多いです。
灯篭(とうろう)
灯篭(とうろう)とは、中にろうそくを立てて火を付ける日本の伝統的な照明機器です。故人の浄土への道標という意味もあります。
墓石・お墓を探すなら「いいお墓」へ
墓石の値段は、石の種類や使用量、墓石のデザイン、彫刻、工事費、立地などさまざまな要因で変動します。そのため、お墓を購入するときは必ず見積もりを依頼して、正確な値段を把握するのが大切。さらに複数の石材店を比較検討すると、適正価格がわかりやすく、より納得いくお墓探しができるでしょう。
「いいお墓」では、全国のお墓をエリアや予算に絞って一覧でチェック可能。資料請求や見学予約も無料で受け付けているので、お墓探しをよりスムーズに進められます。墓石・お墓をお探しの方は、ぜひ一度「いいお墓」をご活用ください。