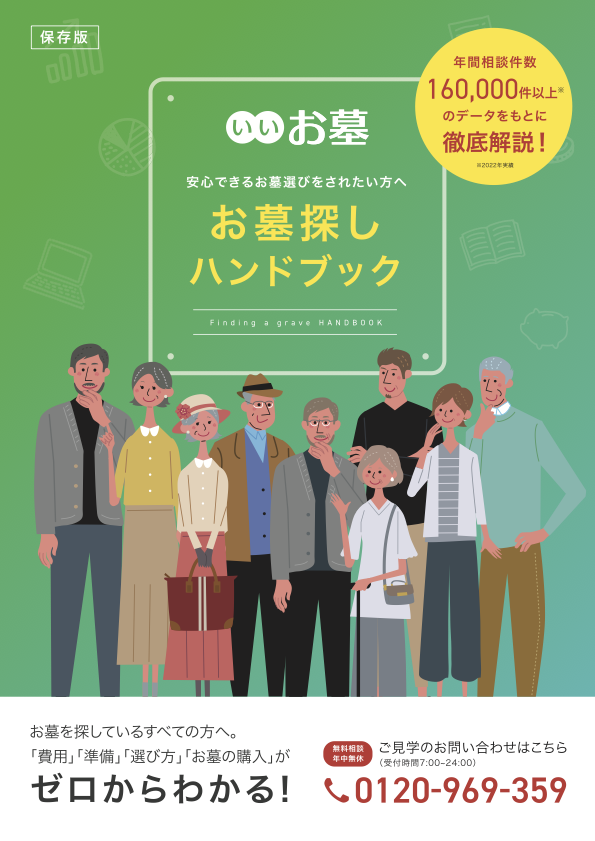法要で僧侶に読経・戒名などをしていただいたら、お礼としてお布施を渡すのが一般的です。永代供養でも、初期費用にお布施が含まれていない霊園・寺院の場合、別でお布施を用意しなければなりません。
この記事では、永代供養のお布施の金額相場や封筒の選び方、表書き・裏書きの書き方などを解説します。
永代供養のお布施は契約次第で必要
お布施とは、法事・法要で読経をしていただいたり、戒名をつけていただいたりしたお礼として僧侶に渡す謝礼のことを言います。
永代供養の場合でもお布施は必要です。
永代供養することを寺院に依頼した場合、お布施が必要になるのは、お墓に遺骨を納骨する際に行われる「納骨法要」の時と、一周忌、三回忌、七回忌などの故人の命日から節目となる年に行われる「年忌法要」の時です。
永代供養の場合では、寺院が供養をしてくれるので基本的に年忌法要の必要はないのですが、親族や親しかった人で集まり、故人を偲びたいということで、永代供養であっても年忌法要を行う人は多いようです。
永代供養のお布施の金額目安
| 法要 | お布施の金額目安 |
|---|---|
| 納骨法要 | 3万円~5万円 |
| 一周忌法要 | 3万円~5万円 |
| 三回忌法要以降 | 1万円~5万円 |
お布施は読経や戒名の授与に対する対価ではなく、感謝の気持ちという意味合いがあるため、その金額は決められてはいません。ただし、いくら包むか、おおよその相場があります。
納骨法要でのお布施の相場としては、3万円~5万円が目安になります。開眼供養(魂入れ)が必要な場合には納骨法要と合わせて10万円ほどが目安になります。寺院や霊園によっては納骨法要のお布施代が永代供養料に含まれている場合もあるので、あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。
年忌法要を依頼する場合のお布施の相場は、一周忌法要での相場は3万円~5万円ほどが一般的です。三回忌以降は一周忌と同様か少なめの1万円~5万円がお布施の相場になります。
永代供養のお布施に使う封筒
永代供養のお布施の封筒は、白無地の郵便番号の記入欄が印刷されていないものを使います。
水引は必要ありませんが、水引が印刷されている封筒でも問題ありません。水引が印刷されている封筒を使う場合は、黒白か黄色の水引が印刷されたものを使うとよいでしょう。
永代供養のお布施の書き方(表書き・裏書き)
永代供養の封筒の表書き

永代供養のお布施の表書きは、「お布施」や「御布施」としても構いませんし、そのまま「永代供養料」と書いても構いません。
なお、お布施と永代供養料を一緒に納める場合は「お布施」と書き、供養料として払う場合は「永代供養料」と書いた方がよいという考え方もあります。
また、浄土真宗では、死者の成仏を願う「供養」という考え方がないため、永代供養料の表書きには「永代経懇志」と書きます。
永代供養の封筒の裏書き

封筒の裏書きは、「中袋がある場合」と「中袋がない場合」で変わるので注意しましょう。
中袋がある場合は、表面に旧漢字で包んだ金額を書きます。頭に金、最後に也をつけ「金◯◯円也」と記入してください。裏面は、住所・氏名・電話番号を書いてください。
中袋がない場合は、裏面に金額・住所・氏名・電話番号をすべて記載します。裏面右側に金額、左側に住所・氏名・電話番号の順番で記入しましょう。
永代供養のお布施のよくある質問
永代供養にお布施は必要?
永代供養の場合でもお布施は必要です。永代供養をに依頼した場合、お布施が必要になるのは、「納骨法要」の時と、「年忌法要」の時です。
永代供養のお布施についての 詳細はこちら>
永代供養のお布施の表書きの書き方は?
永代供養のお布施の表書きは、「お布施」や「御布施」としても構いませんし、そのまま「永代供養料」と書いても構いません。
なお、浄土真宗では、死者の成仏を願う「供養」という考え方がないため、表書きには「永代経懇志」と書きます。
永代供養のお布施の表書きについての 詳細はこちら>
永代供養にかかる費用の相場

永代供養で最低限必要になる費用は、永代供養料、お布施、刻字料の3点です。それぞれ単独で請求される場合もあれば、セット料金としてまとめて支払う場合もあります。
なお、お墓の種類や、墓じまいも併せて行う場合など、状況に応じて他にも費用がかかることもあるため、契約時によく確認することをおすすめします。
永代供養料はお墓を維持、管理し、故人を供養するための費用です。多くの場合、永代供養料のなかに、墓所使用料も含まれています。
永代供養料の費用内訳としては、墓所使用料が2割、維持管理費が6割、法要料が2割程度とされています。通常のお墓に比べると比較的費用は抑えられますが、選び方によっては100万円を超えることも少なくありません。
刻字料は石碑や墓誌などに故人の名前を彫ってもらうための費用です。永代供養料に含まれている場合も多いですが、刻字自体の料金は3万円ほどが相場です。
全国の永代供養墓ランキング
全国の永代供養墓のランキングをご紹介します。永代供養墓をご検討の場合は参考にしてみてください。
関東












関西







中部




北海道・東北


中国・四国


九州・沖縄





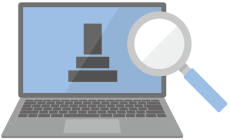
 かんたん
かんたん