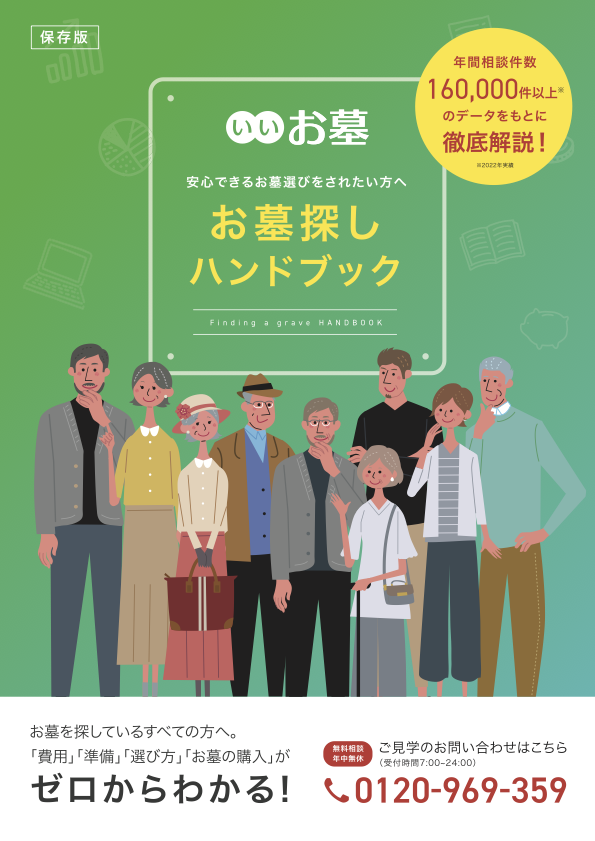3月の春のお彼岸、9月の秋のお彼岸。年2回のお彼岸の時期に毎年お墓参りに行かれる方も多いと思います。
この記事では、今年のお彼岸の日程、お彼岸でやるべきことや過ごし方、お彼岸でのお墓参りの方法、仏壇でのお供えなどについて詳しくご紹介します。
2024年(令和6年)のお彼岸はいつ?
2024年(令和6年)の「春のお彼岸」と「秋のお彼岸」のスケジュールはこちら。
春のお彼岸
3月17日(日)から3月23日(土)までの7日間で、お彼岸の中日となる春分の日は、3月20日(水・祝)です。
秋のお彼岸
9月19日(木)から9月25日(水)までの7日間で、お彼岸の中日となる秋分の日は、9月22日(日・祝)です。
お彼岸とは?
お彼岸とは、春分の日、秋分の日を中日(真中の日)とした前後3日、それぞれ7日間のことです。7日間の初日を「彼岸の入り」、7日間の最終日を「彼岸の明け」と言います。
また、春分の日や秋分の日は、死者やご先祖さまのいる世界(彼岸)と私たちが生きている世界(此岸)が最も通じやすくなると考えられており、この時期に死者やご先祖さまを供養することが古来から行われてきました。これは日本独特の風習といわれています。
お彼岸の時期にすること
お彼岸の時には、ご先祖さまの供養をすることがとても大切です。そのために、お墓参りに行ったり、仏壇・仏具の手入れや掃除を行ったりします。その際、春のお彼岸であれば「ぼたもち」を、秋のお彼岸であれば「おはぎ」をお供えします。
また、このお彼岸の時期には、お墓を購入するために霊園の見学に行く方も多いようです。


お彼岸でのお墓参り
普段は忙しくて、なかなかお墓参りに行けないという方は多いでしょう。お彼岸には、少し時間を作って家族そろってお墓参りに行きましょう。お墓参りの仕方は、家や地方によって異なりますが、一般的なお彼岸でのお墓参りの方法についてご紹介していきます。

お墓参りですること
- お墓の掃除
お墓についたらまず、お墓の掃除をしましょう。掃除を始める前に、お墓に手を合わせることを忘れないようにしましょう。そのあと、雑草を抜いたり、墓石の汚れを落としたり、お墓の掃除を始めます。 - お供えをする
墓石に水をかけてお清めします。次にお花やお菓子、おはぎやぼたもちをお供えします。お供えに向いているお花は、菊やリンドウなど、日持ちし枯れた時に散らからないものが好ましいです。 - お墓に手を合わせる
お線香をあげて、お墓に手を合わせます。最初に、いつも見守ってくださるご先祖様に感謝の気持ちを伝えます。次に、お願い事がある方は、お願いをしましょう。
お寺によっては、「彼岸会」を行うことがあるので、確認しましょう。


お彼岸での仏壇のお供え

お彼岸には、仏壇を掃除し、普段よりも少し豪華なお供え物をしましょう。お花と精進料理、おはぎやぼたもちなどをお供えするとよいでしょう。
お墓や仏壇にお供えした食べ物は、「仏様のおさがり」として、食べるのが供養になると言われているので、できるだけ早くいただきましょう。かたくなってしまったり食べられなくなった物は、無理して食べる必要はありません。
お彼岸の意味
修行によって迷いを脱し悟りを開いた彼方の岸を彼岸と言い、「布施」「持戒」「忍辱」「精進」「禅定」「智慧」の6つを修業することで、彼岸に行くことができるとされていました。
日本では、その浄土に渡るために、善事を行い、先祖に思いを馳せ、供養を行う期間を「彼岸」と言うようになりました。「彼岸」という言葉はインドで使われている言語の一つ、サンスクリット語の「パーラミター」(波羅蜜多)の漢訳で「到彼岸」の略だといわれています。
彼岸は極楽浄土とされており、西方の遥かかなたにあると考えられていました。そこで、太陽が真東から昇り真西に沈む「春分の日」と「秋分の日」は、現実の世である此方と彼岸の両方の世界が通じやすくなると考えられたため、「春分の日」と「秋分の日」を含めた前後の日に、ご先祖様の供養をする行事が行われるようになったと言われています。
お彼岸の歴史
お彼岸の起源は、諸説ありますが、はじまりは奈良時代ころだと言われています。
また、平安時代に編纂された『日本後紀』には、延暦二十五年(806年)の2月、「毎年春分と秋分を中心とした前後7日間『金剛般若波羅蜜多経』を崇道(すどう)天皇のために転読させた」という記録が残っています。これが、日本の歴史上最初のお彼岸法要の記録と言われています。非業の死を遂げた崇道天皇の祟りを鎮めるため、全国の寺院で彼岸法要が行われたそうです。
それから次第に、一般の人にも「お彼岸」は広まったとされています。仏教行事ですが、インドや中国にはありません。
お彼岸でやってはいけないことはある?
お彼岸は死者やご先祖さまを供養する時期であるため、結婚式やお引越し、病院へのお見舞いは避けた方がいいという話を聞いたことがある方がいるかもしれません。
しかし、結論から言えば「お彼岸にしてはいけないこと」はありません。
仏教ではお彼岸とは六波羅蜜の修行をする期間、すなわち自分を見つめ直す修行の期間であり、身を慎む期間ではありません。そのため、仏教では彼岸の時期の結婚や引っ越しを咎めてはいません。ただし、結婚式においては招待客のことを考えて、彼岸の結婚式は好ましくないという意見は一定数あります。
彼岸は死を連想させるから病院へのお見舞いは避けるべき、という考え方があります。これも大切なのは相手との関係性やどこまで配慮するかということでしょう。
また、彼岸花を持ち帰ってはいけない。そして家に持ち帰ると火事になるという迷信を聞いたことのある人もいるのではないかと思います。彼岸花は強烈な毒性があり、その毒性によって生活のさまざまな場面で人々に活用されてきたという側面がありますが、その毒性について警鐘を鳴らす意味合いから、そのような言い伝えが生まれたものと考えられます。
まとめ
お彼岸の日にちはその年によって異なりますが、春分の日の前後3日の7日間と秋分の日の前後3日の7日間ということに変わりはありません。
お彼岸ではぜひ家族揃ってお墓に行き、キレイに掃除をすることで、ご先祖様に生まれてきたことや、日ごろ見守ってくださることに感謝の気持ちをお伝えしましょう。


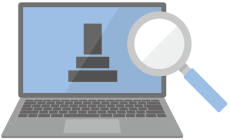
 かんたん
かんたん