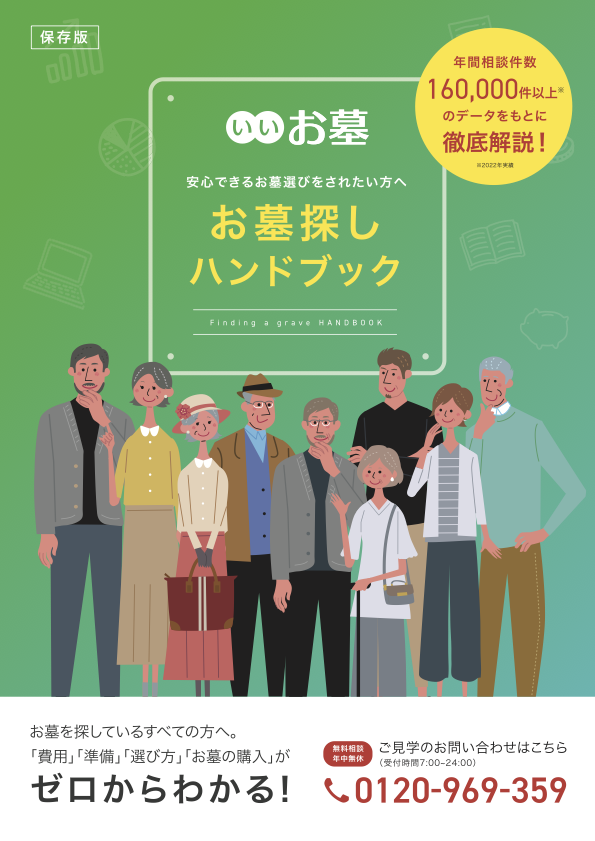お彼岸で意外と悩まれる方が多いのが「ぼたもち」と「おはぎ」の違い。
そもそも「ぼたもち」と「おはぎ」の違いとは何なのか、お彼岸で食べるのは一体どちらなのか……両者の違いを論じたものは多数ありますが、ありすぎてよく分からないという状況に陥る方も少なくないようです。
そこで今回は「ぼたもち」と「おはぎ」の見分け方に関する諸説をまとめ、結論として何がどう違うのかを解説します。
【結論】春のお彼岸は「ぼたもち」、秋のお彼岸は「おはぎ」
結論から言うと「ぼたもち」と「おはぎ」は同じものです。そして、名称の違いはそれぞれの季節に咲く花からきています。
春のお彼岸で食べるものは「ぼたもち」と呼び、春に花が咲く「牡丹(ぼたん)」が由来です。
秋のお彼岸で食べるものは「おはぎ」と呼び、秋に花が咲く「萩(はぎ)」が由来です。
ちなみに、夏は「夜船(よふね)」、冬は「北窓(きたまど)」と呼ばれます。
ぼたもちとおはぎの違い/諸説1「大きさが違う」
大きいものを「ぼたもち」
小さいものを「おはぎ」と呼ぶ
牡丹(ぼたん)は、花が大きく豪華なので、どかっと大きいのが「ぼたもち」。一方、萩(はぎ)の花は、小さくしとやかな感じなので、上品な小ぶりのものが「おはぎ」という説です。
ぼたもちとおはぎの違い/諸説2「材料が違う」
もち米で作られたものを「ぼたもち」
うるち米で作られたものを「おはぎ」と呼ぶ
もちの部分を構成しているお米の種類が異なり、「ぼたもち」はもち米、「おはぎ」はうるち米がそれぞれ使われているという説です。
しかし、料理レシピによっては、材料が「白米」「十六穀米」など、もち米でもうるち米でもない場合もあり、作り手や状況によって異なるのでそのたびに名称を変えるのはやや大変に思えます。
ぼたもちとおはぎの違い/諸説3「手加減が違う」
(もちのつき方が)容赦ないものを「ぼたもち」
(もちのつき方が)容赦あるものを「おはぎ」と呼ぶ
もち米をお餅になるまでついたものを「ぼたもち」と呼び、まだ粒が残る程度についたものを「おはぎ」と呼ぶという説です。
ぼたもちとおはぎの違い/諸説4「あんこが違う」
こしあんを用いたものを「ぼたもち」
つぶあんを用いたものを「おはぎ」と呼ぶ
もち自体ではなく「あんこ」の違いで呼び名が変わり、こしあんを用いているのが「ぼたもち」、つぶあんを用いているのが「おはぎ」という説です。
これは、あんこの材料となる小豆の収穫時期に由来すると言われます。小豆は秋に収穫されるため、秋に食べる「おはぎ」は採れたての小豆が使われ、粒のままでも皮も柔らかく美味しく食べられるため「つぶあん」を用いるとのことです。春になると小豆も時間が経って固くなるため、春に食べる「ぼたもち」には「こしあん」を使うというわけです。
さらに「ぼたもち」は牡丹の花のように「こしあん」のつるりとした感じ、「おはぎ」は萩の花のように「つぶあん」のつぶつぶした感じ、といった説もあります。