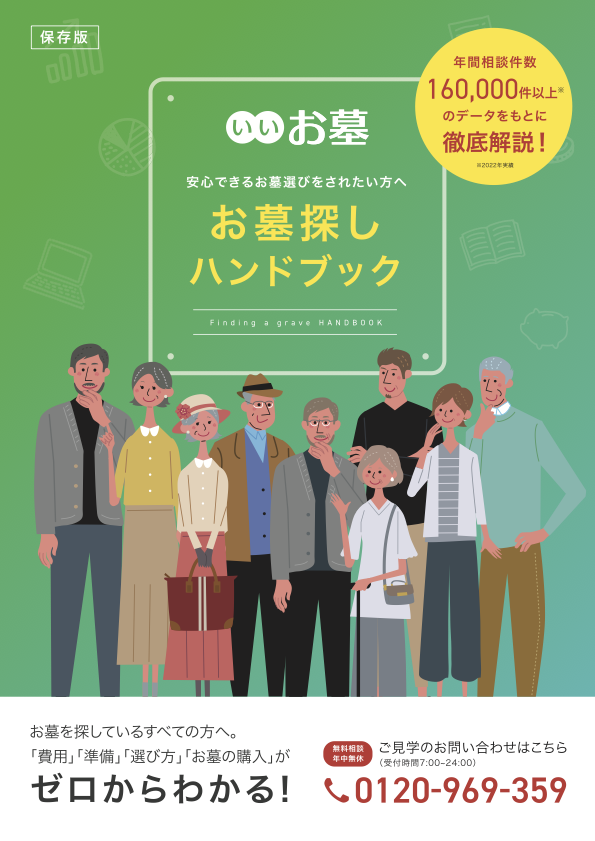永代供養墓(えいたいくようぼ)とは、遺族の代わりに霊園・寺院が遺骨を管理・供養するお墓。お墓の後継者が不要で、一般墓より費用がおさえやすいと、近年人気を集めているお墓です。
この記事では、永代供養墓の意味や種類、メリット・デメリット、注意点などをわかりやすく解説します。
永代供養墓(えいたいくようぼ)とは?

永代供養墓(えいたいくようぼ)とは、遺族の代わりに霊園・寺院が遺骨を管理・供養するお墓。霊園・寺院によって範囲は違いますが、お墓の掃除や故人の供養を永続的にまかせられます。
そのため永代供養墓には、お墓の後継者が必要ありません。残された家族の負担を減らせるのはもちろん、無縁仏や無縁墓になる心配も無用。また遺骨の有無に関係なく、生前に申し込めるのも特徴です。
永代供養墓は、核家族化・少子化・高齢化の影響で、「お墓を継承する子どもがいない」「残された家族に負担をかけたくない」といった人が増え、注目されるようになりました。ちなみに、永代供養墓のはじまりは、昭和60年、滋賀県大津市の比叡山延暦寺大霊園にできた「久遠墓」です。
永代供養墓にするとお墓はどうなる?
- 他人の遺骨とまとめて埋葬する
- 一定期間個別で納骨したあと合祀にする
永代供養墓には、他人の遺骨とまとめて埋葬するか、一定期間個別で納骨したあと合祀するか、大きく2つの埋葬方法があります。いずれにせよ最後は合祀される永代供養墓が多いですが、合祀のタイミングや個別の納骨期間は霊園・寺院によって違うので確認してください。
複数の遺骨を1つの区画にまとめて埋葬する方法。骨壺から遺骨を取り出して埋葬するため、一度合祀すると他人の遺骨と混ざって、個別に取り出せなくなります。
永代供養墓の期間は何年くらい?
前述したとおり、永代供養墓の個別納骨期間は、霊園・寺院によって違います。
ですが、17回忌、33回忌、50回忌といった年忌法要を区切りとする霊園・寺院が多い様子。なかでも、弔い上げとされる33回忌まで遺骨を安置する永代供養墓がよく見られます。
永代供養墓の種類と費用相場
永代供養墓の費用相場は5万円〜150万円ほど。ですが実際には、永代供養墓の種類や供養の期間、遺骨の扱いなどで費用は変動します。
- 合祀型(合祀墓):5万円~30万円
- 集合型(集合墓):20万円~60万円
- 個別型(個人墓):50万円〜150万円
- 納骨堂型の永代供養墓:10万円~150万円
- 樹木葬型の永代供養墓:5万円~150万円
永代供養墓は、埋葬方法やお墓の形態によって、大きく5つの種類にわけられます。ここからは、永代供養墓の種類ごとの特徴と費用相場を確認していきましょう。
合祀型(合祀墓)の永代供養墓:5万円~30万円

合祀型は、他人の遺骨とまとめて、共通のお墓に埋葬する永代供養墓。他人の遺骨と混ざってしまうため、一度納骨すると個々の遺骨を取り出せません。合祀型は、永代供養墓でもっとも一般的な種類で、墳丘や塔、モニュメントなどさまざまな形態があります。
また、合祀型の永代供養墓の相場は5万円~30万円で、他の永代供養墓より費用をおさえられます。
集合型(集合墓)の永代供養墓:20万円~60万円

集合型は、共通のお墓へ個別に遺骨を埋葬する永代供養墓。専用の区画があったり、骨壺に入れて納骨したりするため、合祀型と違って他人と遺骨が混ざりません。一定期間は個別で保管されますが、期間が終わると合祀されます。
集合型の相場は20万円~60万円と、合祀型と個別型の中間の価格帯です。
個別型(個人墓)の永代供養墓:50万円〜150万円

個別型は、個人単位で遺骨を埋葬する永代供養墓です。契約期間中は個別のお墓で納骨・供養して、終了後は合祀墓に移動する霊園・寺院がほとんど。ただなかには、個別納骨期間の制限がなく、合祀されない永代供養墓もあります。
個別型の費用相場は50万円〜150万円と、永代供養墓のなかでもっとも高額です。合祀するまで個人のお墓や納骨スペースが必要なため、一般墓と同じくらいの費用がかかります。
納骨堂型の永代供養墓:10万円~150万円

納骨堂とは、遺骨を納めるための施設のこと。建物内に多数の収骨スペースがあり、個々の区画を購入して納骨・参拝できます。納骨堂型の永代供養墓も一定期間経過すると合祀されるのが通例です。
納骨堂は、ロッカー式・仏壇式・機械式の3つのタイプに大きくわけられ、それぞれ費用相場が違います。1人用のロッカー式は10万円〜30万円、仏壇式は30万円〜150万円、自動搬送式は50万円〜150万円が相場です。また、2024年にいいお墓が実施した「第15回お墓の消費者全国実態調査」によると、納骨堂の全国平均購入価格は80.3万円でした。
樹木葬型の永代供養墓:5万円~150万円

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓。埋葬方法や遺骨の扱いによって、合祀型・集合型・個別型と3つのタイプに分けられます。
樹木葬の費用は、合祀型が5万円〜30万円、集合型が10万円〜60万円、個別型が20万円〜150万円。個別のスペースや樹木が用意されている樹木葬ほど、高額になります。ちなみに「第15回お墓の消費者全国実態調査」では、樹木葬の全国平均購入価格は約63.7万円でした。
永代供養墓の費用は誰が支払う?
永代供養墓に限らず、お墓の費用は祭祀財産の継承権を持つ人(祭祀継承者)が支払うのが一般的です。また、祭祀継承者だけにまかせず、家族や親戚が協力して支払うご家庭も少なくありません。
さらに、永代供養墓は生前に購入できるため、本人が支払いを済ませておくケースもあります。
永代供養墓のメリットとデメリット
永代供養墓のメリット
- お墓の後継者がいらない
- お墓の維持・管理が不要
- 一般的なお墓より比較的安価
- 宗旨宗派不問の受け入れが多い
- 生前に申し込み・購入できる
永代供養墓のメリットは、お墓の後継者の有無に関わらず申し込めること。子どもがいなかったり、遠方に住んでいたりしてお墓の継承が難しくても、永代供養墓なら問題ありません。お墓の管理は霊園・寺院が行ってくれるため、家族の負担を減らせるのもメリットです。
また、永代供養墓は一般墓より低コストで、金銭的なメリットから選択する方が増えています。さらに宗旨宗派不問の永代供養墓が多く、生前に購入できるのも魅力です。
永代供養墓のデメリット
- いずれは遺骨が合祀される
- 従来のお墓参りができない
- 家族・親族の理解が必要
永代供養墓のデメリットは、いずれ遺骨が合祀されること。一度合祀されると、他人の遺骨と混ざってしまうため、個々の遺骨を取り出せなくなります。
また永代供養墓には、線香・ロウソクが禁止されていたり、参拝スペースが限られていたりする霊園・寺院があります。従来のお墓参りができず、物足りなさや不満を感じるご家族もいるかもしれません。永代供養墓は、遺骨の扱いやお墓参りなどが従来のお墓と違うため、家族・親族の理解がないと選択するのが難しいでしょう。
永代供養墓に向いている人・向いていない人
永代供養墓に向いている人
- お墓の継承者がいない
- 家族に負担をかけたくない
- 先祖代々のお墓に入りたくない
霊園や寺院にお墓の管理・供養をまかせられる永代供養墓は、お墓の継承者がいない人に向いています。また継承する家族がいても、お墓を管理する負担をかけたくないと考えて永代供養墓を選ぶ人も多いです。
その他、「家族と疎遠だから」「独身だから」「夫婦だけでお墓に入りたいから」といった理由で、先祖代々のお墓に入りたくない人にも永代供養墓は適しています。
永代供養墓に向いていない人
- 家族が永代供養墓に反対している
- 遺骨を取り出す可能性がある
本人が希望していても、家族から永代供養墓を反対されている人は、まず周囲の理解を得ることからはじめましょう。家族と話し合い、全員が納得したうえで永代供養墓を選択するのが重要です。
また永代供養墓では、一度合祀されると遺骨を取り出せません。改葬や手元供養、散骨など、後日遺骨を取り出す可能性がある人は、永代供養墓には向いていないでしょう。
永代供養墓の選び方と注意点
- 立地(アクセス・交通手段)
- 費用(総額・内訳)
- 施設(種類・設備)
- 管理主体(宗旨宗派・規約)
- 供養方法(納骨期間・法要回数)
永代供養墓を選ぶときは、こちらの5つポイントをチェックするのが大切。
立地や施設は、永代供養墓を現地見学して自分の目で確かめてください。管理主体や供養方法についても、現地見学とあわせて運営元に質問するとスムーズです。また、費用は霊園・寺院によって幅があるため、複数の永代供養墓の見積もりを取得して比較検討するとよいでしょう。
永代供養墓に関するよくある質問
今あるお墓から永代供養墓に改葬する流れは?
1.移転元の寺院・霊園に改葬の申し出をする
既存のお墓がある寺院・霊園に改葬の申し出をして、「埋葬証明書」を発行してもらいます。
2.改葬許可申請書に署名押印をもらう
既存のお墓がある地域の役所から「改葬許可申請書」を取得し、既存のお墓・移転先の永代供養墓の管理者に署名押印してもらいます。
3.移転先の永代供養墓に申し込み・契約する
移転先の永代供養墓に申し込みし、契約後に発行される「受入許可書」を受け取ります。
4.改葬許可申請をする
「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受入許可書」を役所に提出して、「改葬許可証」を発行してもらいます。
5.遺骨を取り出し、永代供養墓に埋葬する
既存のお墓で閉眼供養をしたあと、遺骨を取り出します。それから移転先の永代供養墓に「改葬許可書」を提出し、遺骨を納めます。
墓じまいと永代供養墓の違いは?
墓じまいとは、今あるお墓を片付けて更地にし、墓地の使用権を管理者に返還すること。墓じまいをすると、元々あったお墓を撤去するため、遺骨を新しい場所に移さなければなりません。
一方の永代供養は、霊園や寺院に遺骨を管理・供養してもらうことを指します。永代供養は、墓じまいをしたあと、遺骨を納骨・供養するときの選択肢のひとつ。その他、新しく購入した一般墓に移したり、手元供養・散骨といったお墓が不要な供養方法を選んだりすることも可能です。
浄土真宗・浄土宗でも永代供養墓を利用できる?
浄土真宗・浄土宗では、故人は死後すぐに成仏して極楽浄土へ旅立ち、そこで生まれ変わるとされています。そのため、死者の成仏を願う「追善供養」の考え方がなく、お墓は故人の魂や霊が宿る場所ではありません。
ですが、「供養」の概念のない浄土真宗・浄土宗でも、永代供養墓を利用することは可能です。
現在は「後継者がいない人のためのお墓」を「永代供養墓」と呼ぶことが多く、永代供養墓を募集している浄土真宗・浄土宗のお寺も存在します。浄土真宗・浄土宗を信仰していて永代供養墓を希望するなら、永代供養墓を取り扱っている浄土真宗・浄土宗の寺院に依頼するか、永代供養墓を取り扱っている宗旨不問の霊園・寺院を利用してください。
永代供養墓にお布施は必要?
通常のお墓と同じように、永代供養墓でもお布施は必要です。永代供養墓に遺骨を納骨する「納骨法要」で、僧侶にお布施を渡します。
納骨法要におけるお布施の相場は3万円〜5万円。開眼供養(魂入れ)をするなら、納骨法要とあわせて10万円のお布施をお渡しするのが一般的です。永代供養料に納骨法要のお布施代が含まれている霊園・寺院もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
永代供養墓の比較検討なら「いいお墓」へ
後継者が不要で、霊園・寺院にお墓の管理をまかせられる永代供養墓ですが、納骨やお墓参りのスタイルは従来のお墓とは違うため注意が必要。メリットだけでなく、デメリットもしっかり検討したうえで、永代供養墓を選択するのが大切です。
また永代供養墓を探すときは、複数の霊園・寺院を比較検討してください。資料請求はもちろん、見積もりの取得や現地見学をして比較することで、理想に近い永代供養墓が見つかりやすいです。
「いいお墓」では、エリアや条件ごとに永代供養墓を一覧でチェックできます。資料請求や現地見学の予約はもちろん、不安や疑問がありましたら無料の電話相談も受け付けています。
永代供養墓の購入を検討されている方は、ぜひお気軽に「いいお墓」へご相談ください。


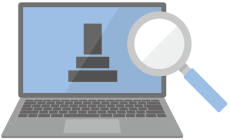
 かんたん
かんたん