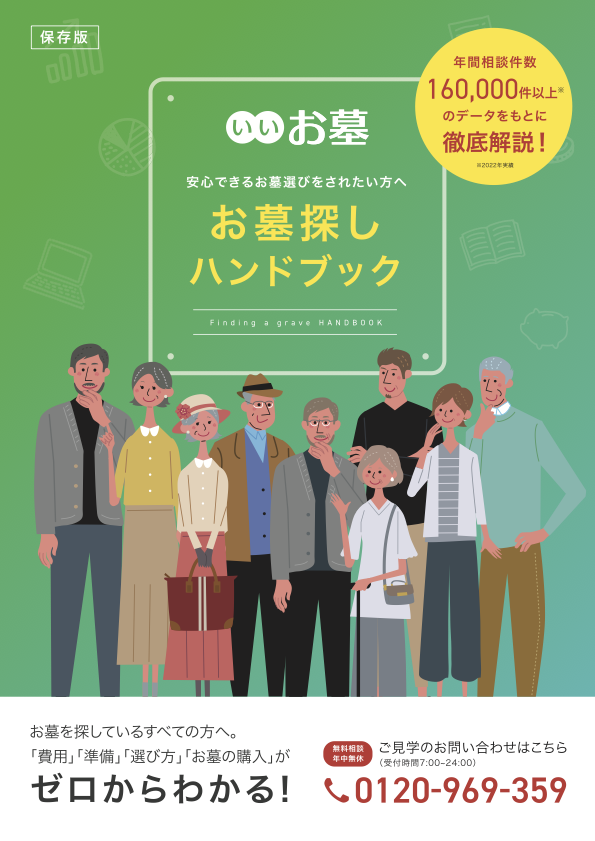お墓の購入は、一生に一度あるかないか。知識がないのは当たり前です。後悔しないお墓を選びをするには、事前に基礎知識を身に着けておくのが大切。わからないことを曖昧にせず、こだわりをもってお墓選びをすることで失敗を防げます。
この記事では、納得のいく霊園・墓地探し、後悔しないお墓・墓石・石材店選びのためのトピックをわかりやすく解説します。
そもそもお墓とは?
家は一生ものと言いますが、お墓は子々孫々末代に至るまで引き継いでいく一家の拠り所。
仏壇や位牌も故人の魂が入っているとされていますが、お墓と違って遺骨を納めたり、ご本尊様を祀ったりはしていません。故人の戒名・法号と、死亡年月日を記してお祀りするのが位牌(浄土真宗では位牌は用いません)。そして、仏教各宗派の本尊仏とともに、位牌や法名軸などをお祀りするのが仏壇です。
わざわざ足を運んでお参りするお墓は、故人を身近に感じる仏壇とは異なる存在。故人と向き合い、思いを巡らせる貴重な時間を生み出してくれる一種のシンボルとして、私たちの生活の一部となっています。また、近年は価値観やライフスタイルの変化により、さまざまなタイプの「お墓」や霊園・墓地が出てきています。
墓石から見たお墓(一般墓)の種類
- 和型墓石
- 洋型墓石
- デザイン墓石
お墓の形や大きさに、本来決まりはありません。ですが、霊園・墓地には決められた区画があり、墓石施工に関するガイドラインが存在しています。
墓石から見たお墓の主な種類は、和型墓石・洋型墓石・デザイン墓石の3つ。その他、「五輪塔」「宝篋印塔」「宝塔・多宝塔」「無縫塔」などの種類もあります。
ご自身の希望と霊園・墓地のルールをすり合わせるために、墓石(一般墓)の主な種類を確認しておきましょう。
和型墓石

和型墓石は、江戸時代に一般化した伝統的な墓石。お墓といえば、和型墓石をイメージする方が多いです。
和型墓石は、台石の上に、竿石と呼ばれる塔状の石を建てます。竿石とは、お墓の縦に長い部分の石で、正面に家名や文字を刻みます。
洋型墓石

洋型墓石は、厚めの台石の上に、低く幅の広い石を載せた形が一般的。高さがないぶん倒れにくく、最近は洋型墓石を選ぶ人が増えています。
また洋型墓石には、「オルガン」型という種類があります。オルガン型は棹石の正面を斜めにカットした墓石で、正面から見ると横長の長方形、横から見ると台形です。角度のついた形状がオルガンに似ていることから、「オルガン」型と呼ばれます。
デザイン墓石

デザイン墓石は、一般的な形式にとらわれないオリジナルのデザインが施された墓石。近年は、家を基軸としていたお墓が故人主体に変化してきていることから、個性的なデザインの墓石を求める方が増えています。自由な形式を認める霊園では、故人の職業や趣味、思想などを表した意匠的な墓石も見られます。
お墓(一般墓)の構造と名称
一般的な和型墓石を例に、お墓の構造と各部分の名称を紹介します。
納骨室(カロート)
納骨室(カロート)とは、墓石の下にある遺骨を納めるスペース。石やコンクリートで作られていて、形式は地域によって異なります。芝台の地下に納骨室を作る陸カロートや、地上に納骨室を作る丘カロートがあります。
水鉢
水鉢は、先祖に水を供えるための鉢で、墓石の手前に作られるお墓が多いです。
香炉
香炉は、お線香をお供えする部分。線香を立ててお供えする「立ち置き型」と、寝かせてお供えする「くりぬき型」があります。
花立
花立は、お花を立てるために墓石に備え付けられています。水鉢を挟んで、左右対称に設置します。
墓誌
墓誌は、お墓に埋葬されている先祖の戒名生年月日・没年月日などの「銘」を刻む石板です。故人の功績を刻むこともあります。
卒塔婆立て
卒塔婆立ては、卒塔婆を立てて支えるもの。石製や金属製など、さまざまな種類がありますが、機能に変わりはありません。
卒塔婆は別名「塔婆(とうば)」ともいい、仏塔を意味しますが、「追善供養のために経文や題目などを書き、お墓の後ろに立てる塔の形をした縦長の木片」です。宗派によっては使用しない場合もあります。
供養方法別に見たお墓の種類
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 樹木葬
昨今では、石材を使った従来型のお墓だけではなく、新たな供養埋葬方法のお墓も注目を集めています。
永代供養墓

永代供養墓とは、継承者に代わって霊園・寺院が管理・供養してくれるお墓のこと。お墓の承継者がいなかったり、家族に面倒をかけたくなかったりする人を中心に、近年需要が高まっています。
永代供養墓は、お墓の継承や維持・管理が不要なのはもちろん、お墓の形態によって費用をおさえやすいです。ただ、ひとくちに永代供養墓といっても、遺骨を合祀・合葬するお墓から個別に保管するお墓、納骨場所が地下だったり地上だったりと、さまざまなタイプがあります。
納骨堂

納骨堂とは、骨壷に入った遺骨を安置する建物のこと。公営霊園や寺院内に設置されている施設が多く、個人・夫婦・家族などの単位で遺骨を収蔵します。
納骨堂は屋内施設がほとんどなので、駅近くで足を運びやすく、天候に左右されずお墓参りできると人気。また、基本的に墓石が不要なため、コストをおさえやすいのもメリットです。近年では、お墓を相続する家族のいない方が、納骨堂に永代供養を頼むことも多くなっています。
樹木葬

樹木葬とは、”自然に還る”というコンセプトのもと、墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓。散骨と並ぶ自然葬の一種で、近年希望者が増えている埋葬のスタイルです。
樹木葬のメリットは、一般墓と比べて費用をおさえられる点。なぜなら、墓石が不要なので墓石代を節約できますし、一般墓より広いスペースが必要ないからです。最近では、既にあるお墓に納骨されている遺骨の一部を墓じまいして、一部を樹木葬にお引越し、つまり改葬する方も増えています。
霊園・墓地の種類

- 公営霊園
- 民営霊園
- 寺院墓地
霊園・墓地は、経営母体によって大きく3種類に分けられます。それぞれの特徴や違い、メリット・デメリットを確認しておきましょう。
公営霊園
公営霊園は、都道府県や市町村などの地方自治体が管理・運営している霊園です。各都道府県や市区町村の役所に、申し込み・問い合わせをします。
公営霊園は、墓地にとって重要な永続性が保証されており、永代使用料や管理費が安くおさえられます。また自治体が管理しているので、宗旨宗派による制約は一切ありません。
ただし契約には、「現住所がその自治体にある」「お墓の承継者がいる」「遺骨がある」などの条件があります。募集も随時行っているわけではなく、希望者が多いと抽選制となるため、購入が困難な公営霊園もあります。また、大規模開発の霊園が多いので、立地が不便なところも少なくありません。申し込みにあたっては十分な検討が必要です。
民営霊園
民営霊園は、財団法人や社団法人、宗教法人が事業主体となる霊園。民間企業が委託を受けて運営している民営霊園もあります。
公営霊園に比べると永代使用料や管理費は割高で、石材店は指定されていることが多いです。ただ、遺骨の有無や宗旨宗派で、申し込みに制限がかけられることはほとんどありません。また霊園によっては、お墓のデザインや大きさを自由に選べます。
寺院墓地
寺院墓地は、寺院の境内地にあり、その寺院が管理している墓地のこと。
お寺の檀家になることが前提となっている寺院墓地がほとんどなので、必ず確認してください。檀家になる場合は、寺院の住職にお寺の行事やお付き合いの仕方について確認しておくと安心でしょう。同時に、長く信頼してお付き合いできるか、住職の人柄も考慮に入れる必要があります。
寺院墓地のメリットは、手厚く供養していただける点です。お墓が境内にあるので法要を本堂で営むことができ、依頼すれば僧侶が読経して供養してくれます。お寺の中にあるので、管理面も安心です。
お墓の値段と費用内訳

| 2020年(n=777) | 2021年(n=455) | 2022年(n=859) | 2023年(n=585) | 2024年(n=1620) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納骨堂 | 87.7万円 | 91.3万円 | 83.6万円 | 77.6万円 | 80.3万円 |
| 一般墓 | 176.2万円 | 169.0万円 | 158.7万円 | 152.4万円 | 149.5万円 |
| 樹木葬 | 68.8万円 | 71.7万円 | 69.6万円 | 66.9万円 | 63.7万円 |
鎌倉新書が実施した「第15回お墓の消費者全国実態調査(2024年)」によると、一般的なお墓の平均購入価格は149.5万円。納骨堂は平均80.3万円、樹木葬は平均63.7万円となっています。
一般墓にかかる費用の内訳は、墓石代・永代使用料・管理料の3つ。墓石費用は約50万円〜150万円、永代使用料は約30万円〜100万円、墓地管理費は年間1万円前後が費用相場です。納骨堂や樹木葬は、墓石を使用しないお墓が主流なので、墓石代がいらないぶん費用をおさえられます。
お墓を購入するタイミングと流れ
- どんなお墓を建てるか決める
- お墓を建てる霊園・寺院を探す
- 墓地購入の契約をする
- 墓石を決める
- お墓を建てる
お墓を購入する流れは、大きく5つのステップにわけられます。どんなお墓を建てるか決めたあと、霊園・寺院を探していきましょう。霊園・寺院が決まったら、墓地購入の契約をして墓石を選び、お墓を建立します。
また、先祖代々のお墓がある場合は、四十九日法要とあわせて納骨式をするご家庭がほとんど。お墓がない場合は、一周忌を目安に新しくお墓を購入する流れが多いようです。
後悔しないお墓の選び方
お墓を選ぶときは、必ず複数の霊園・寺院を比較・検討すること。気になる霊園は資料請求して、現地見学で実際に足を運んでみてください。
複数の霊園から資料請求する
気になる霊園を複数探し、資料を請求して比較・検討しましょう。
- お墓の種類(一般墓・納骨堂・樹木葬)
- 墓石の種類(和型墓石・洋型墓石・デザイン墓石)
- 経営母体(公営霊園・民間霊園・寺院墓地)
など、種類や運営母体の違うお墓を比べることで、より自分の希望に近づけます。また同じ条件のお墓も調べ、一般的な設備や費用感を確認しておくと安心です。
霊園の現地見学をする
条件に合う霊園が絞り込めたら、必ず現地見学をしてください。霊園の雰囲気や管理状況、事務所の対応など、資料だけではわからないポイントがたくさんあります。
また、家族がお墓参りをしやすいよう、最寄り駅からの距離や交通手段、霊園の雨の日対策なども確認しておきましょう。
墓石・石材店の選び方
霊園・墓地の場所が決まったら、次は墓石選びです。あらかじめ墓石のことを知って、イメージや要望を明確にしておけばその後の流れがスムーズになります。
墓石・石材店選びのチェックポイント
- 石のサンプルを手にとって、石の色合いや艶を確認する
- 3年以上経ったお墓の墓石を見る(建立年月日から判別)
- 石の種類・使用量・加工・施工などで費用が変動する
- チラシやインターネットの表示価格で判断しない(表示されているのは標準的な価格)
- 「国産=いい石」「中国産=粗悪」といった偏見は持たない
墓石・石材店選びの注意点
「白御影石」「黒御影石」など、石の名前だけを見て選ぶ方は少なくありません。ですが、ひとくちに御影石と言ってもたくさんの種類があり、品質や価格の差も千差万別。チラシや広告では、安い石種や標準的な価格を前面に出している石材店が多いです。
広告の表示価格だけで墓石・石材店を選ぶと、「石材を変えたら、価格が2倍になった」「石種を変えただけで値段が80万も上がった」ということになりかねません。墓石材の種類や価値の知識をもっている人は稀です。霊園・石材店のチラシやインターネットの表示価格だけで、墓石を判断しないようにしましょう。


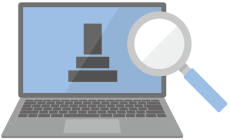
 かんたん
かんたん