書を捨てよ、町へ出よう

寺山修司の命日は5 月4 日。有名な「五月の詩」で「僕は五月に誕生した」と宣言した若葉の季節に亡くなった。彼のお墓は高尾霊園にある。

墓石の上には開きっ放しの本のレリーフが置かれている。「書を捨てよ、町へ出よう」と当時の若者を鼓舞した寺山修司が、書をそのままに町へと出かけた状態を暗示しているのかもしれない。
鬼才、異才、前衛の天才など様々に呼び表された寺山修司が活躍したジャンルは多岐にわたっている。
早熟な中学時代からの俳句、短歌、詩作に始まり、ラジオドラマ、小説、散文、演劇、映画、流行歌作詞、ボクシング・競馬評論等に至るまでまさに疾風のように駆け抜けていったといえる。
みずみずしい果実のような短歌

活躍の場がどうあれ、寺山の原点はやはり俳句と短歌に代表される短詩型の文学にあったことだけは確かであろう。
初期歌編から短歌研究新人賞を受賞した「チェホフ祭」などの一連の短歌作品は、その清新さ、透明に包んだ果実そのままのようなみずみずしさで決して色褪せることのない青春のある一瞬を紛れもなく描画しているように思われる。
また単なる叙情にとどまらず、「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」に代表される、当時の時代を撃つような焦燥や彷徨への思い。
そして「田園に死す」における土着的な負の祝祭空間のような歌の一群。その後の彼の表現は、いずれもこれらの短歌で実現された様々な形の変奏であり続けたとも言えるのではないか。
言葉の人としての最期
後年、演劇実験室「天井桟敷」を設立して以降の寺山の活動は明らかに演劇を中心に据えて、こぢんまりとした日常や小市民的な守りの殻を揺さぶり、ある種のアジテーションやスキャンダルに結びつくような「動」を喚起する作風が多く見られるようになった。
競馬やボクシングなどの「行為」への興味も同様であろう。それには寺山が若くして重篤な入院生活を余儀なくされたことの裏返しによる意識も背景にあっただろう。
その意味でアクションや行動を示唆する人のようにみえて、作品の根源には一貫して、淋しさ(寺山は父を早くに亡くした一人っ子であった)や遠からぬ死の意識が流れ続けていたように思われる。
絶筆となった、散文詩ともエッセイともつかぬ小品「墓場まで何マイル?」の中に以下のような文章がある。
「私は肝硬変で死ぬだろう。そのことだけははっきりしている。だが、だからと言って墓は建てて欲しくない。私の墓は、私のことばであれば、充分」
何事かへの行動を呼びかけながら最後まで「言葉の人」であることを決して手放さずに、途方もない通行者としてあらゆるジャンルを瞬時に渡っていったとも言えるだろう。


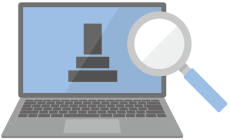
 かんたん
かんたん