三島作品にも通ずる、虚ろな雰囲気さえ醸す平岡家の清楚な墓石
三島由紀夫(本名:平岡公威)の墓は多磨霊園の一角にある。それは個人名が墓名碑となっているお墓ではなく、代々高級官僚を務めた平岡家の墓として祖父母、両親や夫人らと共に弔われて静かに佇んでいる。
三島の華美な文学活動やセンセーショナルな活躍ぶりに対比すると、お墓の佇まいはむしろひっそりとして目立たないといった方が良い。

自決という特異な最期を終えたこともあり、その墓は個の死者としての存在感をあまり訴えず、どこか無名の列に連なるように清楚に建立された墓石のようにも見える。それはまた、彼の遺作「天人五衰」で主人公の本多がラストで松枝清顕の恋人であった聡子(尼となって出家)を寺に訪ねてゆくとき、何もない場所に来てしまったと感じたような虚ろな雰囲気にも通じているように思えるから不思議だ。
決して時代に迎合せず、時代の寵児として活躍したが…
三島由紀夫は戦後文学の旗手として早熟の才を謳われ、詩から小説、戯曲、エッセイまで幅広く手がけ、45年という長くはない生涯の間にいずれも一級の作品を残し、1963年にはノーベル賞の候補にもなっている(最終候補には残らず)。 小説の代表作は「金閣寺」「潮騒」「午後の曳航」など、戯曲でも「近代能楽集」「サド侯爵夫人」「鹿鳴館」など記念碑的な作品群を擁し、小説よりも戯曲家としてその力量を評価する見方も多い。
小説の代表作は「金閣寺」「潮騒」「午後の曳航」など、戯曲でも「近代能楽集」「サド侯爵夫人」「鹿鳴館」など記念碑的な作品群を擁し、小説よりも戯曲家としてその力量を評価する見方も多い。
華美な文体でレトリックを駆使し、人工的・装飾的・思弁的な作品内容が多い印象だが、戦後の時代と併走しつつ、時代に決して迎合せずに時代の寵児としてむしろ昭和の高度成長時代を揺さぶり、先導していたように思われる。
後半生は時代精神との対立、滅びの感覚が鮮明に
だが、その後半生は、当時経済先進国への道をひた走り始めた日本の時代精神との対立を次第に鮮明にして、滅びの感覚がより研ぎ澄まされていき、やがて楯の会の活動から自決に至る顛末としてあまりにも有名だが、今もさまざまな解釈を拒んで死の理由は謎のままに留められているようだ。

彼は晩年に日本に向けて有名な預言を残している。「無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであろう」と。―その預言の向こうに今日の日本のさまざまな衰退の影を思うとき、なおさら深い感慨を抱かずにはいられない。



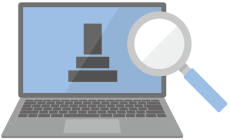
 かんたん
かんたん